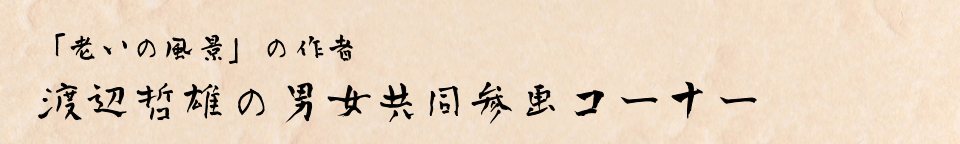- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 明日は快晴
明日は快晴
慎吾が不機嫌な顔で黙々と箸を運んでいる。父親の武夫はというと、これもまた苦虫を噛み潰したような表情でビールを飲んでいた。
「ごちそうさま」
ボソリとつぶやいて慎吾が席を立とうとすると、
「慎吾、ちょっと待て!」
武夫がバン!とテーブルを叩きながら立ち上がった。
「お前、明日釣りに行けなくなったことがそんなに気に入らないか!」
「お父さん」
姉の奈津子が間に入ろうとすると、
「女は黙っていなさい!」
武夫の目はアルコールですっかり充血している。こうなるともう、奈津子どころか、母親の和子にだってどうすることもできない。
「いいか慎吾、お父さんだって疲れてるんだ。何も好きこのんでゴルフに行くわけじゃない。しかし男には断り切れない付き合いってものがあるんだ。それで仕事がうまく行く。仕事がうまく行ってるからこそ、この家のローンだって払って行けるし、お前たちの服だって買ってやれるんだ。それなのにお前の態度は何だ!いつまでも女の腐ったのみたいにうじうじしてるんじゃないぞ!」
「…」
慎吾はよほど悔しかったのだろう。武夫の顔をにらみつけたまま、両手のこぶしをしっかりと握りしめている。
いつもなら、ふてくされた慎吾は黙って部屋に引きこもり、武夫は腹立ちまぎれにもう一本ビールを抜いて、それで戦いは終りになる。ところが今日は違っていた。気まずい沈黙にたまりかねたように、奈津子が立ち上がってこう叫んだのだ。
「お父さん!そんな言い方ってないと思うわ!」
普段、穏やかな奈津子にしては思いがけないくらい厳しい口調に、武夫は少したじろいだ。
「お父さんは慎吾と約束をしたのよ。慎吾は海釣りの本を買って来て読んでたわ。ゴルフの約束をするのなら慎吾に断ってからにすべきだったのよ。お仕事が大変なことはみんな分かってるつもりだし、感謝もしているわ。だから、ちゃんと相談すれば慎吾だって納得したはずよ。でもね、誰のおかげで食べてゆけるかってことと、今度のことはどういう関係があるの?」
「お、お姉ちゃん…」
慎吾が慌てて奈津子のブラウスの袖を引っ張ったが、
「私、今日は言わせてもらうわ」
奈津子は引き下がらない。
「ねえ、お父さん、もしこの家にお母さんがいなかったら、お父さんは今までのように働けたと思う?私たち子どもの面倒を見ながら残業するわけには行かないわ。もちろん日曜日にゴルフに出かけるわけにも行かないわ。いいえ、私たちがもっと小さかった頃には、会社に行くことだって難しかったかも?お父さんが働いてくれるからお母さんが家にいられるのと同じように、お母さんが家にいてくれるからお父さんが働けるんだとしたら、自分一人でこの家の生活を支えているように言うのは間違いだと思うわ」
「…」
「それにね、お父さんは何かというとすぐに女は黙っていなさいって言うけれど、そういう言い方も気分が悪いわ。さっきも慎吾に女の腐ったのみたいって言ったけど、女が腐ったらいったいどうだっていうの?」
「いや、それはつまりその…言葉のあやで…」
すっかり追い詰められた形の武夫に、
「奈津子、もうやめなさい。お父さんだって分かっているのよ」
和子が助け船を出した。
「分かっていながら威張ったり威張られたり…それも許し合える家族になりたいって、母さん思っているのよ」
その夜遅く、コーヒーを入れながら和子が尋ねた。
「あなた、本当にいいの?」
「ああ、どうしてもってわけじゃないんだ」
武夫が釣り竿を準備しながら答えた。
「部長には電話を入れておくよ。おれも仕事って言えば何でも許されてしまうような変な甘えがあってね。考えてみれば、本当はおれ自身がゴルフに行きたかったような気もするんだ。それにしても、今日は奈津子のやつに随分教えられたよ」
「子どもだとばかり思っていたけれど、中学三年生といえばもう立派な大人なんですね」
「いやいや、立派なおんなというべきだよ、あいつは…。あ、そうそう、天気予報だ」
武夫がスイッチを入れたテレビのスピーカーからは、明日は快晴であるというアナウンサーの弾んだ声が流れていた。
終