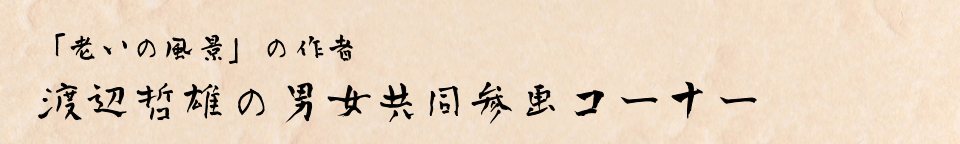- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 女の病室
女の病室
妙子が笑った。
脳出血で倒れ、手術で一命を取りとめた妙子は、集中治療室を経て個室に移った頃から、栄吉が声をかけながら汗を拭ってやると、かすかではあるが微笑むようになった。
それが栄吉には嬉しかった。
三十年前、原因不明の下痢と食欲不振が続いた挙句、栄吉の父親が五十代で衰弱死した。
「八屋源を…頼む…」
いまわの際の源一の手を握って、
「死んだらあかん!死んだらあかん!」
静子はただただ泣き崩れ、栄吉はおろおろとうろたえていたが、その傍らで、
「お義父さん、お店は必ず守りますよ!」
大声でそう応えた瞬間に、妙子の人生が変わった。子どもには恵まれなかったが、サラリーマンの妻として家庭を守ることに幸せを感じていたはずの妙子が、小さな八百屋のおカミさんになった。仕入れから資金繰りまで一人でこなす妙子を放ってはおけず、栄吉も会社を辞めて家業を継いだ。郊外には次々と大型スーパーが進出したが、明るい応対と気配りと、何よりも工夫した惣菜の味が評判で、八屋源はかろうじて町内の台所であり続けた。静子を送り、店を畳み、わずかな貯えを頼りに穏やかな年金生活に入った矢先の妙子の脳出血だった。
「なあに、病院を我が家だと思えばええ。俺はいつだってお前の側にいてやるぞ」
栄吉は、もの言わぬ妻に約束したが、大部屋に移ると同時に、女性の部屋に男性がいるのは困るという理由で、師長から付き添いを遠慮するよう言い渡された。
「どうしていけないのですか?男の部屋には女が付き添っているじゃありませんか。私は妻の側にいてやりたいんです」
という栄吉の抗議を、師長は一蹴した。
「男と女は違うんです。どうしてもであれば、有料個室に移っていただきます。男の人が一緒だと他の患者さんが嫌がられるのですよ」
もちろん、栄吉に個室料を負担する余裕はなかった。
途方に暮れる栄吉の耳に、
「お見舞いだけなら構わないのですよ」
ひどく明るい師長の声が突き刺さった。
終