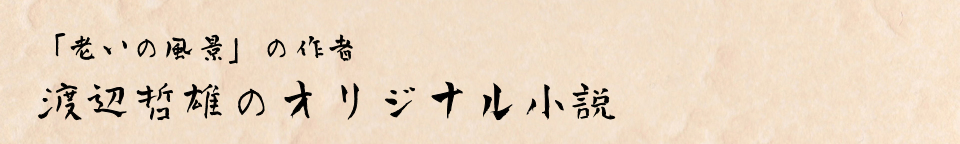- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師2
暴力教師2
迂闊だった…と尾崎俊介は、四方正人の家に車を走らせながら思った。正人の一年生当時の担任で、この春、他の中学校に転任した石川朝子の話によると、正人は私語こそ一言も発することはなかったが、授業中の本読みは聞き取れないくらいの声でできていた。
「正人くんのような緘黙児にとっては、会話よりもむしろ言葉に感情をこめる必要のない本読みの方が抵抗が少ないのでしょうね」
石川朝子はそう解説して、正人を新しい担任に引き継いだ。それが二年生に進級してクラス編成が変わったとたんにできなくなった。環境の変化に馴染めないせいだろうと俊介は単純に考えていたが、そこにいじめが介在しているとしたら許せない。
そういえば思い当たるふしがある。
正人は給食の時間に食事に手をつけないでにやにやしていることがあるが、ひょっとするとあれは、誰かに箸を隠されて困っている姿ではなかったのか。いつだったか正人が例によってボタンをいじりながら裸足で町を歩いていたという報告を受けたことがあるが、それは誰かに靴を隠された結果ではなかったのか。正人は変わり者だという先入観が、正人に対する正しい理解を阻んでいた。かなり奇異な行動が正人にあったとしても、見る者の目には正人が奇異な人間であることを証明する材料としてしか映らなかった。
しかし、昼間のグラビアの一件は違っていた。正人のうろたえぶりから考えても、あれは間違いなく誰かの仕組んだ悪質ないたずらに違いない。
俊介は背筋が寒くなった。
これまでどのテストの結果を見ても、正人の成績は平均より上に位置している。そのくせ少しでも心の内面を表現しなければならない作文を求めたりすると、正人はきまって白紙で提出した。通常の理解力と通常の感受性を持っていながら、その表出を拒否し、どんなに哀しくても、どんなに悔しくても、はにかんだように笑いながらボタンをいじることしかできないのだとしたら…正人の心の中はまるで真冬の荒野のように寒々とした風景ではないか。
俊介は正人を理解しようと思った。
それにはまず、正人の家庭を尋ねてみることだ。問題児であることが判っていながら、これまで家庭訪問をしなかった自分の怠慢を俊介は恥じていた。
町外れに川が流れている。
上流に養豚場や製紙工場があるために、排水で川はにごり、異臭を放っている。通称『よどみ川』と呼ばれているその川を背にして、あけぼの荘という老朽アパートは建っていた。
(ここか…)
俊介は車を下りた。すると、いち早く人間の匂いを嗅ぎつけて数匹の薮蚊が俊介の顔に群がった。住人の生活に余裕のないことを示すように、建物の周囲に生い茂った雑草の中から虫の音が沸き上がっている。二〇七号室という部屋の番号から見当をつけて、俊介は二階に続く鉄の階段を上がった。足を運ぶ度に無神経な大きさで響き渡る鉄板の音を気にしながら急な階段を上りきった時、
「!」
俊介は思わず小さな叫び声を上げそうになった。
通路に黒いかたまりがのっそりと立っている。それが学生服姿の四方正人であることは、月明かりの中ですぐに判別ができた。
「お母さんは部屋か?先生、話があるんだ、お母さんに」
俊介がドアをノックしようとすると、正人が慌てて俊介の背広の裾を引っ張った。
「?」
振り向くと正人は困ったような表情でボタンをいじっている。
「留守じゃないんだろ?」
俊介は構わずドアを叩いた。
「こんばんは、大手門中学の尾崎です。お留守ですか?」
ノブを回すと鍵がかかっていた。
「正人お前、締め出されたのか?」
俊介がそう言おうとした時、内側から鍵を外す気配がしてドアが開いた。
「あの、済みません、お客様だったものですから…」
四方正人の母親は、懸命に何かをとりつくろおうとしている。その横をすり抜けるようにして、ジャンパー姿の中年の男が慌てて靴を履き、そそくさと出て行った。
戸惑う俊介の後ろで、正人は狂ったようにボタンをいじっている。