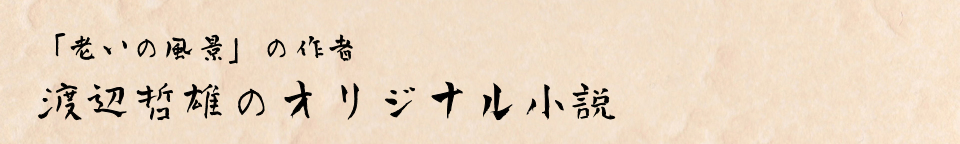- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師5
暴力教師5
塚本浩一の妹の千波が突然腹痛を訴えて泣き出したのは、夜の九時を十分ほど過ぎた頃だった。初めのうちは、
「ばか、まだ小学二年生のくせに、アイスクリームを食べてからジュース二缶も飲むからだぞ」
と軽くあしらってテレビを見ていた浩一だったが、やがて千波の額にうっすらと汗がにじみ、えびのように体を曲げて、うっ、うっ、と断続的に苦しみ始めると、浩一は急に胸が締め付けられるような不安に襲われた。
「千波、お前大丈夫か、ん?我慢できないのか?」
千波は返事をしないで目尻に涙を浮かべている。
「待ってろ、千波!俺、母ちゃん呼んで来る」
浩一はアパートの階段を転げ落ちるように駆け下りて自転車に飛び乗った。
一週間ほど前の夜、父親の清一が母親の芳江に、お前また店を変わるのかと尋ねた時、芳江は尖らせた唇から酒臭い煙を空中の一点に向かって勢い良く吹きつけながら、
「スナックよりキャバレーの方が実入りがいいのよ。それに今の店のマスター、色々と細かくていけ好かないしね」
とうそぶいていた。
(確か駅前のルージュとか言ってたな)
浩一はペタルを漕いだ。
今まで知識としてしか知らなかった胸騒ぎとか不吉な予感とかいう言葉が実感となって自転車の後ろから追いかけて来る。人通りが少なければ歩道を走り、車が空いていれば車道を走りして、信号を抜ける度に町はにぎやかになり、駅のガードをくぐり抜けると、突然目の前に、浩一の住んでいる地域とは別世界のネオンの巷が広がった。千鳥足の酔っ払いたちの間を縫うようにハンドルを操る浩一の耳に、
「ばかやろう!気をつけろ!」
という怒鳴り声が何度か突き刺さった。
目的の店を捜し当てるのにはもう少し苦労するのかと思っていたら、駅裏の一番大きな通りの真ん中に、ひときわ華やかなネオンに飾られてキャバレー『ルージュ』はあった。店の前で黒いズボンに黒いベスト姿の若い男が、盛んに手を叩きながら客を引いている。めまぐるしく点滅するたくさんの裸電球でアーチ型に縁取られた入口が、秘密の国に通じるトンネルのようにポッカリと暗い穴をさらしている。
浩一は自転車を飛び降りると、ひるむ心を振り切ってトンネルの中に駆け込んだ。すぐ後ろで、
「おい、こら!」
という客引きの慌てた声と自転車の倒れる音が聞こえたような気がしたが、そんな記憶は店の中に響き渡るけたたましいロック音楽にあっけなくかき消された。レジの前を通り過ぎる浩一の姿は、支払いを済ませる数人の客の陰になって職員からは見えなかった。ピンクのライトに照らし出されたステージの上で、三人のヌードダンサーが爬虫類のように腰をくねらせて踊っている。ひと筋の強烈な光が、回転するミラーボールに反射して、部屋中に無数の水玉模様を散らしている。明るい方向にばかり向いていた視線をフロアーに転じると、小さなガラステーブルを真っ赤なソファーでコの字型に囲んだたくさんのボックスに人がうごめいていた。サラリーマン風の男たちにしなだれかかって、肌の透けるネグリジェのようなコスチュームを身につけた女たちが、ある者はつまみを食べさせ、ある者は煙草に火をつけ、ある者は胸を触らせて笑っている。
暗闇に慣れた浩一の目がボックスからボックスへと移って行き、やがてある一点を見つめたまま動かなくなった。周囲と比較すると明らかに年をとっている太り気味の女が、客の膝にまたがり、口移しに何かを食べさせている。
その中の一人が芳江だった。
(母ちゃん!)
浩一は全身がカッと熱くなるのが判った。
その浩一の腕を、追いかけて来た客引きの若い男が力任せに引っ張った。
それが、やり場のない浩一の怒りの格好のはけ口になった。
「うわ!」
男は、浩一の頭突きをまともに顔面に受けて、その場にしりもちをついた。
浩一は外へ飛び出した。
ペタルを踏む度に千波の苦しむ顔と、つまみをくわえた母親の顔とが交互に浮かんで消えた。
「畜生、汚え!」
「畜生、汚え!」
何度も何度も吐き捨てるようにつぶやきながら、ネオンの街を全速力で走りぬけた浩一は、今度は駅前のパチンコ店に向かって懸命に自転車を漕いだ。汗で赤いTシャツがべっとりと貼りつき、足は、ふくらはぎの辺りの筋肉が今にも痙攣を起こしそうに硬直している。乾ききった粘膜の痛みを喉の奥に感じながら、浩一はなぜかもっと自分の肉体を痛めつけたい衝動にかられていた。
父親の清一は、三軒並んだパチンコ店の中のマンモスという店で、両方の耳にパチンコ玉で栓をし、煙草をくわえたまま、七が三つそろったパチンコ台を睨みつけていた。
閉店まで時間をつぶし、行きつけの居酒屋でビールを一本飲んでから芳江を迎えに行くのが日課になっている。
「父ちゃん!」
という声に振り向くと、浩一が肩で息をしながら立っていた。
「千波が腹を痛がるんだよ!」
浩一は、清一の耳元に顔を近づけて、店に流れている軍艦マーチに負けないくらい大声を張り上げた。清一は、は?という顔をして耳の栓を取ったが、すぐにまた視線をパチンコ台に戻すと、
「救急箱に薬があるだろうが!適当に服ませておけ、ばかやろう!」
次々と落ちてくる出玉を大きなプラスチックの容器に勢い良く移しながらそう言った。
でも…と言いかけた浩一に、そこから先を言わせない無関心さが清一の横顔にあふれている。
「くそったれ!」
浩一は足元に積んである出玉の入った箱の山を思いっきり蹴飛ばした。パチンコ台から手を離すわけには行かない清一の目の前で、玉は通路の床を音を立てて転がって行く。
「浩一!」
と怒鳴る父親の声に振り向きもせず、浩一は再び自転車にまたがってアパートに向かった。
何もかもがうす汚く見えた。
何だかひどく独りぽっちだった。
その分、部屋で苦しんでいるはずの千波が愛しく思えた。
アパートの灯が見えた。浩一はほとんど立ち上がった姿勢でペタルを漕いでいた。階段を一つ飛びに駆け上がって部屋のドアを開け、
「千波!」
と叫んだ浩一は、自分の目を疑った。
苦しんでいるはずの千波が、ポテトチップスを食べながらテレビを見て笑っている。
「ウンチしたら治っちゃった」
あどけない千波の顔が許せなかった。
「ばか!」
浩一はポテトチップスの袋を取り上げて床に投げ捨てた。
千波は火がついたように泣き出した。
(泣きたいのは俺の方だよ…)
浩一は散らばったポテトチップスを見つめたままこぶしを握り締めていた。