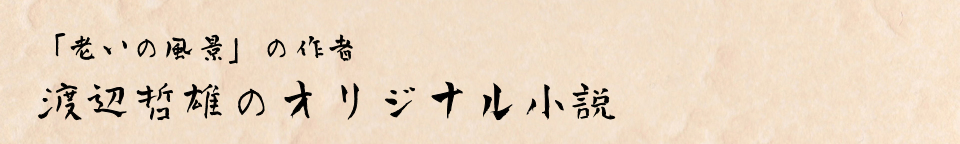- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師8
暴力教師8
「それで、その後どうなったの?」
夜も九時を過ぎてから帰宅した俊介の世話をしながら、妻の由紀子は眉をひそめて話の続きを催促した。
二人は結婚して十七年になる。
当時、養護教員として学校の保健室に勤めていた由紀子は、頭痛や腹痛を訴えて教室から逃げ込んでくる不登校予備軍の生徒たちを何とか励まそうと躍起になりながら、肝心の担任教師たちが案外冷淡であることに少なからず失望を感じていた。そんな中で比較的熱心に保健室を尋ねては子供たちの話し相手になっていたのが尾崎俊介だった。
チックといって、ストレスのために首の筋肉が頻繁に痙攣するようになった男子生徒を一緒に指導する中で、二人は急速に親しくなった。
結婚して二年目に長女の絵美が生まれたのを機に、由紀子は仕事を辞めた。
その絵美が、今話題になっている四方正人や塚本浩一と同じ一五才に成長して俊介の隣でコーヒーを飲んでいる。
他人事ではなかった。
俊介の学校で起きていることが絵美の学校で起きないとも限らない。
「結局四方くんが犯人じゃなかったんでしょ?」
「それがよく判らないんだ…あ、お茶漬けもう一杯もらおうか」
「あなた食べすぎよ、果物にしたら?」
「ん?じゃそうするか」
「私も」
「絵美はさっき食べたばかりでしょう?果物だって太るんだから」
「だいたい、ちゃんとしゃべらないからいけないんだ」
「あら、しゃべれば太らないの?」
「いや正人のことだよ」
「まあ、それじゃあなた、四方くんはそんな時でも黙ったままなの?」
「例によってボタンをちぎってしまっただけだ」
「そんなのはお父さん、塚本という子が室伏という子に財布を盗ませて、四方君のカバンに入れておいたのに決まっているじゃない。解らないの?」
台所で母親がむいたリンゴを食卓に運びながら、絵美が腹立たしそうに言った。
「もちろんお父さんだってそうは思うんだが、何しろ当の正人が一言も弁解しないんじゃどうしようもない」
「で、あなたはどうしたの?」
「ま、一応この件は任せてもらうということで切り上げて、放課後正人を呼んで色々と聞いてみたが何も言わない。まさか証拠もないのに室伏や塚本を問い詰めるわけにも行かないしな。とりあえず帰りに伊藤明代の家に寄ってわけを話し、明日からは現金はこちらで預かる事にした」
「お父さん?」
絵美はリンゴをかじりながら、
「おカネのこと解決しようなんて思わない方がいいわよ」
中学生の顔で俊介を見た。
「?」
「あのね、クラスのみんなはね、きっと解ってると思うの、誰が盗ったのか。それよりも私、四方くんに伝えることの方が大切だと思うわ、誰も四方くんのことを疑っていないって。ひょっとしたらお父さん、一番の被害者の四方くんを、まるで刑事みたいに根掘り葉掘り追求したんじゃないでしょうね?盗ってないんならないってはっきり言ったらどうだとかって机叩いたりして」
「ばか、俺が机を叩いたりするもんか」
「でもあれこれ聞いたんでしょ?アリバイとか…」
「おいおいアリバイだなんて、お父さんはただ念のために」
「その念のためってのが恐いのよね。人って案外そういうことで傷つくんだから。四方くん大丈夫かしら。私心配だわ。今頃思いつめて…」
「絵美、なんてこと言うの!面白がってるんじゃないわよ。それよりあなた、宿題まだ済んでないんでしょ?ほらほら食べてばかりいないで早くやりなさいよ」
「はあい」
由紀子は、うるさい絵美をそう言って追い払うと、
「あらあなた、リンゴおいしくない?」
口元まで運んだリンゴを食べるのを忘れてぼんやりしている俊介に尋ねた。
「あなた?」
「ん?ああ」
俊介は絵美の言ったことが気になっていた。
確かにあの場では伊藤明代が被害者の立場になってはいたが、財布が無事見つかっている以上、明代はその時点でもう被害者ではなくなった。本当の被害者は犯人に仕立て上げられた四方正人だった。その正人を、たとえ事情を聴くためとはいえ、個別に職員室に呼ぶという形で犯人扱いした。
「正人が盗ったんじゃないだろ?」
という聴き方をしたつもりだったが、聴かれる正人にしてみれば、どんな聴き方をされようと同じ事だったに違いない。しかし他にどんな方法があったというのだ。俊介はそう思う一方で、今頃思いつめて…という絵美の言葉が頭の芯に棘のように突き刺さっていた。
塚本浩一の挑戦的な視線を思い出した。
俊介は食卓を立って壁のハンガーにかけてある上着のポケットから黒い手帳を取り出し、四方正人の家の電話番号を調べると、玄関先の受話器を取り上げた。
「もしもし四方正人くんのお宅ですか?担任の尾崎ですが」
やがて俊介の顔色が変わった。
正人はまだ帰っていない。
「はい、はい、私もすぐそちらに伺いますから」
俊介は上着をはおりながら慌てて出て行った。
今年厄年を迎えた夫の後ろ姿は、由紀子には心なしか少し疲れているように見えた。
時計はとうに十時を過ぎている。