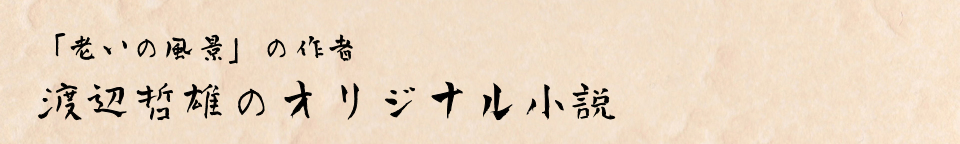- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師9
暴力教師9
「まあ、学校でそんなことがあったんですか…」
澱み川のほとりのあけぼの荘の二〇七号室で、四方妙子と日比野義和は顔をこわばらせて俊介を見た。
「もう一度心当たりを探してみよう。学校で嫌な思いをしたのならなおさらだ」
日比野義和は車のキーを持って立ち上がった。
「今までこういうことは?」
俊介が尋ねると、
「いえ、一度も…。あの子は学校が終わるとまっすぐ家に帰る子ですから」
妙子の声は震えている。
「僕も一緒に探しましょう」
三人は鉄の階段を早足に下りた。
「うるさいぞ!何時だと思ってるんだ、ばかやろう!」
どこかの窓が開いて誰かが怒鳴ったが、その頃には三人は既に車に乗り込んでいる。
「僕は通学路に沿って学校付近を捜してみます。お二人はそれ以外の心当たりを捜して下さい。十二時に一度アパートに集まりましょう」
「判りました。お願いします」
二台の車のヘッドライトがあけぼの荘の前で左右に分かれて走り去った。
取り返しのつかないことが起きようとしているのではないかという不安がハンドルを握る俊介の胸を締め付けていた。正人の通学コースをアパートから学校に向かってゆっくりたどりながら、俊介は暗闇に黒い学生服を捜す事の難しさを思い知った。人通りの絶えた深夜の町並みは、しかし、こうして走ってみると中学生が長時間過ごせるような場所は見当たらなかった。
もしも自分が正人だったらと俊介は考えてみた。
嫌な出来事のあった学校にはもちろん一分だって長く居たくない。かといってまっすぐ家に帰り、何も知らない母親と何事もなかったようにいつもの生活に戻るには気持の切り替えが難しい。たとえばこれが映画であれば、澱み川の堤防などは傷ついた中学生が膝を抱えて座っている場所としては恰好の舞台になるのだろうが、そこには両岸にずらりと軒を連ねた人家からの人目がある。恐らく正人は人目を避けたいに違いない。
自殺?
不吉な二文字が、それを思い浮かべるだけで不思議な現実感を伴って頭の中で膨れ上がり、
(まさかそんな事は…)
俊介は小さく首を振った。
冷静にならなくてはいけない。黄昏から深夜にかけて中学生が一人で過ごせる場所など決して多くはないはずだ。しかもそれは学校からそれほど遠くなく、人目につかない所でなければならない。
俊介は手のひらがじっとりと汗ばんでくるのを感じながら、通学路沿いの広場や神社に的をしぼって車を走らせた。