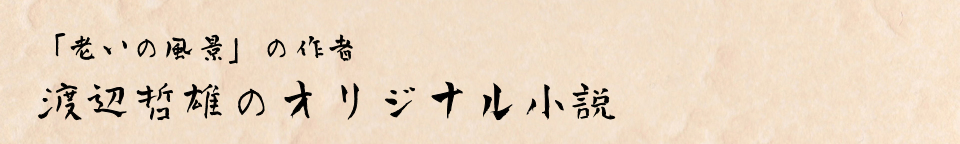- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師10
暴力教師10
一方、妙子に指示された場所に車を入らせた日比野義和は、
「妙ちゃん、ここが?」
サイドブレーキを引いて運転席から妙子の横顔を見た。
それには答えないで急いで車を下りた妙子を日比野義和は小走りに追いかけた。目の前に明るい水銀灯に照らされて芝生の緑が広がっている。
「正人に楽しい思い出があるとすれば、この公園しかないわ」
妙子は涙ぐんでいた。
正人が緘黙を指摘されて児童相談所に通い始めた頃、月に一回は妙子も一緒に石田直行のカウンセリングを受けていた。石田は特別に何かをしてくれるわけではなかったが、話をしていると何だかとても穏やかな気分になって、妙子も正人もお互いの気持が寄り添い合うのを感じていた。カウンセリングが午前中に組まれた日は、おにぎりを持って行って公園で食べた。ある日、小高くなった芝生の上でお茶を飲もうとして、膝元に置いた正人の食べかけのおにぎりが信じられないくらい遠くまで転がって行くのを見て、二人は顔を見合わせて大笑いをしたことがあった。思い出の糸をどんなにたぐってみても、この程度の些細なこと以外に正人の楽しい過去を見つけることのできない現実が哀しかった。
「?」
日比野が立ち止まった。
かすかではあるが、どこかで金属のきしむ音がした。
「ブランコだわ!」
妙子が日比野の腕をつかんだ。
「行こう」
日比野が妙子の手を引いて駆け出した。
「こっちよ!」
いつの間にか公園の様子の分かっている妙子の方が先になった。
正人は一人うなだれてブランコに座っていた。
「正人!」
二つの影が駆け寄った…とその時、別の方向から長身の影が一つ加わった。
正人が驚いたように立ち上がった。
妙子が息子の肩を抱くよりも早く、日比野義和の平手が正人の頬で激しい音をたてた。
「正人くん、あまったれるな!学校でどんなつらい目にあったか知らないが、こういう形でお母さんに心配をかける権利はないぞ!」
正人はうめくような声を出して泣いた。
その右手はボタンをいじってはいなかった。
いや、力いっぱい妙子に抱きしめられて、正人の両手は完全に自由を失っていた。
俊介は正人を担任してこの時初めて彼の声を聞いた。