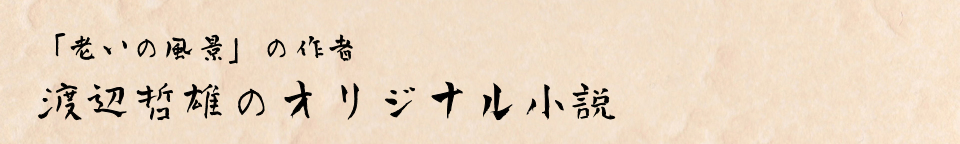- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師11
暴力教師11
幡豆と書いて『はず』と読ませる炉端焼きの店のカウンターの隅で、尾崎俊介はチッと舌打ちして腕時計を見た。
午後七時半…。
約束の時間を三十分も過ぎている。
「おやじさん、ビールもう一本」
「はいカウンターさん、おビール追加!」
俊介の目の前に、長い櫂(かい)の先に乗せられたビールがぬうっと差し出された時、
「へ、いらっしゃい!」
出入り口の引き戸が開いて、背広姿の二人の若者が入って来た。
(なんだ、俊彦じゃないのか…)
がっかりしてビールを注ぐ俊介の後ろで、若者二人は戸惑ったように立っている。
「ん?」
見ると五つほどあるテーブルは一杯で、カウンターの席が俊介をはさんで二つだけ空いている。とはいっても俊介の右隣の椅子の上には黒いビジネスバッグが置いてあるために、若者は俊介に席を一つ移動してくれるよう申し出ていいものかどうか迷っているらしい。
「あの、この席はどなたか…」
と若者の一人が言いかけた時、再び店の主人の威勢のいい声が飛んで、
「済まん済まん、五分ばかり遅刻だな」
ようやく現れた小島俊彦が俊介の左隣に腰掛けた。
お前、約束は七時だぞと責める代わりに俊介は、
「相変わらずだな」
バッグを自分の足元に移しながら思わず笑ってしまった。
俊彦は昔からこういうところが少しも変わらない。悪気はないのだが、親しい間柄で深刻に謝ったり謝られたりするのが嫌いで、こういう場合はいつだって遅れて来た方に約束の時間を合わせてしまう。だから反対に自分の方が待たされた場合でも、おい、五分ほど遅刻だぞと先手を打つのが俊彦のやり方だった。
「で、話しって何だ、俊彦。お前の塾に来いって話ならお断りだぞ」
俊介が言うと、
「お前こそ相変わらずせっかちだな。とりあえず乾杯をしてからだ」
俊彦は使っていたおしぼりをコップに持ち替えた。
「何年ぶりだ?お前とこうして飲むの」
「何言ってるんだ、お前の送別会以来だろうが」
「ということは三年…か」
「三年だ」
「早いもんだ」
俊彦は遠い目をして空になった俊介のコップにビールを注いだ。二人ともアルコールは強い。
「そろそろ熱燗にしよう」
と俊彦が言い出した頃には、二人の前にはビール瓶が五、六本並んでいる。しかし、
「ところで俊介」
と真剣な顔をしたつもりの俊彦の目は、さすがに焦点が定まらなくなっていた。
「困ってるんだ」
「何が」
「評判が良すぎるんだよ、小島ゼミナールの。クラスを一つ増やさなくてはならん」
「結構じゃないか、心配してたんだぞ、突然お前が教員辞めるって言い出した時は」
「教育は人だ、そうだろう?俊介」
「当たり前だ、酔ってるな、俊彦」
「ああ酔ってるぞ、酔ってるとも。俺はな、俊介、酒にも人生にも酔わなくてはいかんと思っている。教育を志した以上、自分をごまかしてはいかん。本当の教育はもう学校にはないぞ。いいか俊介、これからは塾だ、小島ゼミナールだ」
「おい、またその話しか、電話でさんざん聞いてるよ。で、困ってるってのは一体何だ」
「ん?俺は困ってなんかいないぞ?」
俊彦は手酌で飲み始めた。俊介はばかばかしくなってお銚子の酒をコップに移して一気に飲み干した。
「どうだ俊介、俺の塾で働かないか?ひとクラス二十人だ。それ以上は増やさん。緊張が薄れるし、第一目が行き届かなくなるからな」
「お断りだといっただろ?あ、おやじさん、お酒頼むよ」
「へい、カウンターさんお銚子追加!」
「どうしてだ俊介、落ちこぼれを出さないためには二十人が限度だぞ?学校の半分だ、理想的だろうが。週二日ずつ三クラス、つまり六十人がお前の生徒だ。月収は三十万、これは夜だけだ。昼間の講師の口はいくらでもある。うまくやれば月収五十万だ」
「カネの問題じゃない」
「もちろんだ俊介、カネの問題じゃない。しかしお前、具体的に転職するとなればカネも大切だろうが。家族の生活もあるし」
「俺は転職する気はないよ、俊彦」
「頑固なやつだなあ」
俊彦はあきれた顔をした。
「ばか、どっちが頑固なんだ」
俊介のろれつもそろそろ怪しくなって来た。
「まあ聞け。いいか俊介、教育は人だ。俺んとこの塾には今お前のような教師が必要なんだ。校則で生徒を縛り付け、勉強したいやつもしたくないやつも一つクラスに詰め込んで、無理やり相対評価で成績つけて、学校なんてお前、優越感と劣等感の製造工場だろうが…。非行と不登校といじめに振り回されているうちに、教師の方がだめになっちまう。俺はそんな学校に見切りをつけて塾を始めたんだ。勉強したい者だけが集まる小規模の集団はお前、教え甲斐があるぞ?考え直せ、俊介、俺と一緒に本来の教育に打ち込んでみろ」
酒の入った杯を持ったまま目の前で左右に揺らす俊彦に閉口して、
「判った判った、俊彦、考えてみるよ」
そう答えた俊介も、しっかりと目をこらさないと俊彦の顔が二重に見えてしまう。
(非行と不登校といじめに振り回されているうちに教師の方がだめになってしまう…か)
四方正人と塚本浩一の顔が浮かんで消えた。
確かに塾には今俊介を悩ませているような問題はないだろう…が、それこそ初めからそういう対象を切り捨てているだけのことではないだろうか。
「おやじさん、お勘定!」
俊介は立ち上がった。
もう一軒行こうと繰り返す俊彦に肩を貸して表に出た俊介は、ビジネスバッグを忘れている事に気がついて引き返した。戻ってくると俊彦はその場に座り込んで何やらぶつぶつとつぶやいている。
(こいつもきっと色々と矛盾を抱えてるんだ…)
俊介は流れてくるタクシーに手をあげた。