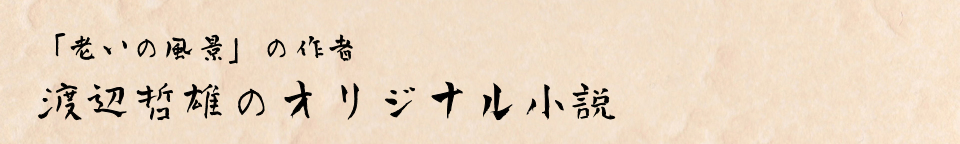- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師12
暴力教師12
俗に、年齢はまず歯に現れるというが、俊介に悪い歯は一本もない。その代わり、午後になっても胸のむかつきの治まらない二日酔いのしつこさに、俊介は自分の歳を感じていた。頭の中に鉛のようなアルコールのかたまりが残っていて、それを転がさないようにそっと首から上を扱わないと、内側から頭蓋骨を直接たたかれるような痛みが脊髄を走りぬける。五時限目が終わり、ようやく授業から開放された俊介が、職員室に戻ってひと息ついた時、
「先生、困りますなあ、ちゃんとご報告頂かないと」
生徒指導主任の佐藤昭夫が耳元でささやいた。
「え?何をです?」
俊介の声に周りの教師たちのいぶかしげな視線が集まった。
「いえ、ここではあれですから、ちょっと…」
佐藤は、刑事にした方が似合うような鋭い目をして辺りをうかがうと、情報を握っている側の人間に特有の傲慢な後ろ姿を見せて歩き出した。俊介はついて行かざるをえない。
佐藤は会議室の隅の机で俊介と向かい合うが早いか、
「クラスで起きた盗難事件は細大もらさずご報告頂かないと困るんですよ」
にわかに語気を荒くしてそう言った。
俊介の頭の中で、鉛の玉があちこちに転がった。
「え?ああ、伊藤明代の財布の件ですか。あれなら無事持ち主に戻ったことですし、大袈裟に扱わない方がと思ったものですから。でも先生はどうしてそれを?」
「財布が出てくればいいってもんじゃないでしょう、盗難事件は何も解決していない。それに盗んだのは先生、四方ではないですよ」
「え?」
「一年六組に吉村茂行ってのがいるでしょ?青白い顔をした、見るからに不健康な。そう、あいつは先生のところの塚本浩一の、まあ言うならば子分なんです。最近では塚本の真似をして学生服の下に真っ赤なTシャツを着て来たりしています。その吉村がいきがってうっかりしゃべっちまったんですよ、自分の仲間に。つまり、塚本が室伏に命令して伊藤明代の財布を盗ませ、それを四方のカバンに入れたということを。恐らく自分が先輩たちのそんな重大な秘密まで聞かされている立場だってことを自慢したかったんでしょう。それが回り回って私の耳に入った。そこで先生には悪いと思いましたが室伏に…」
「確かめたんですか!」
「生徒指導として放ってはおけないでしょう。こういうことはすぐさま手を打たないと必ずこじれます」
佐藤の言葉には有無を言わせない圧力があった。が、俊介としては知らない間に自分の部屋に土足で踏み込まれたような不快感を拭い去れない。
「で、室伏は?」
「認めましたよ、自分がやったことは。しかし塚本に命令されたことだけは頑として否定しています。やはり恐いんでしょう、塚本が。これから先は担任である先生の仕事ですよ」
「は?」
「まずクラス全員の前で室伏に謝らせるかどうかして、四方に対する誤解を解いてやる義務があるでしょう。もちろん黒幕が塚本ならそのこともはっきりさせるべきです。とりあえず解決の突破口は私が作ったわけですから、ひとつ先生、あとのことはうまくやって下さい。うやむやのまま終わらせていい問題ではありませんからね」
「はあ…」
俊介は二日酔いを忘れた。
確かに例の盗難事件は未解決のままになっている。しかしこういう形で真実が明らかになったことが果たして歓迎すべきことなのかどうか、今の俊介には判断がつかなかった。もちろん佐藤昭夫の言うとおり、うやむやに済ませてよい問題だとは思ってはいなかったが、実害が起きていないということと、この種のことは真実を追究して行く過程の中で、疑ったとか疑われたとかいう新しいトラブルを生み出しかねない問題であることが解決に向けての俊介の意欲を減退させていた。目撃者がない以上、到底真実を明らかにすることは不可能だろうという悲観的な見通しがあったことも否定できないし、何よりもクラスのだれ一人として四方正人を疑ってはいないという安心感が決定的な救いになっていた。だからこの問題は被害者である四方の気持の方を整理してやることで一応の決着をつけようと考えていた。
ところが思いがけない方向から真実が暴かれた。もう放置しておくわけにはいかなくなった。ここから先は先生の仕事ですよ…と佐藤に言われた時には、厄介な荷物を目の前に放り出されたような腹立たしさを感じたが、避けて通ろうとしていた自分の方が間違っていた。しかし、塚本浩一はまだ室伏篤久の影に隠れている。室伏だけを謝らせて格好をつけてみたところで本質は少しも変わらない。
考えてみれば室伏もまた被害者なのだ。
(直接浩一に当たるしかないな…)
俊介は覚悟した。