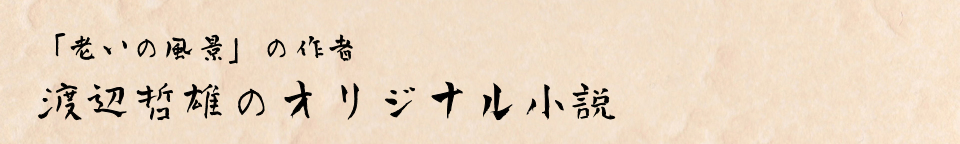- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師13
暴力教師13
その日のホームルームは、風邪で休んだ二人の生徒の他に、さらに二つの席が空いていた。
「塚本と室伏はどうしたんだ?」
教壇の上から尋ねる俊介の質問は虚しく宙を舞った。
「しようのないやつらだなあ…」
とつぶやきながら、俊介には二人の行動が容易に想像できた。佐藤指導主任のようなやり方で彼らを追いつめれば、こうなるのはむしろ当然ではないか。俊介がこの問題で頭を悩ませているのと同様に、彼らもまた自分たちを守るために必死に対策を講じる立場に立たされているのだ。
いずれにしても俊介は今日、塚本浩一の家を訪ねる予定にしている。万事はそれからだ。考えようによっては、ホームルームに彼らがいないということは、塚本と個人的に話をしてから担任としての態度を決めようとしている俊介としては、返って好都合だったと言えなくもない。
一方、塚本浩一と室伏篤久は俊介の想像どおり、町を南北に流れる鮎の瀬川の川原の石に腰を下ろして、重苦しいため息をついていた。
「俺、浩ちゃんのことは一言もしゃべってない。本当だぜ」
篤久はそう言って媚びるように浩一を見た。
浩一の目は川を流れて来る空き缶を追いかけている。
「きっと吉村だよ、浩ちゃん、あいつがどこかで口をすべらしたんだ」
浩一は立ち上がると、学生服を脱ぎ捨てて真っ赤なTシャツ姿になり、足元の小石を空き缶めがけて投げつけた。石は空き缶から随分と離れた場所で小さな水しぶきを上げた。
「畜生!」
浩一は意地になって次々と小石を投げたが、ことごとく外れて、空き缶ははるか視界のかなたへ流れ去った。
「どうする?浩ちゃん」
「うるせえ!少し黙ってろよ」
浩一は篤久に背を向けて座った。
「ごめん、でもきっと浩ちゃん、先公たちは」
「うるせえって言ったろ!」
「畜生!」
今度は篤久が立ち上がって石を投げた。
篤久が黙ると、川の音が急に大きくなって、二人は何だかとても大切な流れから自分たちだけがとり残されて行くような不安に包まれた。その不安を振り払うように、
「ようし!」
浩一が大声で言った。
「何かいい考えが浮かんだのかい?浩ちゃん」
「緘黙だよ篤久、緘黙」
「かんもく?」
「お前は先公に聞かれたら、俺に命令されたとか、むりやり盗まされたとか言っちまえばいい、正直によ。で俺は緘黙だ。一言もしゃべらねえ。にやにや笑ってボタンをいじってらあ。黙っていても四方なら良くて俺は許されねえとしたら、そんなのお前、差別だもんなあ」
「浩ちゃん、俺、浩ちゃんのことはしゃべらないぜ」
「しゃべってもしゃべらなくても同じことだよ、ばれてるんだから」
浩一は学生服の内ポケットをまさぐってタバコを取り出した。
そのタバコの先に篤久がライターを差し出した。火はその都度風邪に吹き消され、三度目でようやくついた。
浩一は四方の緘黙がどうしても許せなかった。四方のことを思い浮かべるだけで、みぞおちの辺りに手に負えない苛立ちのかたまりのようなものが膨れ上がって、無性に腹が立った。なぜだろう…と考えて見ても、理屈ではなかった。四方という人間が憎いのではない。四方を憎まなくてはならないほんのわずかな接点も、浩一と四方の間には存在しない。ただ、どんなに嫌な思いをしても、怒るわけでも、泣くわけでも、すねるわけでもなく、黙ってボタンをいじっていられる四方の神経が癇に障った。そんな四方が周りから大切にされたりすると、浩一の苛立ちは攻撃性を帯びた。怒れ!泣き叫べ!すねて不登校にでもなってみろ!そういう思いで浩一は四方の箸を隠し、靴を隠し、教科書の間にヌードグラビアをはさんだ。
その浩一が明日から緘黙になる。
先生は四方と同じ行動をとる自分をいったいどんなふうに扱うだろう…。
(こいつは案外面白い思いつきかも知れないぞ)
浩一は、見る見る日差しの傾いて行く秋空に向かって白い煙を吐き出した。