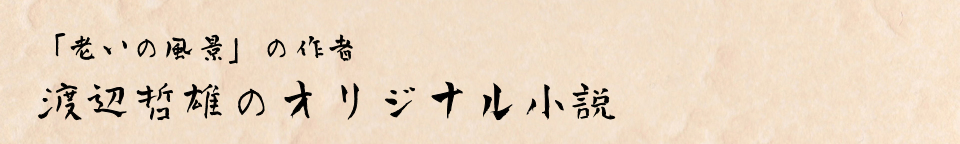- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師15
暴力教師15
台風が近づいている。それが前線を刺激して、久しぶりにまとまった雨を降らせている。こんな日は生徒たちの心も沈みがちになるのだろう。いつもならがやがやと騒がしいホームルームの時間も、全体に活気がなかった。それぞれの役割の生徒から連絡事項の伝達が終わり、例によって学級委員の司会でひどくおざなりな一日の反省が済むと、
「それでは先生のお話です」
伊藤明代が俊介を促した。
俊介は教壇に立つと、塚本浩一を見た。
浩一はいつものように襟元から赤いTシャツを覗かせて外を眺めている。激しい雨が校庭の土を叩きつけている。
「みんなちょっと注目してほしい」
俊介はそう言って、全員が静かになるのを待った。ホームルームの時間ごとに長々と教訓めいた話をするのを義務のように実行している教師がいる。しかし、この年齢の子供たちは総じてお説教が嫌いである。思春期が子供から大人への脱皮を図る時代である以上、彼らの心の中に大人に対する強烈な憧れと、それに匹敵する鋭い批判が渦巻いているのは当然である。大人の世界の醜さに過敏になっている彼らから見ると、その醜さを隠し、したり顔で説教をする時の大人ほど許せないものはないらしい。それが分かっているから、俊介はこれまでホームルームの時間にあまり構えた形で子供たちに話をすることをしないで来た。
その俊介が、注目を促して教壇の上で黙っている。
当然、子供たちはいつもとは違う空気を感じ取って、やがて全員の視線が俊介に集まった。
「先日伊藤明代の財布が紛失し、四方の持ち物から出てきたことはみんなも覚えていると思います。先生はその時、犯人捜しをするのはよそうと言いました。クラスメート同士が疑ったり疑われたりすることは避けたいと思いましたし、わざわざ犯人を暴いたりしなくても、それをしたあとの虚しさ後ろめたさを味わえば、きっとその愚かさに気づいてくれると信じていたからです。今から一人の生徒が、そのことについて勇気ある告白をします。先生はそれを単なる謝罪の表明であるとは思いません。反省をし、これからは二度と悪質ないじめをしないという意思表示であると受け止めたいと思います。いいですか?皆さんもこれを他人ごとだというふうに聞かないで、心の通う温かいクラス作りのスタートラインだと考えて欲しいのです」
俊介は生徒の側へ移って、教壇を浩一に譲った。
浩一はのっそりと立ち上がり、肩をそびやかして教壇に登った。
思いがけない展開に一瞬どよめいたクラスは、間もなく、つばを飲む音が聞こえるくらい静まり返った…が、思いがけない展開は実はこれからだった。
浩一はしゃべらない。
貝のように口を閉ざして教壇に立ったまま、学生服の上から三番目の金ボタンをいじっている。
「どうした浩一、なぜ黙ってる!」
と言おうとして、俊介は浩一の意図に気がついた。
浩一は明らかに四方正人の真似をしている。
四方は?と見ると、彼もまたいち早く浩一の意図に気づいたのに違いない。表情を硬くして、震える手で浩一と同じようにボタンをいじり始めた。
「お、緘黙が二人になったぞ!」
例によって、ひょうきん者の沢口進がはやし立て、それを皮切りに教壇の雰囲気は一変した。
「塚本くん、黙っているなんて卑怯よ!」
「そうよ、きちんと謝りなさいよ。男らしくないわ!」
「黙っているのが卑怯なら、四方だって同じだぞ」
「浩一だって、ひねくれ病という重い重い病気にかかってるのかも知れないぜ」
俊介は、頭の芯に焼け火箸を押し付けられたような憤りに耐えていた。
なんと言う巧妙で残酷な挑戦なのだろう。
塚本の沈黙を非難すれば、それはそのまま四方に対する非難になると同時に、これまで四方の緘黙を許して来た教師の側の矛盾を露呈させることになる。しかもこれは、四方に対する最も効果的ないじめにもなっているのだ。
「どうだ、悔しかったらおれをしゃべらせて見ろ!」
浩一はそう言いたげに、俊介に向かって不遜な微笑みを見せた。
その瞬間、俊介の思考が停止して感情だけが燃え上がった。
気がつくと教壇に向かって歩いていた。
生徒たちが総立ちになった時、俊介の右手が塚本の左頬で激しい音を立てた。
「浩一!」
俊介は大声を出して浩一のむなぐらをつかんだ。
「先生、やめて!」
という聞き覚えのない男子生徒の声が、静まり返った教室の空気を引き裂いた。
「先生、やめて!」
「先生、やめて!」
俊介も生徒たちもそして塚本浩一も、少し甲高いその声の主を見た。
緊張が頂点に達しているのだろう。四方正人は肩を震わせて叫んでいた。
俊介は振り上げたこぶしを下ろし、浩一を解放した。
開放された浩一は、正人の声に終われるように教室を飛び出した。
雨は止む気配なく降り続いている。