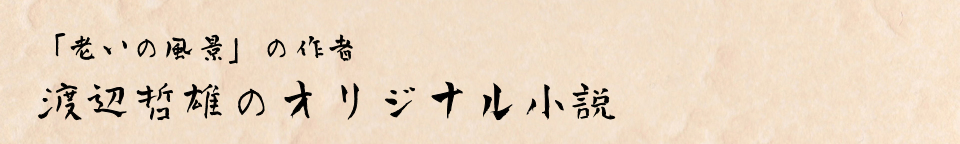- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師18
暴力教師18
今年一杯で定年を迎える若林洋一郎校長は、自宅の玄関先で、俊介の到着をやきもきしながら待ち構えていた。
タクシーが着くが早いか、自ら傘をさして俊介を迎えに出た若林校長は、
「いやあ尾崎先生、お待ちしていましたよ。先方はえらい剣幕です。ヤクザですな、まるで。ま、どうぞ。どうぞお上がりください」
言葉遣いは丁寧だが、ひどく狼狽した声で、俊介を和風の応接室に案内した。
「それにしても困ったことになりましたねえ、先生。なにしろ相手が悪すぎますよ、相手が。いえね、私もついさっき電話で話しただけですが、それだけであなた、先方の人間性は十分すぎるくらい判りましたよ。塚本の父親ってのは先生、ありゃまともじゃないですね、少なくとも理屈の通る相手じゃない」
「はあ」
「私のことも、あれですよ、いきなりてめえ呼ばわりです。てめえが校長か、責任を取れ責任を・・・と、こうですからね」
「申し訳ありません」
「先生に謝ってもらっても仕方がないですが、これはひとすじなわでは行かない相手だと覚悟した方がいい。すぐに謝罪に来いというのをあれこれと理由をつけて、九時三十分まで延ばしたのは、その前に先生から事情を聞かなければと思ったからです」
「謝罪なら私が行きますよ、校長先生。私が塚本に手を上げたのですから。それに平手であの程度叩いたくらいで全治二週間というのも腑に落ちません。浩一に会って、その点も確かめたいですしね」
「それはよした方がいい。先生はそういうところがまだお若い…というか、穏やかじゃありません。当事者同士が顔を会わせたらあなた、お互いに興奮してまとまるものもまとまらなくなるでしょう?相手は診断書を持っているんですよ、診断書を。いいですか?私がいつも機会あるごとに申し上げているように、教育の現場ではいかなる理由があろうとも手を上げた教師が負けなのです。保護者もマスコミも教育委員会も、暴力だけは許しません。言葉は適切じゃないかも知れませんが、これからの教育は内申書を盾にねちねちとやるしかないのですよ。悪いようにはしませんから、ここはひとつ私にお任せください」
「任せるって校長先生、先生はいったいどうなさるおつもりですか?」
「どうするもこうするも、謝罪の一手しかないでしょう。全治二週間の診断書を持って、出るところへ出られたら先生、傷害罪が成立するんですよ、傷害罪が。もちろん私は校長としての監督責任を問われますし、先生は暴力教師として処分されます。刑事罰の上に、軽くて訓戒、それが戒告以上の処分になれば、減俸だけではなくて先生の将来にだって差し支えます。その上、マスコミに騒がれでもしたらあなた、教師を続けることだって難しくなるでしょう」
「納得できません!」
俊介は正座した膝の上のこぶしを握りしめて、教室での一部始終を詳しく報告した。
暴力を肯定するつもりは毛頭ないが、世の中には暴力以上に許されない行為があると俊介は思っている。
裏切り、侮辱、差別、無視…。
対話をあきらめた関係の中で、力の強い者が弱い者を屈服させる目的で行われる『体罰』は別にして、怒りという感情の最終的な表現としての暴力には、少なくとも当事者の間に、そこに至る情緒的な了解があるのに対し、これらの行為は常に一方的で合理的理由に欠けている。暴力が爆発的で一過性であるのに対し、これらの行為は陰湿で継続的である。時として人は、暴力には耐えられるが、裏切りや侮辱には耐えられない。俊介の浩一に対する暴力は、確かに非難されるべき性質のものに違いないが、それによって浩一の行為が正当化されるものではないはずだ。若林校長の言うように、ひたすら謝罪に徹するとしたら、俊介と浩一との関係はゆがみ、教育の可能性は完全に消えてしまう。
俊介は覚悟した。
自分の取った行動で受けるべき裁きは、潔く受けよう。それにはまず浩一の両親に事の経緯を十分理解してもらうことが必要だ。
「校長先生がなんとおっしゃろうと、私は塚本の両親に会いますよ」
俊介は、黒縁の眼鏡の奥で瞬きを繰り返す若林洋一郎の目を真っすぐに見た。
壁の柱時計がゆっくりと九時を告げ始めた。
若林校長は車のキーを力なく持って立ち上がった。
「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」
俊介の言葉に振り返った若林校長は、思いがけないくらい老人の顔をしていた。
二人を乗せてコーポ北山に向かう車のワイパーが、降りしきる雨を忙しく払いのけている。