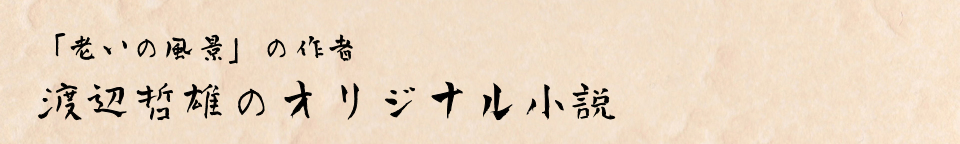- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師21
暴力教師21
地方紙とはいえ毎朝新聞は、五百万部を越える購読者数を誇り、系列のテレビ局と球団を持つ一大マスメディアである。
その毎朝新聞が各支社からレポートを募り、『学校における暴力』をテーマに秋の家庭欄の特集を組むという報せは、栗本小枝子にとっては久しぶりの朗報だった。念願の新聞記者として採用にはなったものの、配属されたのが職員の数がわずか五人という地方の支局だったために、ローカルな取材に明け暮れている現状を小枝子はあきたらなく感じていた。正義感に燃える二十二才の小枝子としては、地方版に載せるための交通事故の記事や、お祭りのレポートを書くために、新聞記者という、女性にとってはハードな職業を選んだつもりはない。本社で活躍している先輩たちのように、できれば社会性のあるテーマに取り組みたい。
「というわけだから栗本くん、ひとつ意欲的な記事を書いてくれたまえ」
と窓際族のデスクに言われるまでもなく、小枝子の胸は新聞記者としての血が騒ぎ始めていた。
『校則』とか『体罰』とかいう問題には興味があった。
小枝子の卒業した女子高は、何かにつけて規則の厳しい学校で、髪型はもちろんのこと、スカートのひだの数からソックスの色に至るまで細かく決められており、違反者には罰則があった。抜き打ちで行われる持ち物検査で廊下に正座させられるのも屈辱的だったが、前髪が眉毛にかかっているのを発見された時、通称『鬼金』と呼ばれていた金本という体育の教師に、人差し指で額をパチンとやられるのが耐えられなかった。朝それをやられると、昼を過ぎても額の真ん中に円いピンクの跡が残り、誰言うともなくその罰は『お釈迦様』と呼ばれて恐れられていた。
それが大学に入ったとたんに突然自由になった。どんな服装をしようと、何時まで夜遊びをしていようと、講義を欠席しようと、大学は何も言わなかった。その代わり、試験の日程や奨学金の手続きなどの大切な連絡事項も掲示板に貼り出されるだけで、うっかり見落としでもしたらそれっきりだった。
小枝子は今でも時々、アルバイトにかまけて試験日を忘れ、卒業に必要な単位を取れないで困ってしまう夢を見る。束縛だらけの高校生活から、何もかも自由な大学生活への環境の変化は、まるで金魚鉢からいきなり大海原に放り出されたような戸惑いと頼りなさがあった。学生は、手に入れた自由を十分活用して着実に見識を深めて行く一握りのグループと、道しるべの示されない開放感に負けて勉学を忘れてしまうグループとに二分された。それでも大学は大量の新入生を受け入れるために、レベルを下げた追試を実施してでもたいていの学生は卒業させた。
そのこと一つを取り上げてみても、わが国の教育は、大切な部分が歪んでいると小枝子は思っている。
自律した人間を育てることが教育の一つの大きな目標であるとすれば、生徒には常に、その年齢に相応しい自由と責任とが配慮して与えられるべきである。それが大学に入るまで極度に制限され、入ったとたんに一気に開放される。そして、自由を制限したり指示に従わせる手段として、教師の生徒に対する暴力が横行する。民主主義を象徴するものの一つがジャーナリストのペンだとすると、その対極にあるものが、権力をを持った者の弱者に対する暴力であるに違いない。
「デスク、私、全力を尽くします!」
小枝子は胸を張った。
この仕事は必然的に他の支局との競争になる。良い記事を書けば、本社勤務に抜擢されるチャンスだってつかめるかも知れないのだ。
「そうだ!」
小枝子は、書類や雑誌や様々なメモで埋ずまりそうな事務机の上の黄色い電話を取り上げた。