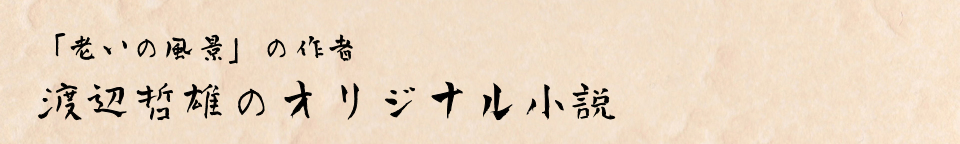- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師24
暴力教師24
栗本小枝子は、駅前の貸しビルの三階にある毎朝新聞支局のオフィスに一人だけ残って、レポートの構想を練っていた。
取材すべき人物のリストは出来上がっていた。暴行を加えた尾崎俊介という国語の教師と、暴行を受けた塚本浩一という中学二年生の生徒についてはもちろんであるが、この事件を特徴づけている人物として、脅迫を企てた塚本清一と、事件をカネで隠そうとした若林洋一郎校長の取材は欠かせない。それに加えて小枝子は、PTA会長の意見と教育委員会の見解を取材してレポートに奥行きを持たせるとともに、大手門中学における教師の対生徒暴力の統計資料か、それが手に入らなければ、生徒を対象にした暴力についてのアンケート調査でも実施して、教育現場の実態と関係者の意識を浮き彫りにしてみたい。
(まず塚本くんに会わなきゃ)
小枝子は窓際に立って夜の街を眺めた。
ひと口に取材といっても簡単ではない。
新聞記者には報道の自由はあっても、取材の権利が保障されているわけではない。取材される側には、取材を拒否する自由だってある。特に今回のような不祥事の場合には、喜んで取材に応じる関係者は初めからいないと覚悟してかからなければならない。とすると、やはりまず一番の被害者である塚本浩一に会い、それを突破口にして取材の輪を広げてゆくのが常套手段というべきであろう。
記事が新聞に載った日は、支局の電話は鳴りっぱなしだった。ということは、この事件はそれだけ世間の注目を引く事件だったということになる。無抵抗な生徒への一方的な教師の暴力。それを理由に逆に学校をゆすろうとする親のエゴイズム。カネを支払ってでも不祥事をもみ消そうとする学校の体質。これほど見事に現代社会のひずみを反映する出来事にタイミングよく出会えた幸運を、小枝子は感謝していた。
オフィスは駅の表通りに面している。
プラタナスの街路樹の続く夜の駅前通を、自動車のヘッドライトの白い光とテールランプの赤い光とが、それぞれ反対方向に流れて行く。そのうちの一台が流れから離れて、オフィスのある貸しビルの下に車を寄せた。
中から降り立った一人の背の高い青年が小枝子には見覚えがあった。先輩?と見るや、青年の姿はビルの通用門に吸い込まれ、やがて勢いよくオフィスのドアが開いた。
階段を一気に駆け上って来たのだろう。
「アパートに行ったら留守だったものだから、たぶんここだろうと思って」
速水憲太郎は肩で息をしている。
「小枝子、お前、今度のレポートを暴力に反対する立場だけでまとめるのはよせ。それが言いたくて来たんだ」
「どういうこと?」
「お前の書いた記事で、尾崎という熱心な教師が学校を辞めようとしている」
「それは責任を感じてるからでしょう」
「そうじゃない。ペンという凶器が彼から職場を奪おうとしてるんだ」
「凶器?」
「そうだ、凶器だ。ペンは真実の見えない記者が握ると凶器になる」
「私には真実が見えないって言うの?」
「学校は告訴を取り下げた」
「え?」
「塚本浩一を裁こうとすると、尾崎という先生の行為も不問に付すわけには行かなくなる。そこで両者は和解をし、事件は不起訴になった」
「納得できないわ。私は今度のレポートでそういういい加減な体質を…」
「まあ聞けよ、小枝子」
俊介は空いている席に腰を下ろし、小枝子は立ったまま不満そうに窓を見下ろしている。
「尾崎という先生は弁解がましいことは一切口にしないが、生徒たちの話を総合すると、彼が塚本浩一を叩いたのは平手でただの一回きりだ。しかし我々が事情聴取した時は、塚本浩一の顔はガーゼの周囲まで紫色に腫れ上がっていた。全治二週間と診断した医者に聴くと、例えばこぶしのようなもので殴らないとああはならないだろうという話だ。変だとは思わないか?」
小枝子は驚いて憲太郎を振り返った。
「その辺りを問い詰めたら、反対に先生を告訴するといきまいていた塚本清一はあっさりと和解に応じた」
「許せないわ!断じて許せない。私、この事件にまつわる薄汚い暴力という暴力を断固糾弾するわ!」
「よせ!」
憲太郎は立ち上がり、小枝子と向き合った。
「小枝子のような世間知らずのお嬢さんが薄っぺらい正義感だけでレポートすれば、真実 はゆがんでしまう」
「何ですって!」
「暴力は否定すべきことに違いないが、そこにいたる人の心まで描けなければ無責任な報道になる。ペンは暴力以上に人を傷つけることがあるんだ」
「そんなことは判っているわ!」
「判っちゃいないよ!現に小枝子の安易な記事で、一人の中堅教師が学校を辞めるところまで追い詰められている。塚本清一は暴力をネタにカネをゆすろうとするし、小枝子は暴力をネタに特ダネをものにしようとしたに過ぎない」
「先輩!」
「人間を本当に理解できないひよっこ記者は、お祭りの記事でも書いてりゃいいんだ」
「やめて!」
小枝子は短く叫んだ。
叫ぶと同時に小枝子の右手は、憲太郎の頬を力いっぱい叩いていた。
叩かれた憲太郎の射す様ような視線が、小枝子を激しい自己矛盾の中に突き落とした。
やがてわっと泣きながら突っ伏した小枝子は、完全に敗北した自分を認めざるをえなかった。