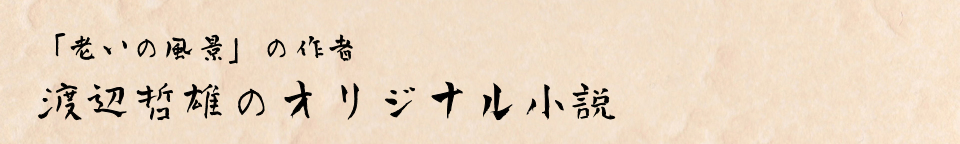- ホーム > オリジナル小説/目次 > 暴力教師25
暴力教師25
学校を辞めたいという俊介の話に、猛烈に反対したのは娘の絵美だった。
「お父さんは悪くないわ。辞めるのは負けることよ」
「絵美・・・」
由紀子は、俊介の思い通りにさせてやろうと考えていた。
「お父さんは学校を辞めるだけで、先生を辞めるわけじゃないのよ。塾の先生も悪くないじゃない。夜は少し遅くなるけど、転勤はないし、変な生徒もいない」
「そうじゃなくて、私、悔しいのよ。だって今度のことでは、お父さんのことよく知らない人ばかりが新聞を読んで騒いでいるんでしょ?夜中に無言電話までかけて来たりして・・・。そういういいかげんな人たちのせいで、お父さんが学校を辞めなきゃならないなんておかしいわよ。それにね、何だかんだ言いながら、塾には絶対にいない変な生徒たちに夢中になってしまうところがお父さんのいいところだし、お母さんだってそういうところが良くって結婚したんだって、いつか話してくれたじゃない」
「お、雨か?」
俊介が立ち上がって窓のカーテンを開けた。
秋の天気は変わりやすい。さっきまで月が出ていたと思ったら、いつの間にか細かい雨が庭の南天の葉を揺らしている。そう言えば確か小島敏彦も絵美と同じようなことを言っていた。学習を離れた生活場面での、教師を含めた個性のぶつかり合いが本当の教育なんだというようなことを言いながら、敏彦は盛んに俊介をうらやましがっていた。
さて、どうするか…。
俊介はまだ迷っていた。
辞表は学校の机の中に入っている。それを提出しさえすれば、一切のわずらわしさから開放されると思う一方で、絵美の言うように、そうすることは何だかひどく価値のない力に屈服することになるような虚しさを拭い去れなかった。
それにしても、このところ俊介は少し疲れていた。あれから何度か職員会議が開かれた。教育委員会に呼ばれて詳しく事情を聴かれもした。PTAの臨時の集会では、冒頭に陳謝させられた。どの席も根底では、理由を問わず教師の暴力は許されるべきではないという前提で一貫していた。俊介もそれを否定しない。ただ、それだけで教育にたずさわる資格のない人間のように判断される安易さが寂しかった。
「少し早いが、今日はもう寝るよ」
重い足取りで俊介が階段を上りかけると、チャイムが鳴った。
「?」
怪訝そうに眉をひそめて出て行った由紀子が玄関先で大声を上げた。
「あなた!塚本くんよ、塚本浩一くんが来たのよ!」
「浩一が?」
浩一は、ずぶ濡れになってドアの外で立っている。
「由紀子、タオルだ!」
俊介がそう言って振り向いた時には、由紀子はもうバスタオルを手に奥から駆けてくる。
「まあまあ、こんなに濡れて…。自転車で来たのね?」
由紀子が浩一の身体を拭こうとすると、
「大丈夫っすよ、おれ」
と無表情に答える浩一は、息を切らしている。
(何でこんなやつに親切にするのよ!)
柱にもたれて腕組みをした絵美が、そう言いたげににらみつけている。
「とにかく上がれ浩一、心配してたんだ」
と俊介が肩に手をかけるのを振り切って、
「先生!」
浩一は俊介の顔を見た。
唇が震えている。
その唇から真実が吐き出された。
「おれの怪我は先生のせいじゃない。おやじが殴ったんだ。でもおれ、おやじが恐くって恐くって、病院でも警察でも本当のことが言えなくて…。だから、だから先生、学校を辞めないでくれ。頼むから辞めないでくれよ」
浩一は深々と頭を下げた。
「判った、浩一、もういい、もういいぞ浩一」
俊介の声を聞くと、浩一は安心したように顔を上げた。
部屋に上がれというのを断って背を向ける浩一に、絵美が無言で傘を差し出した。
浩一は照れ臭そうに、絵美から受け取った女物の傘を差して自転車にまたがった。
「明日は学校に出て来いよ!待ってるぞ、待ってるぞ浩一!」
遠ざかる浩一の後ろ姿に俊介が声をかけた。
その俊介の手を、傘を差しかけた由紀子の手がしっかりと握りしめた。夫はもう学校を辞めないだろうという確信が、握りしめた手から伝わって来る。
「それにしても、どうして浩一くんはあなたが学校を辞めようとしていることを知っていたんでしょう?」
という由紀子の質問に、
「そういえばそうだな。まさか小島が浩一に会うわけもないだろうしな」
俊介も首をひねったが、実は、栗本小枝子という若い新聞記者が昼間コーポ北山を訪ねて浩一を説得したのだという事実を、その時の俊介は知る由もない。
「二人とも中に入ったら?」
絵美が明るく声をかけた。
「あなた、今夜は思いっきりビールを付き合うわよ」
由紀子がはしゃいで見せた。
「ようし!飲むか」
俊介が両手を挙げて晴れやかに伸びをした。
久しぶりに明るさを取り戻した尾崎家を包み込むように、秋の雨がやさしく降り続いている。
終