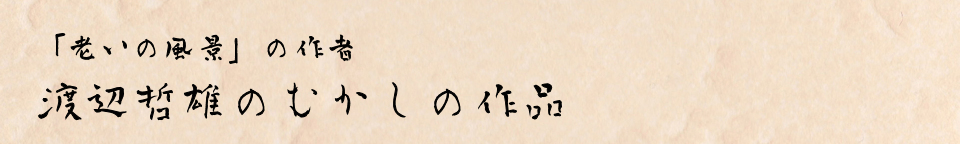聴海の運命
作成時期不明
聴海と名乗る占い師の家は、百足長屋という、城下でもとりわけ日当たりの悪い貧乏長屋の西外れにありました。いつの間にか長屋の片隅に住みついてほとんど姿を現さない聴海のことを、初めのうちは誰もが気味悪がっていましたが、この男が大小三十六枚の貝殻を使って人の運命を言い当てる世にも珍しい貝占いが、万に一つも外れたことがないという評判が立ってからというものは、一人またひとりと客の数が増え、この頃では順番待ちの客を当て込んで、百足長屋に茶店ができるほどの盛況ぶりです。
白木に黒々と「聴海運命鑑定所」と書かれた大きな看板の下がった入り口を一歩中に入ると、狭い板敷きの部屋のぐるりには黒い幕が張り巡らされ、真昼でも夜のような闇の中に、丸太ほどもあろうかと思われる四本の蝋燭の怪しい炎に囲まれて、山伏姿で座っている男こそ、占い師聴海その人でした。目の前に敷かれたムシロの上には縦横六列に並べられた貝殻が三十六枚。さらにその前で、床に額をこすりつけるようにひれ伏している若い娘は、かれこれ半日近く待たされて、ようやく順番の巡って来た今日七番目の占い客です。聴海は眉にかかる白髪の髪を振り乱しながら、手に持った巨大な数珠を一心不乱にこすり合わせてなにやら呪文を唱えては、えい!えい!という鋭い気合とともに貝殻を一枚一枚めくって行きます。すると、貝殻の裏側には不思議な文字や模様が描かれていて、聴海の占いはどうやらその文字や模様の現れ方の中に人の運命を見極めようとするもののようでした。
「あな不思議やな不思議やな。天は運を造り、地は運を運び、海は運を告げる。いざお聴きそうらえ海の声。貝が伝える海の声」
聴海が静かに目を開けて厳かにそう言うと、娘も真剣なまなざしで顔を上げました。
「聴海さま…。わたくしは、わたくしはあのかたと…」
声が震えています。聴海は再び目を閉じてしばらく沈黙していましたが、やがて苦いものでも噛み潰すように言いました。
「残念じゃが結ばれはせぬ」
「しかし…しかし聴海さま」
「よいか、人の運は不変であるぞ。誰がどのような努力をしようと決して変えられるものではない。人は己の運に忠実に生きてこそ幸せになれるのじゃ。どの道結ばれぬ運命であれば、傷つけ合わぬうちに、そなたの方から身を引くことが双方のためとは思わぬか」
聴海の声には逆らうことの出来ない自信と威厳がありました。娘は力なく首をうなだれてすぐには立ち上がることもできず、ただ熱い涙が頬を伝うばかりです。
そんな聴海のところへ城からの使いの者が訪ねて来たのは、ある夏の盛りのことでした。
* * * * *
突然殿さまに呼び出されることになった聴海はさすがに戸惑っていました。いったい何のために召し出されるのでしょう。もしも占いをしていることが原因で何かお咎めを受けるのであるとすれば、すぐさま引っ捕らえて牢につなげば済むことです。使いの者がそれをしないで、わざわざ三日後に城に上るよう申し渡して帰ったところを見ると、それほど悪い話とも思えません。では聴海がこれまで行った占いの中に、何か不都合があったとでも言うのでしょうか。いいえ、たとえそうであっても、殿さまからじきじきに呼び出されるのは不自然です。第一、聴海の占いは正確そのもので、感謝されこそすれ不都合なことなどあるはずがないではありませんか…とすると、残る理由はただひとつ。聴海は考えました。殿さまは聴海を城に呼んで、自分自身の運命を占わせるつもりに違いありません。だとしたらこれは聴海にとって喜ぶべきことと言わなければなりません。世はまさに戦国時代です。明日の行方さえ定かでない戦乱の世にあって、武士も百姓も町人も自分の運命に限りない不安を抱いています。そんな折り、聴海が城中で殿さまの運命を占ったという評判が伝われば、うわさは火のように広がって、やがて全国の大名小名から声がかかるのは必定です。そうなれば聴海はもう、これまでのように百姓町人ばかりを相手にするしがない町の占い師ではありません。カビ臭い百足長屋を引き払い、有力な大名に召し抱えられて、左うちわで暮らすことだって決して夢ではないのです。
「いよいよわしの運も上り坂に向かったようだわい」