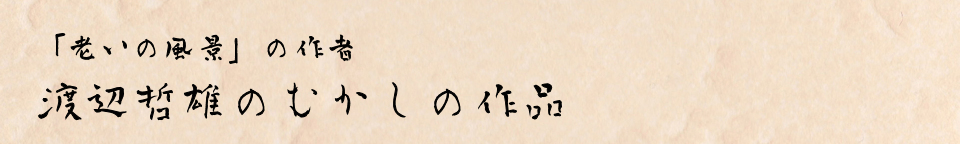おかるの恩返し
平成30年01月25日(木)掲載
その日、殿様はたいそうご機嫌が斜めでした。せっかく張り切って狩りにやって来たというのに、まだ一匹の獲物も射止めることができません。射止めるどころか、森には獲物の姿がないのです。これでは自慢の弓の腕前も披露することができません。
「ええい、もっと鐘を鳴らせ!獲物を追い出すのだ」
殿様は大声で家臣たちに命令しましたが、言い終わらぬうちに雨が降りだしました。まるで森の神様の怒りに触れたかのように雨は激しさを増し、とても狩りなど続けてはいられません。
「くそ、いまいましい!」
腹立ちまぎれに殿様が見上げた空に、カラスが一羽飛んでいます。殿様はきりきりと弓をしぼり上げました。
ひょう!という音を立てて矢が放たれました。
突然全身を襲った激しい痛みに、カラスは声を上げることもできず、土砂降りの雨の中を真っ逆さまに落ちて行きます。
「殿、お見事でござりまする」
「うむ、帰るぞ」
殿様はひらりと馬にまたがると、振り向きもしないでお城へ帰って行きました。
どれくらいの時が流れたのでしょう。
ずぶ濡れのカラスの体に巻き付けられた真っ白な包帯には、赤い血が滲んでいます。
「助かるべか、じいさま」
「大丈夫だべ、ばあさま」
耳元の声にようやく目を覚ましたカラスは、激しい痛みと共に自分がまだ生きていることに気が付きました。
「よしよし、怖がらなくてもいいだぞ」
じいさまが優しく言いました。
「ほれ、これでも食べて元気を出すだ」
ばあさまが食べ物を口に運んでくれました。
カラスはすっかり安心しましたが、優しくされればされるほどカラスには人間というものが分からなくなりました。何の罪もないカラスを突然弓矢で射落とすのも人間なら、傷ついたカラスを自分の家に連れ帰り、優しく介抱するのも人間なのです。きっと人間は森の仲間たちとは違って、置かれた立場や育ち方で、良い人間と悪い人間とに分かれてしまう、心の弱い動物なのでしょう。
親切なじいさまとばあさまの熱心な手当の甲斐あって、傷は少しずつ回復し、ひと月もするとすっかり元の元気な体に戻ったカラスは、じいさまとばあさまに別れを告げて、仲間たちの住む懐かしい森へ帰ることになりました。
ばあさまは泣いていました。じいさまの目にも涙が光っていました。子どものいないじいさまとばあさまは、いつの間にかカラスのことを我が子のように可愛がっていただけに、別れるのはとてもつらいことでした。
「おおい、気を付けて帰るだぞ!」
「もう二度と弓矢なんぞに当たるんでねえだぞ」
じいさまとばあさまは、力一杯手を振ります。カラスは嬉しそうに、カア!と一声鳴くと、くるりくるりと上空に輪を描いていましたが、やがて決心したように遠い空に消えて行きました。
「とうとう行ってしまった…」
淋しそうに肩を落とすばあさまを、
「あいつは森で暮らすのが一番仕合せなんだ」
じいさまが慰めました。
そのくせ二人とも何だか心にぽっかりと大きな穴が空いてしまったような気がして、カラスの飛び去った空を見つめていつまでも立ち尽くしていました。
一方、カラスはというと、あれほど恩を受けたじいさまとばあさまに別れを告げて来たにしては平気な顔をしています。それどころか、時折りにっこりと微笑みを浮かべたりしているところを見ると、森へ帰ることは、別れの悲しみを忘れさせてしまうほど心の弾むことなのでしょうか?
いいえ、そうではありません。カラスは今、胸の中に一つの素敵な計画があるのです。そして、それを実行するためには、どうしてもこういう形でひとまず悲しい別れを設定することが必要だったのです。