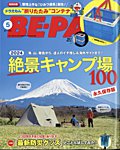奥山荘歴史の広場 胎内市
|
奥山荘は今日の胎内市、新発田市加治川地区の一帯に所在した中世の荘園遺跡で、10か所が国の史跡として指定された。奥山荘歴史の広場は、国指定史跡
奥山荘城館遺跡のうち復元整備した「江上館」と、そこから出土した遺物などを展示した奥山荘歴史館からなる。 昭和59年(1984)10月、中世東国を代表する荘園の奥山荘の荘域に形成された、城館遺跡・信仰関係遺跡・生産遺跡等の13か所が奥山荘城館遺跡として史跡指定された。国の史跡名勝天然記念物に指定して、保存を図ろうとするものである。
江上館跡 ※ストリートビュー ※GOOGLE 画像江上館は、三浦和田一族の惣領家中条氏の居館と考えられており、中条の中心に位置している。中条氏は、建仁元年(1201)5月、城資盛が逃亡し、鳥坂城が鎌倉勢によっておとされると、同年6月28日、奥山荘地頭として和田(のち中条氏という)宗実が赴任して以来、398年間、この地の豪族として繁栄し続けた越後の武将中の名門である。 この義盛の弟宗実が建久3年(1192)には軍功を賞され越後国奥山荘の地頭職を与えられた。和田宗実に男子がなかったので、娘(津村尼)の婿高井重茂(兄の和田義茂の子)が、宗実の後を継いだ。 高井重茂は、三浦和田一族にとってその運命を左右する和田合戦、宇治合戦(三浦泰村の乱)に際し、惣家に反旗を翻し、北条氏について戦い戦功を得て、奥山庄の地頭職を安堵され、その子高井時茂に伝え、有名を馳せた鎌倉武将、三浦和田一族の血を伝える名家として北越の地、奥山庄に連綿として君臨することになった。 「鎌倉殿の13人」の1人「和田義盛」は、源頼朝の挙兵に参加。軍功を重ね常に政権の中枢にいたが、北条氏の策略にあって、建暦3年(1213)5月、挙兵する。和田合戦と言われる戦いで、将軍実朝を擁し兵力で勝る義時が圧倒、和田一族は力尽き、義盛は敗死した。
1277年(建治3)、時茂は孫3人に奥山庄を分与した。その結果茂明が奥山庄の中心地を受け継ぎ、その子孫は中条氏と名乗った。その後、中条茂資(もろすけ)が南北朝時代の観応の擾乱の頃に鳥坂城を築き、詰めの城とした。戦国時代の16世紀頃、居館も鳥坂城の麓に移されたとされている。江上集落から行くと鷲麻神社がある。ここはかつての大手門の跡と推定され背後に大きな空濠をめぐらしてある。本丸の土塁を幅14.5m、高さ6mあり、北の角には鬼門おとしが現存し、堀は幅21.8mにおよぶ。本丸の南角には現在、土塁を一部崩して稲荷神社が祀られており、そこから西へ進めばもう一つの門があったと推定される地点におこもり堂が建てられている。その堂の背後から北へあの鷲麻神社へ向けて約80mに及ぶ土塁が見事に残される。 居館は、15世紀代に築造されたと考えられている。80年間にわたって中条氏の居館であった。 館内部は、南方の晴(ハレ)の場と北方の褻(ケ)の日常空間が設定され、塀で仕切られるようになる。館の周囲には家臣団の屋敷地や密教寺院などが配置されており、館が単独で存在していたのではないことが明らかになっている。 白磁、青磁などの出土品は中国(明朝)から輸入されたものが多く出土し、近くの水田からは明銭が出土していることからも、中世豪族が舶来の高級品を日常生活に使いうる力を持っていたことがうかがえる。 また南西300mの地点で江上館の前身にあたる坊城館が見つかったことから、本地域一帯が古くからの荘園の中心地である「政所条」内であったと考えられるようになっている。
≪現地案内看板より≫
 江上館は、三浦和田一族の惣領家中条氏の居館と考えられており、中条の中心に位置している。館内は60m四方で、土塁・堀を合わせるとほぼ一町(110m)四方となる。この一町四方という規格は、国人領主の身分を表している。館の存続期間は、ほぼ15世紀代に限られており、越後における方形居館の成立年代を考える上で貴重である。館には馬出状の郭が付属しており、当初から主郭の北方を張り出させるプランをとっていた。当初、南北の虎口は平入であったが、館の整備に伴って直進できない構造の虎口に造り変えられた。これは16世紀後半に織豊系城郭で採用されるより、1世紀も早い段階で成立していた先駆的なものとして注目される。さらに虎口の整備に伴って館内部は、南方の晴(ハレ)の場と北方の褻(ケ)の日常空間が設定され、塀で仕切られるようになる。 江上館は、三浦和田一族の惣領家中条氏の居館と考えられており、中条の中心に位置している。館内は60m四方で、土塁・堀を合わせるとほぼ一町(110m)四方となる。この一町四方という規格は、国人領主の身分を表している。館の存続期間は、ほぼ15世紀代に限られており、越後における方形居館の成立年代を考える上で貴重である。館には馬出状の郭が付属しており、当初から主郭の北方を張り出させるプランをとっていた。当初、南北の虎口は平入であったが、館の整備に伴って直進できない構造の虎口に造り変えられた。これは16世紀後半に織豊系城郭で採用されるより、1世紀も早い段階で成立していた先駆的なものとして注目される。さらに虎口の整備に伴って館内部は、南方の晴(ハレ)の場と北方の褻(ケ)の日常空間が設定され、塀で仕切られるようになる。なお、館の周囲には家臣団の屋敷地や密教寺院などが配置されており、館が単独で存在していたのではないことが明らかになっている。 また南西300mの地点で江上館の前身にあたる坊城館が見つかったことから、本地域一帯が古くからの荘園の中心地である「政所条」内であったと考えられるようになっている。  地図 地図
 ストリートビュー ストリートビュー
 |
|
|