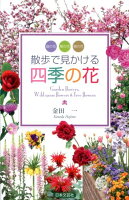ユキツバキ Snowy camellia 加茂市
| 雪国新潟には雪とかかわりの深い植物が幾つかあげられる。ユキツバキも、その一つである。昭和25年(1950)に植物学者本田正次博士が津川町で、一般にツバキと呼ばれてきたものと形態も性質も非常に違った新種のツバキを発見し、「ユキツバキ」と命名した。「カメリア・ルスチカーナ・ホンダ」という学名もつけられた。 ユキツバキは新潟県を中心とした日本海側の雪の多い各県の山地帯に分布しており、新潟県では昭和41(1966)年8月27日に県民投票で圧倒的支持を得て、新潟県の木として指定された。豪雪の中でも枝折れすることなく、早春に美しい花を咲かせる生命力が、新潟県民性をあらわしている、ということが選ばれた理由といわれている。 当時の「県の木選定委員会」会長であった吉田巖加茂市長は、加茂山公園に多く群生しいているユキツバキを県の木にしようと市民に呼びかけたのも功を奏した。 本州中央を東北地方ら中国地方にかけて脊梁山脈が連なっているため、日本海側と太平洋側で気候的特長が大きく異なっている。なかでも冬季の深雪が大きな違いといえるだろう。 雪にうもれてしまった地表面は恒温化するため、マイナス温度にはならず、植物の保護に役立っている。地表の寒風にさらされることもなく、すみやすいのである。このような特殊な環境の中で長い間生活しているうちに植物のなかには、少しずつこの雪圧に適応した形態を持つようになってきたものがいくつか知られている。ユキツバキも、その一つである。ヤブツバキのように立ち上がらず、雪圧に適応し、幹を横臥させ、不定根を出しながら横への広がりを見せる得意な形態のものである。 本県では雪の少ない海岸平野部には、ヤブツバキ、雪の多くなる山地帯にはユキツバキ、この接点付近では中間形のユキバタツバキと生育環境の違いが分布の条件となっている。ユキツバキの花はサザンカに似て平開し、雄しべは筒状にならず基部まで分離し、花糸は黄色、葉は葉柄が短く、その両側に細かい毛が生えており、葉脈も先端まではっきり見え、葉緑のきざみが鋭い。花は形や色が変化意富むことにより園芸的価値も高く、愛好家が多い。ヤブツバキの花はポトリと落下するが、ユキツバキには、それがない。 ユキツバキは山地のいたるところで見られるが、加茂市の加茂山公園のものが有名である。加茂山公園のユキツバキ園には野生種と園芸種を含め、約100種、1300本の雪椿が栽培されている。また、公園全体では、50,000本のユキツバキを鑑賞できる。 加茂市では県木にユキツバキが選ばれた翌年の昭和42年(1967)から加茂山公園を「ユキツバキ日本一の群生地」と銘打ち、雪椿祭りを開催し、加茂の名を一躍全国に広めた。 ユキツバキの開花時期 4月~6月
|