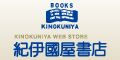| 1892年(明治25)1月8日〔生〕 - 1981年(昭和56)3月15日〔没〕 大正-昭和時代の詩人,翻訳家。詩訳集「月下の一群」や詩集「月光とピエロ」で昭和の詩壇に大きな影響を与えた。 明治25年(1892)1月8日、堀口九萬一と母政の長男として、東京・本郷に生まれる。在学中の子だったことから大學と名付けられた 父九萬一は、越後長岡藩下級武士の出身で、父親を戊辰戦争で失っている。新潟師範を卒業したが、この時寄宿先の娘政を見初め婚約する。この時政は11歳であった。 九萬一は、上京し東京帝国大學に入学し、明治23年(1890)政と結婚する。 明治27年(1894)、九萬一が外交官試験に合格した。この年妹花枝が生まれると、九萬一は外交官として朝鮮に単身赴任し、家族は長岡に引き揚げる。 明治28年(1895)、母政が死亡したので、祖母千代の手で育てられ、幼児期から長岡中学卒業までは、新潟県長岡で過ごす。大學は3歳で母を失い、若くして死んだ母のおもかげを、生涯追い続けていた。 父九萬一は大學が8歳の時、ベルギー人のステナ・ジュッテルンドと再婚した。後のことではあるが大學が渡航した際は、フランス語が母国語であった継母と生活を共にし、その影響をうけ、育つこととなった。 明治42年(1909)旧制長岡中学(現長岡高等学校)(※地図 ※GOOGLE 画像 )を卒業した。同級に小説『法城を護る人々』で知られた松岡譲がいる。卒業と共に上京、与謝野鉄幹、晶子の主宰する新詩社に入社する。大學の文学開眼であった。この新詩社で、明治43年(1910)、詩人で小説家の佐藤春夫を知り、生涯交友を持つ。佐藤春夫は大學と同じ、明治25年の生まれであった。 上京後も大學は、父九萬一とともに、たびたび長岡に帰郷している。父九萬一は、昭和18年(1943)から20年(1945)の死の時まで、夏になると墓参りをかね、長岡で親しくしていた杵淵家に来て、長逗留している。 明治43年(1910)、父九萬一に内緒で慶應義塾大學文学部予科に入学する。しかし、将来は外交官を継がせたいと考えていた九萬一は、文学にのめり込んで行く大學を心配し、当時の任地メキシコに呼び寄せた。 慶応大学の学生であった頃、小泉信三、久保田万太郎、佐藤春夫、堀口大學、水上滝太郎、小島政二郎ら学生が銀座のブラジルコーヒーカフェ『銀座パウリスタ』に通ったことから『銀ブラ』という言葉が生まれた。
明治44年(1911) 7月、大學は慶応を中退して、メキシコに向かったが、途中喀血、ホノルルで2ヶ月間の療養を余儀なくされた。当時は不治の病とされた結核で、大學にとっては宿痾の病であった。 大正2年(1913)父がスペインに赴くのに従って、ベルギーに行き、継母の義父の家に身を寄せる。しかし、ここで喀血、またまた4か月の療養を余儀なくされる。 大正3年(1914)、九萬一は、ヨーロッパで拡大した戦禍を心配して、大學をスペインに呼び寄せた。 大正6年(1917)、大學は、外交官試験を受けるため単身帰国する。しかし、筆記試験に合格したものの、口述試験の際に発病し、とうとう外交官の道を断念する。九萬一も、大學の身をあんじて、外交官にすることを諦めて、本人に任せることとした。九萬一は病弱な大學が文学の世界で名を成せるよう、任地に呼び寄せ、大學が30歳になる頃まで養って文学修業を助けた。 大學は、九萬一とともにヨーロッパにいて、フランス象徴派詩人、現代詩人に心を寄せていった。 大正8年(1919)、 処女詩集「月光とピエロ」、処女歌集「パンの笛」刊行。以後、昭和の詩壇におおきな影響をあたえていく。 昭和13年(1938)、継母のステナ・ジュッテルンドが癌のため69歳で没した。大學にとっては、フランス語習得の先生でもあった。 大正14年(1925)フランスの翻訳詩集『月下の一群』を出版する。出版は、同郷の長谷川巳之吉の経営する第一書房が行った。大學のすべての出版物は第一書房からとなった。以後次々と翻訳小説や自作詩歌集等出版。 大學の詩の特徴は、方法的にはウィッチシズムを、素材的にはエロチシズムを大胆に取り入れたといわれる。そのせいもあって、戦争中から戦後にかけて、その著書が淫猥を理由に発禁処分や出版拒否にあっている。 この大正14年(1939)中頸城郡名香山村関川(現妙高市関川)畑井要之亟の娘マサノと結婚。大學はこの時47歳、マサノは20歳であった。野尻湖畔のホテルで手伝いをしていたマサノを見初め、九萬一もその面倒見の良さを気に入ったという。 昭和16年(1941)10月、妻と共に静岡県興津に疎開する。 昭和18年(1943)、長男広胖が生まれる。 昭和19年(1944)、東京久世山に住んでいた九萬一が、興津の大學の疎開先に身を寄せている。 昭和20年(1945)1月、長女すみれ子が生まれる。7月、興津から妙高山麓(旧関川村)の妻の実家に一家で再疎開する。 10月31日、父九萬一が死去する。 昭和21年(1946)11月、高田市南城町に移った。住居は快適ではなく、食料事情も悪かったが、その頃の高田には、芥川賞作家小田巌夫や、写真家浜谷浩が疎開してきていて文化サロンの観があった。小田巌夫は、ここで『文芸雑誌』という雑誌を発行し、大學もここに寄稿している。 昭和25年(1950)神奈川県葉山一色へ移住。その後、昭和28年(1953)には、同じ葉山町堀内に転居し、ここが大學の終の棲み家となった。 昭和32年(1957)日本芸術院会員に推される。 昭和39年(1964)、長男広胖が白馬岳で遭難死した、大學は、大きな悲しみに打ちひしがれ「わが山」という詩を残している。 昭和45年(1970)、文化功労章を受章し、昭和50年(1975)には、葉山名誉町民に推され、近くの森戸神社境内には「花はいろ 人はこころ」の詩碑が建立された。 昭和48年(1973)、母校長岡高校のために作った「母校百年」の詩碑が、長岡高校前庭に建立され、大學はこの除幕式に参列した。 昭和54年(1979)、文化勲章を受章。 昭和56年(1981)3月15日、死去。89歳。 ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ☯平成9年(1997)、長岡市立中央図書館が「堀口大學コレクション」を開設 🔶代表作 詩集「砂の枕(まくら)」,歌集「パンの笛」など。
🔶記念碑
🔶墓所 神奈川県鎌倉市十二所512 鎌倉霊園 |