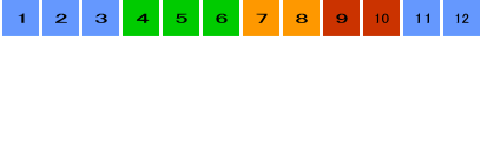| 国道403号線から布施谷川に沿って北へ向かい、北野橋を渡ると、右手の田の中に、隣り合ったエノキの古木に枝を絡ませながら曲がりくねって伸びた藤の古木と古い石の祠がある。古くから地元では「藤ノ木さま」と呼ばれ、親しまれている。※ストリートビュー 万葉集巻17に大原高安真人(高安王)(?~742)が詠んだ 『妹が家に 伊久里の森の 藤の花 今来む春も 常かくし見む』がある。 諸説あるが、地元では、伊久里は新潟県三条市井栗であると伝承されている。 万葉の藤の近くの伊久礼神社に、「万葉の歌碑」と呼ばれる碑があるが、明和元年(1764)、井栗村の大庄屋松川牧牛が建立したものである。 現在の藤は古い木ではあるが、この歌が詠まれたころのものではない。 昭和39年(1964)、市の指定文化財に指定されている。 三条市井栗には伊久里の藤にまつわる伝承が残されている。
昔、京都の旅籠へ美しい娘が訪れ、主人の伝兵衛に、「私は越後蒲原郡井栗村のふじといい京都見物に来たが、峠道で追いはぎに襲われ、財布を奪われてしまい、京都見物もできず、家へ帰ることもできません。」と懇願し、三日間宿に泊めてもらい、京都見物をして、帰りの路銀まで借りて帰った。 翌年の春、伝兵衛は、井栗村を訪ね、おふじという名の娘を探したが見つからなかった。伝兵衛はあきらめ、有名な伊久里の藤を見て帰ろうと思いたち訪ねると、満開の藤の花が咲く木の根元に「伝兵衛様 ふじ」と書いた紙に包まれて、小判が入っていた。用立てた金額の倍以上あったという。伝兵衛は「昨年京都見物に来た娘は、この藤の木の精が、人の姿に化身したものだったのか」といって、何時までも藤の花房に見入っていたという。
🌌住宅街にある小さな神社だが、歴史は古く、延長5年(927)に編纂された延喜式にも登場している。境内には明和元年(1764)、井栗村の大庄屋松川牧牛が建立し歌碑があり、万葉集の歌人・大原高安真人が詠んだとされる歌「妹我家尓伊久里能森乃藤花 今來牟春毛常加久之見牟」が記されているが、これは神社の近くにある藤の木を詠んだといわれている。 |
松川 弁之助享和2年(1802)4月9日 - 明治9年(1876)7月27日幕末・明治期の北海道開拓者。 井栗村の大庄屋・6代目松川三之助重基の6男として生まれ、50歳を過ぎてから蝦夷地に渡り、五稜郭建設工事に携わったほか、樺太漁場などの北方開拓に後半生をささげた。札幌市の開拓神社に祀られている。 |
 万葉の藤
万葉の藤  伊久礼神社
伊久礼神社