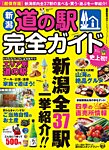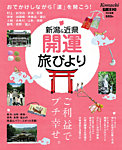| 8月14日~16日の3日間開催される「ふるさとわしままつり」。 14日には島崎・小島谷地域での盆踊り大会と花火大会が開催されます。15日は『道の駅良寛の里わしま』で行われる四千本の竹灯籠が幻想的です。 最終日の16日に島崎地域で開催される六夜祭は、800年の歴史があり、現在の形になったのは明治初期であるといわれます。 旧和島村の島崎地域にある「宇奈具志神社」に古くから伝わる秋の祭礼「六夜祭」では、赤い装束に弓矢を手にした20人位の子どもたちが、まちの東にある鎮守様「出田明神」から「宇奈月神社」までの道中、天に向けて弓を引きねり歩く「弓踊り」を奉納します。 長岡市の無形文化財にも指定されています。
六夜祭この祭りは800年の歴史があり、現在の形になったのは、明治初期であるという。宇奈具志神社に古くから伝わるお祭りで、わしままつりの最終日に行われる。宇奈具志神社の祭礼「六夜祭」に伴い、御神馬、みこし、てんぐなど100人余りで編成する行列が午後8時に宇奈具志神社を出発。良寛と貞心尼が歌をよみ交わしながら歩いたであろう「はちすば通り」など島崎地内を練り歩き出田神社まで進む。 宇奈具志神社までの帰りは、市無形文化財に指定されている「弓踊り」を勇壮に踊りながら進む。踊り手を務めるのは、地元の中学生16人。顔を白塗りしてえぼしをかぶり、赤い装束をまとって手には弓と弓矢。笛と太鼓の音にあわせて弓矢を射るように体をそらせて踊る。その発祥は明かではないが、武運を祈って始まったと伝わる。
宇奈具志神社 ※GOOGLE 画像言い伝えによれば、養老年間(717~724)、現在の神社が祀られている場所から約1km離れた水田に降臨されたのを奉斉し、『出田大明神』として人々に尊崇されていたという。鎌倉時代の宝治2年(1248)に現在の場所に移り、その後天和元年に火災により焼失。翌年再建、文政10年に改築、明治3年(1870)に社号を『宇奈具志神社』に改称。社境の土を麹室に塗ると麹がよくできるとされ、醸造の神、麹の神ともいわれている。
|
 宇奈具志神社
宇奈具志神社  出田神社
出田神社  はちすば通り
はちすば通り  道の駅わしま
道の駅わしま  長岡市和島支所
長岡市和島支所  島崎公会堂
島崎公会堂