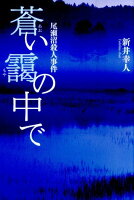|
大正11年(1922)に完成した大河津分水は新潟平野の洪水を激減させたばかりか、寺泊の海岸い大きな変化をもたらした。 この分水路は信濃川本流の4倍近い水を流し、同時に大量の土石を運んできた。そして、野積海岸から寺泊にかけて、長さ7キロ、幅約750メートル,300へクタールもの新しい陸地ができた。その後この土地は、国から民間に土地が払い下げになった。 海岸沿いを走る国道402号横に鮮魚専門店など十数店舗が軒を並べる。近くの寺泊漁港で水揚げされたベニズワイガニやノドグロなど日本海の幸を求めて、県内だけでなく高速道を使って首都圏からも年間200万人以上が訪れる。夏のシーズンばかりか、土・日曜には広く関東ナンバーの車などでごったがえす通称「魚のアメ横」は、この新しくできた土地にできている。 さて、この「アメ横」は、昭和49年(1974)、テレビコマーシャルですっかりおなじみになった角上魚類、そして翌年の山六水産の出店に始まる。角上魚類は江戸時代の網元で、のちに鮮魚の卸を兼業するようになった。1970年代は、新潟県内にもスーパーマーケットが広がり、個々に魚を卸していた。しかし、個々で売られている魚は非常に高く、もっと安い値段でと考えたのである。 角上魚類の社長柳下さんは卸業から小売業への方向転換を決めた。74年、寺泊漁港※ストリートビューから歩いて数分の国道402号(当時は県道)沿いに初めて出店した。 角上魚類が出店した当時、道は舗装されてなく、車もほとんど通らず、売上もほとんど ないというという状態であった。しかし、売り物にならないズワイガニを無料で食べさ せるなど、サ-ビスと価格に努力を払っていった。 中卸を介さずに直接魚市場で買い付けし、ほかの鮮魚店より値段を二、三割安く抑え、魚種も豊富にそろえた。近くの寺泊海水浴場を訪れる人たちが立ち寄り、徐々に魚の鮮度と安さが口コミで評判が広がった。新潟や長岡からも来るようになり、売り上げは伸び続けた。近くにほかの店も進出してきて、80年ごろに現在の「アメ横」ができ上がった。 現在年間200万人の観光客が訪れるという。このうち多くの人が、浜焼きも含め八店舗(四業者)で形成される「アメ横」に立ち寄っている。
 地図 地図
 ストリートビュー ストリートビュー
|