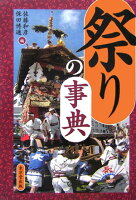盆踊り「大 の阪」 魚沼市
| 盆踊り「大の阪」は魚沼市堀之内八幡宮境内にて、盂蘭盆の8月14日から3夜踊られる。八幡宮境内には、高さ6メートルほどの踊り櫓を丸木で組み、その上に太鼓を据え、四隅に提灯を吊るし、櫓の中央には盆踊歌の詞章を側面に記した2メートルほどの長さの六角灯籠を吊り下げる。 近世には盆の13日から16日まで、各家々に提灯を掲げるなか、本陣を中心に町を一晩中踊り流し、裕福な家では酒食などを供して踊りを盛り上げたという。 堀之内地区は、江戸時代には三国街道の宿場町で、江戸時代中期、縮布の需要が増し、小千谷や十日町とともに越後縮の集散地として栄えていた。堀之内の縮市は、上方や江戸の商人で大いに栄えたといわれる。 「大の阪」の起源は定かではないが、江戸時代の中頃、旅する人々によって、江戸や京大坂の庶民の文化の流入がもたらされ、地元の文化と融合して作り出されたものといわれる。 太鼓の拍子(七拍)に合わせてゆったりと唄い、踊る足の運びや手ぶりは、単純素朴なもので、その緩やかな動きには、古風を感じさせ、優雅で洗練された踊りである。歌詞や身振りの「みやび」は京阪地方の系統を引くものである。 (音頭)大の阪ヤーレ七曲り駒を
笛太鼓の囃子方と踊り手が掛け合い式に歌を交わしながら「左回り」に踊る(左回りは喪葬儀礼の回り方という)。歌の合間に笛の間奏が入るが、これは昭和初年に復興した際に付け加わったものという。(踊手)ハヤレソリャよくめせ旦那様 (音頭)よくめせ駒を南無西方 (音頭)よくめせ旦那様 〽大の坂七曲り駒を よくめせ旦那様 〽てんま町橋にねて笠を とられた川風に 〽三才鹿毛の駒江戸で 値がする八両する 〽十三で糸をとれば糸は 細らで身が細る 〽十七は籠の鳥籠が せまくて遊ばれぬ 15ある歌詞は昭和35年(1960)頃、まとまったものである。昔は50余首もあったという。どの歌詞にも「南無西方」の文句がはいるので、「念仏踊」とも呼ばれ、節も御詠歌の哀調をおびている。 会津征討の戦乱、明治初年の禁令、明治・昭和の戦後など中断することもあったが、美しい旋律は人々の心から消えなかった。伝統的な盆踊りの姿を伝えるものとして、昭和29年(1954)には県の無形文化財の指定を受け、平成10年(1998)12月に重要無形文化財に指定されました。 🤩2022年11月30日、全国各地の41件の民俗芸能で構成される「風流踊」が、ユネスコの無形文化遺産に登録されることが決まり、新潟県内では「綾子舞」(柏崎市)と「大の阪」(魚沼市)が対象となった。
薮上神社 |
|
盆踊り「大の阪」まで 日
|