| 太平洋戦争末期の昭和20年8月1日、長岡のまちはB29の空襲によって焼け野原となりました。この戦災復興への力強い意欲と願いを込めて、昭和21年のこの日から「長岡復興祭」が始まり、翌22年には10年ぶりに花火大会が復活した。 その後、復興祭は年々盛大になり、昭和26年には「長岡まつり」に名称を変更。花火大会もまつりの一環として2日・3日に行うようになった。 (前夜祭)現在では8月1日に、戦災殉難者慰霊祭、灯籠流しのほか、民踊流しや30数基に市民の熱気がぶつかり合うみこし渡御などの前夜祭を開催。22時30分、長岡空襲が始まった同じ時間に慰霊と平和への祈りを込めた花火「白菊」が上がる。又この「白菊」は2日、3日の大花火大会の冒頭にも打ち上げられる。 (武者行列)8月2日に行われる武者行列は、戊辰戦争で敗戦となった長岡藩の窮状に、三根山藩から見舞いとして米百表が贈られたが、これを配給せずに小林虎三郎・三島億二郎らが教育の重要性を説いて、国漢学校の開設にあてた。その建学の精神を学び、長岡まつりのメイン行列のひとつとしたものである。行列は会津藩鉄砲隊、米百表の儀、騎馬隊などで。(大花火大会)2日・3日には、信濃川で豪快な大花火大会がおこなわれる。長岡花火は、天保11年長岡藩主牧野忠雄の川越移封が、翌年沙汰やみとなったことを岩って花火をあげたことが発祥である。戦時中に中止されたこともあったが、「復活祭」で復活した。正三尺玉やナイアガラ大スターマインが夏の夜空を彩るこの一大イベントには、市外からの観光客も大勢訪れます。 日本三大花火大会の1つとして知られる「長岡まつり大花 火大会」。 2005年8月2日、7.13水害・中越大震災・豪雪の3つの自然災害からの復興元年と位置づけ、復興祈願花火「フェニックス」が打ち上げられた。「フェニックス」は、花火の中心にフェニックス(不死鳥)に見立てた光跡が現れる尺玉(10号)花火である。 2016年には、「フェニックス」を両日とも5分フルバージョンで打ち上げたほか、新たにミュージック付きスターマイン「米百俵花火・尺玉100連発」が打ち上げられ大好評だったことから、今後引き続き打ち上げられることとなった。 2日間で約100万人を越える人出が見込まれる。(案内図)
|
|
長岡祭りまで
日
|

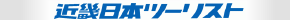
![【POD】長岡弁 新潟県長岡市長岡地域の方言[改訂版] 【POD】長岡弁 新潟県長岡市長岡地域の方言[改訂版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2408/9784991292408.jpg?_ex=200x200)
