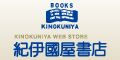| 1828年9月26日(文政11年8月18日)〔生〕 - 1877年(明治10)8月24日〔没〕 1828年(文政11)9月26日、長岡藩士小林又兵衛親真(長岡藩士、天保7年(1836)新潟町奉行となる 百石取り)の三男として誕生。名は虎三郎、または虎ともいう。字は炳文、隻松または寒翠と号す。家は、上級武士の中で、最下層であった。また、河井継之助とは姻戚関係にあり、その施策に強く意見することもあったという。 幼少の頃、天然痘にかかった虎三郎は、左眼を失明、顔面に痘痕が残った。しかし、このハンディをバネにして、長岡藩校崇徳館で学び、17歳にして藩校の助教を務めるほどの学識深い俊英だった。 1850年(嘉永3)23歳の時に藩命で江戸に遊学をし、当時兵学や砲学、洋学で有名な佐久間象山の門下に入りした。これは父の又兵衛が新潟町奉行時代、新潟に立ち寄った作久間象山と会った時、その見識に感銘して「むすこの虎三郎をぜひ門人にしていただきたい」と頼み込んだ因縁によるものだ。 長州藩士の吉田寅次郎(吉田松陰)と「象門の二虎」と称せられるほどに学問に秀でていた。勝海舟とも交流した。 また、象山に「天下、国の政治を行う者は、吉田であるが、わが子を託して教育してもらう者は小林のみである。」と言わせるほど、虎三郎は教育者だった。 虎三郎は象山とともにペリー来航をつぶさに見聞し、師の意見である横浜開港論を当時老中であった藩主牧野忠雅に説いた。このことが筆頭老中阿部正弘の忌諱に触れ、「藩士の身分で天下の御政道に反対するとは不届き」として帰郷、謹慎を命ぜられた。 1859年(安政6)、のちの教育第一主義の原点となる教育論『興学私議』を著わす。これが後の米百俵、国漢学校創設の思想的なバックボーンとなっている。 1868年(明治元)戊辰戦争では非戦を説いたが入れられず、戦争には加わらなかった。焼土と化した長岡で、敗戦後は大参事に推され藩政の責任者となった。 翌年1869年(明治2)、小林虎三郎は三島億二郎と共に長岡の復興に力をつくし、士族の師弟を四郎丸の昌福寺に集めて国漢学校を開設する。 1870年(明治3)、牧野家の分家、三根山藩主から長岡藩の窮乏を見かねて見舞いとして米百俵がおくられてきた。長岡藩では、この使い方について相談したが、飢えていた藩士たちはこの米の平等分配を要求して虎三郎に槍や刀を突き付けて脅した。しかし虎三郎は「みんなに分けてしまえば一日分の米で終わってしまう。これをまとめて人材養成に使えば何万俵にもなって帰って来る」と断固として要求をはねつけ、百俵の米を250両の金にかえて国漢学校や道場の整備に使った。 5月に坂之上町に国漢学校を開設して藩士の子弟を教育、渡辺廉吉(法学博士)ら多くの人材を出した。学習内容は、国学・漢学・地理・科学などであった。 この学校は1870年(明治3)、藩主牧野忠毅が領地を返上して柏崎県に吸収されたことから柏崎県の管理となり、それと同時に長岡小学校と名を改めた。こうした虎三郎の米百俵の精神が実り、明治維新後、長岡からは数え切れないほどの著名な人材が輩出している。 山本有三はこの話に感動、『米百俵』を書き、新国劇名などでも上演された。
虎三郎は1871年(明治4)、「病翁」と自ら名を改めているが、幼いとき罹患した天然痘の後遺症によって、リウマチ、腎臓病、肝臓病などさまざまな病を患っていた。「百俵ばかりの米を家中の者たちに分けてみたところで、一軒のもらいぶんは、わずかに二升そこそこだ。一日か二日で食いつぶしてしまう。あとに何が残るのだ。おれは、この百俵の米をもとにして、学校を立て、道場を設けて、子どもを仕立てあげてゆきたいのだ。この百俵は、今でこそただの百俵だが、後年には一万俵になるか、百万俵になるか、はかり知れないものがある。その日暮らしでは、長岡は立ち上がれない。あたらしい日本はうまれないぞ」 『米百俵』新潮文庫より この年以後は上京し療養につとめながら、著述に没頭した。洋学のみならず漢詩、漢文にもすぐれ「講学私議」「小学国史」など多くの著作を残した。死後、甥の小金井権三郎によって「求志洞遺稿」が刊行されている。 1877年(明治10)、湯治先の伊香保で熱病に罹り、8月24日に東京府東京市内にあった弟の雄七郎宅で死去。享年50。 虎三郎には、妻子があったが、子が早世し、後に妻とも離縁している。小林家の家督は長兄、次兄とも死亡しており、弟が継いでいる。 葬地は東京の谷中墓地であったが、1959年(昭和34)に長岡市内の興国寺に改葬された。 (没後) ☯1993年(平成5)に「米百俵 小林虎三郎の天命」 が中村嘉津雄主演でオリジナルビデオ化される。 ☯2001年(平成13)5月13日、国会における所信表明演説で小泉純一郎首相(当時)が「米百俵」を引用したことで、小林虎三郎の故事が全国的に知れ渡った。 ☯2002年(平成14)10月5日、長岡の地に今尚、深く根付く“米百俵の精神”を伝える「第1回米百俵まつり」が、大手通周辺で開催された。 ☯2018年(平成30)度から初めて使用される小学校のの「道徳」の教科書検定では、愛国心の高揚が求められ、教材の一つとして「米百俵」が取り上げられていた。 ☯2023年(令和5)6月、晩年の療養中に書いた「伊香保日記」の新たな冊子が見つかる。 🔶記念碑
🔶墓所 |