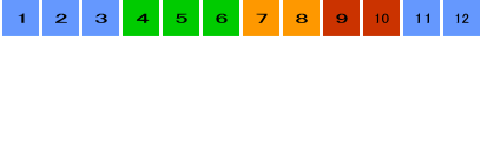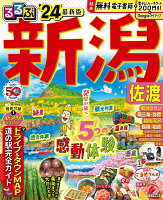秋葉公園 Akiha Park 新潟市
| 🔗桂家 新津の緑といえば何と言っても秋葉公園に代表される秋葉丘陵地。桜の名所として知られている。見晴広場周辺に200本、その奥の秋葉湖畔に桜並木があり、公園全体で1000本ほどの桜の樹がある。 新津駅の南東約2キロ、市街のすぐ南側に盛り上がる秋葉山一帯を自然公園化したもの。 南側には赤松林を始め、小楢(こなら)、杉などの森林に覆われており、秋葉湖と呼ばれる湖沼や白玉の滝、またいくつかの清水がある。 頂上に五峯閣、展望台と白亜の平和塔、西側に秋葉神社。ほかにアスレチック、運動広場、動植物観察、キャンプ場、野外音楽堂など野外活動のための魅力的な施設がたくさんあって、これらははりめぐらされた遊歩道によって、広い範囲を自由に散策できるようになっている。 森林浴とともに、様々な植物や野鳥の観察にはもってこいの場所です。 平和塔の内部には、昭和29年(1954)にインドのネール首相から送られた仏舎利がおさめられている。 公園は全体で60ヘクタールほど在るが、これまで整備されたのは30ヘクタール程度だという。 秋葉山はそもそも宝暦11年(1761)に庄屋の桂家が、新発田藩から功績によってもらい受けたものだという。当時、五頭連峰から吹き下ろすだしの風の通り道にあたる新津の人々は火災をもっとも恐れ、桂家も自宅の神社に火の神の秋葉大権現を祭っていた。その神社を貰い受けた山に移し祭神の名をとって秋葉山と名づけたといわれている。この山も戦後、あちこちが人手に渡るなど変遷をたどり、その後、市が総合公園として整備に乗り出した。 (案内図)
🔙戻る
🌌正面広場(噴水広場)秋葉公園の入口にあり、7m高さまで吹き上げる噴水がある。秋葉山の老松を背景に五色の噴水はその色を変えながら美しい虹を描く。🌌日本庭園旧桂山荘の庭だったところに地形を生かして、池やヒノキとスギ材で造られた東屋がある。ここから新津の街並みと新潟平野を雄大に眺めることが出来る。茶道愛好者による野点等の会場にも利用されている。🌌秋葉神社 ※GOOGLE 画像秋葉神社を創建した桂家は桓武天皇の皇子である葛原親王に始まる家柄であり、葛原親王から数えて13代目に当たる治部卿親輔の子秀行は春日神社を興すため能登国に下り葛原家を興しました。葛原家16代誉秀が能登国から越後に移り、善道興野(現、新潟市秋葉区善道町)に住み桂原と改姓し、更に子の代以降は姓を「桂」と称した。3代六郎左衛門誉春の代には隆盛となり、新発田藩勝手方御用役を命じられ、新発田城西門の普請を勤めた功により庄屋格に取り立てられた。宝暦11(1761)年には新発田藩領主溝口氏より神社建立のため田家山を賜り、宝暦13年(1763)に祖先より邸内に奉祀してきた秋葉神社をここに奉遷し当地の鎮守とした。これが現在の秋葉神社の始まりとなった。この山は「田家山」と称していたが、以降は「秋葉山」と称するようになった。 神社周辺には神々の伝説が残る七色の池や、自然豊かで動物もいる秋葉公園があり、行楽の地としても親しまれている。神社拝殿裏手から本殿までの間はトリムコースの一部にもなっている。 〔御祭神〕
�秋葉神社拝殿
🌌秋葉山見晴公園 ※GOOGLE 画像春の園遊会や平和塔祭りには約3万人の観光客でにぎわう。公園には、平和塔、平和像が建立されている。また、日本猿・小鳥などの小動物も飼育されていて子供たちに親しまれている。一般行楽客用に無料休憩所五峯閣もある。🌌平和塔 ※GOOGLE 画像昭和29年(1954)にインドのプラサイド大統領と、ネール首相から日本の永遠の平和のために新潟県民に贈られたお釈迦様の舎利(お骨)を安置し、平和を祈念するとともに、風光明媚の秋葉山見晴公園に当市の観光の象徴と舌建てられた。平和塔には、平和国家建設の尊い礎となられた戦没者各位の英霊と、希望によって故人の霊、無縁の霊を祀っている。塔の高さ21.48m、規定19.6m。🌌秋葉山キャンプ場 ※GOOGLE 画像遊歩道の整備と共に公園も整備され市内随一のキャンプ用野外施設となっている。フリーサイト10区画でキャンプ場利用については、秋葉区建設課へ事前申し込みが必要。付近ではサンコウチョウや、カラ類にエナガ、コゲラ等の鳥たちがいる。杉林に入る。ウグイス、ヤブサメ、沢からオオルリの声が聞こえる。🌌遊歩道春には新緑と数十種類の小鳥のさえずり、夏にはセミの声を聞き、秋には満山紅葉を楽しむなど四季折々の風情を鑑賞できる。カラ類にエナガ、コゲラ等の留鳥のほかに、杉林からはウグイス、ヤブサメ、サンコウチョウ、オオルリの鳴き声が響く。公園内にはウォーキングに最適な全長4キロメートルのトリムコースと、秋葉湖から石油の里まで整備されている「木もれ日の遊歩道」コースがある。 トリムコースのスタート地点は日本庭園となっていて、案内図に従って散策するとよい。 桂家江戸時代前期の寛文元年(1661)、能登国飯田(石川県珠洲市飯田)から移住し、葛原誉秀を祖とし、寛文11(1671)年に善道興野に居を定めた。2代誉智のときに葛原の姓は皇室に対し不敬であるとして桂原と改姓し、新津桂家の祖となり、「桂原」の原の字を省き、桂と称するようになったという。 3代誉春の代に、元文元(1736)年11月には新発田藩勝手方御用役を命じられ、寛保元(1741)年9月、新発田城西門の普請を勤めた功により庄屋格に取り立てられ、苗字帯刀の家柄となった。殖産事業にも尽くし、茶園・下興新田開発で財をなした。 宝暦11(1761)年には新発田藩から神社建立のため田家山を与えられたので、宝暦13(1763)年9月、京都よりご神体を勧請して秋葉神社※ストリートビューを建立した。これ以降田家山は「秋葉山」と呼ばれるようになった。 4代誉章は、明和元(1764)年に新発田藩領新津組22ヵ村の大庄屋となった。代々敬神尊王を家風とし、松岡仲良について垂加神道を学び、書籍数万巻を収集して、邸内に書庫を設けて「万巻楼」とした。 6代誉正は平田篤胤の門人に入り、本居内遠、大國隆正ら国学者と親交があった。 7代誉重は、父祖以来の治績をうけて民政の実をあげるとともに、一層国学に傾頭し、平田学派の門下として勤皇の志が篤く、鈴木重胤の高弟となり、出羽庄内の大滝光憲とともに東国における国学扶植の中心的存在であった。また重胤の有力なパトロンとして、師の大著「日本書紀傳」147巻の出版を援助した。彼はまた佐藤信渕より農政を学び、自ら「済世要略」「世継草摘分」などの書を著し、国学の教化によって産業経済の実を図ろうとした。 8代誉恕は、父誉重や重胤を師とし慶応4年(1868)の戊辰の役には父とともに勤皇を唱え、越後攻略の官軍に兵糧を献じ、自宅を会津攻めにむかう山県有朋率いる新政府軍の本営に提供した。そして父誉重とともに官軍の先鋒として活躍した。 山県は、西郷隆盛が兵をともなって新潟に上陸した際には、ここから長駆馬を飛ばして向かったという。 🔙戻る
|
|
 秋葉山見晴公園
秋葉山見晴公園  秋葉苑
秋葉苑  秋葉湖
秋葉湖  五峯閣展望台
五峯閣展望台  正面広場(噴水広場)
正面広場(噴水広場)  日本庭園
日本庭園  秋葉神社
秋葉神社  平和塔
平和塔  秋葉山キャンプ場
秋葉山キャンプ場  秋葉神社拝殿
秋葉神社拝殿