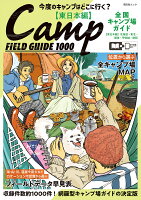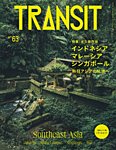| 大石ダムは、昭和42年8月28日の羽越水害を契機に、国が7年の歳月と172億円の巨費を投じて昭和53年8月に完成した重力式の多目的ダムで、付近一帯は公園になっています。 大石ダム下流に作られた県民憩いの公園。夏には、緑あふれる大自然が、秋には紅葉の絶景が広がり、多くの方々が訪れます。ゴーカート、ミニSL、バッテリーカーなどの乗り物や、小動物園などお子様連れにも人気のスポットです。(案内図)
大石川渓谷関川村の東西を貫いて流れる荒川の支流、大石川は、飯豊連峰の北端に座する朳差岳(16346.4m)に源を発する。大石川の奥地は峻嶮だが美しい渓谷を見せる。大石ダムは高さ87m、幅243.5m治山治水・発電の多目的ダムである。ダムができ河川改修がなされるまでは、かつて「暴れ川」だった。 ダム直下の左岸下流公園に通ずる赤い橋からの渓谷が美しい。流れは緩やかで、両岸が深く切れ落ちる。公園には駐車できるスペースもある。 大石ダム ※GOOGLE 画像昭和42年8月、荒川流域はかつてない大雨に襲われ、洪水や土石流によって、新潟県側で死者・行方不明者90名、被害総額445億円を出し、壊滅的被害を受けました。尊い命が失われ、多くの田畑や建物が流された。この「羽越水害」を契機に昭和45年に工事が着工され、昭和53年に完成した「大石ダム」は、荒川流域の人々の生命と財産を洪水から守り、あわせて発電を行うことを目的としてつくられました。 大石ダムは、洪水に備えて、6月から9月までの期間、水位を約30m低下させておくなど制限水位維持のために各種の設備を設けているほか、山間部で雨雪の多いことを考慮した様々な設備が設置されています。 大石ダム完成以降、大きな洪水災害が起こることもなくなりました。大石ダムはこれからも地域の安全を守り続けています。 関川村の伝説 大里峠(おりとうげ)むかしむかし、女川の蛇喰に「忠蔵」、「おりの」の夫婦と娘の「なみ」が仲よう暮らしていたど。忠蔵が炭焼きしてると、大蛇が出てきたんだど。忠蔵は持っていた斧で大蛇を退治して、味噌漬けにしたてがねェー。なんと十二樽半もできたど。おりのは、「この樽は見んなよ」と言われたことも忘れて、大蛇の味噌漬けをみんな食ってしもだど。のどがかわいたおりのは、女川の水を飲みにいったら、なんと、おっかない大蛇の姿になっていたんだど。それから、「何年もたったある日、蔵市という座頭が大里峠で琵琶をひいていると、「法師さま、もう一曲聞かせてくださえんし」と美しいおなごの人があらわれたど。おなごは、自分は大蛇になって、この大里峠をすみかにしているが、やがて、貝附の川幅の狭くなった所をせき止めて、荒川や女川を湖にして、そこをすみかにしようと思っていると語ったど。「このこどを誰かに言うだどぎは、法師様の命はねえもんと思うでくたんせし」と言い残して、生ぐさい風と一緒に姿をけして行ったど。 座頭は急いで夜道をくだって、下関にたどりついて、村の衆にこの話を聞かせ終えると、もう息をしてねがったど。そうして、琵琶と杖だけが残ったんだど。村の衆は、村中の鉄を集めて釘を作って、大里峠あたり一面に打ち込んだどサ。そうしたらばノー、大蛇はせつながって騒ぎたててとうとう死んでしもだど。 村の衆は、自分の命を捨てて村を助けてくれた法師さまを、神様としてまつることにしたんだとさ。下関の大蔵神社には、宝物としていまでも法師さまの琵琶がまつられているがネエ。 (※この伝説は、宝暦七年(1757)の大水害などを題材としてつくられたとする説がある。 関川村ではこの「大里峠伝説」と「水害供養」の二つをテーマにして8月28日近傍の休日に大したもん蛇まつりを行っている。)  |
 大石ダム
大石ダム  大石オートキャンプ村
大石オートキャンプ村  大石ダム湖畔公園小動物園管理所
大石ダム湖畔公園小動物園管理所  左岸下流公園
左岸下流公園