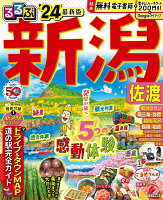| 文化年間(1804~1817)に上総国(千葉県)から苗を求め月潟梨として栽培されたものが始まりである。 かつての暴れ川中ノ口川は、川沿いにある月潟村に、ゆたかな土壌をもたらした。昔からナシ畑が広がり、名産地として知られるようになった。 現在も類産ナシの原木が、大別当の深沢家の梨畑にある。近年「二十世紀」など他品種におされ、栽培する農家もなくなり、この木は全国で唯一栽培されている樹である。今では市場出荷されることもなくなった。 この木が植えられたのは文化年間(1804-1818)といわれる。月潟村史によると、深沢氏の祖先、剛蔵氏が、上総の国から苗を持ってきて栽培をはじめたとされている。 推定樹齢200年、樹高3.0m、根元周囲2.4m、枝張りは東西6.6m、南北6.2mで、棚作りとなっている。※ストリートビュー 類産梨は県内で古くから栽培されている早生系赤、長十郎などと同じ赤梨系統の一品種である。果形は不斉の楕円形から卵形、果皮は茶褐色、果肉は白褐色である。葉がほかの和ナシより1.5倍ほど大きいという。 毎年11月に400個程収穫され、総重量にして100~150Kgに達する。翌年6月中旬まで貯蔵に耐える長所がある。 果肉はやや酸味があり、石細胞が多いので「ようかん」などの加工用に使用されている。 昭和16年(1941)、国天然記念物に指定された。昭和38年(1963)の豪雪で枝が折れるなどの被害を受けたため、昭和39年(1964)春に、20mほど離れた現在地に約1.2mの土を盛って移植した。 平成8年(1996)に樹幹部・根系部の外科治療、土壌改良等の内科的処置の結果、現在樹勢は良好である。
≪現地案内看板≫
国指定天然記念物 指定 昭和16年11月13日 樹齢二百年、根元周囲2.4m、樹高1.8m、地上1mのところから六本の大枝に分かれる。開花期は四月末、果実は卵型で翌年六月頃まで貯蔵に耐える。 この地の梨栽培の歴史は、文化年間、大別当の深澤剛蔵氏が上総国より苗を求めて植えたのが始まりとされている。 しかし、文政の越後大地震、天保の大飢饉などの天災もあり、庶民の生活は貧しく、梨の需要は伸び悩み、梨栽培は普及しなかった。 このような状況においても、剛蔵氏は研究を続け、次第に収益を上げるようになり、これに倣って他にも栽培する者が出てきた。 その後、利益の上がる養蚕が始まり、梨栽培は一時低迷したが、一部の熱心な農家が先進地千葉方面の栽培技術を視察研究し、明治十年頃から本格的に発展することとなり、大正期には栽培面積も六十町歩にまで広がることとなった。 平成二十七年三月 新潟市教育委員会 ≪月潟村の梨羊羹≫
地元の天然記念物、 樹齢200年の「類産梨」の実と厳選された材料を使用して作り上げた「梨ようかん」。 羊羹本来の甘みに、梨独特の美味さが加わり絶妙な食感で、現代風味の羊羹です。 マスヤ製菓 月潟の類産ナシ発祥の地  地図 地図
 ストリートビュー ストリートビュー
|
|