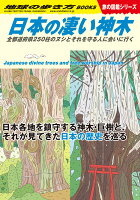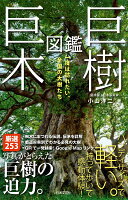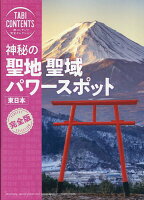|
「余五将軍維茂墓碑」のすぐそばに赤ら顔の巨大な杉が立っている。根元の周囲16メートル、目通りの幹周りは40メートルに広がっている。 3本の主幹の中の一本は昭和36年(1961)の第二室戸台風で折れてしまい、そこには、いまトタンをかぶせ覆ってある。残る二本が、さながらツノをはやしたかのように、たくましく延びている。ほかの大枝も合わせると、六本の巨枝が上へ向かってせり上げている。樹高40メートル。樹齢は記されていないが、推定樹齢1400年、屋久島の縄文杉に次ぐ巨木という。(平成12〜13年度に環境省が行った「全国巨樹・巨木林フォローアップ調査」での杉の部において、それまで日本一であった鹿児島県屋久島の縄文杉を抜いて名実ともに日本一の巨木となっている)。 昭和2年(1927)国の天然記念物に指定された。 水害で根回りに被害が発生したことも、また「本州一」が知られるようになると、観光客が根を踏み荒らし、皮がはがされた。このままでは枯れてしまうという判断から、平成9年(1997)に、樹勢回復手術と、根保護のため四方を木道で囲む工事が行われた。 11世紀、この地で晩年を過ごした、陸奥鎮守府将軍だった平維茂の遺骸を葬る際の標木として植えられたという言い伝えがある。「将軍スギ」の名も、これに由来する。しかし専門家の推定の樹齢はこれをはるかにさかのぼる。 将軍杉が地面から枝分かれした独特の形態となったことについて、地元に残る言い伝えがある。 昔この大杉の上に鷹や鷲が巣を作り、田畑を荒らしたり鶏や家畜を殺したりしたので、村人たちは相談してこの木を切り倒すことにした。大勢の樵たちが伐採にとりかかった瞬間、木は大音響をあげて、枝のところまで地中に沈んでしまった。現在根元から12本に分かれているのはそのためだという。村人たちは、この不思議な光景に驚き伐採を止めたという。 一説では、一度村人たちがこの木を舟材に使用しようとしたところ、一夜にして杉は地中にもぐったとの言い伝えがある。
≪現地案内看板≫
天然記念物 将軍杉 所在地 東蒲原郡阿賀町岩谷二〇一三 指定 昭和二年四月八日文部省 管理団体 阿賀町 我が国における日本一のスギである。推定樹齢約千四〇〇年、幹のまわりは十九メートル三十一樹高約四十メートルに達する。根元の近くから六本の大支幹にわかれているが中央の一本は昭和三十六年秋の第二室戸台風のため折損した。 樹下の「余五将軍維茂墓碑」は、この地に晩年を送ったとつたえる陸奥鎮守府将軍平維茂の業績をしのび寛文八年会津藩主保科正之が建てたもので将軍杉の名もこれに起因する。 その昔、村人がこの杉を切り、船を造ろうと計画したところ、一夜にして地面に沈んでしまったという伝説が残されている。 |