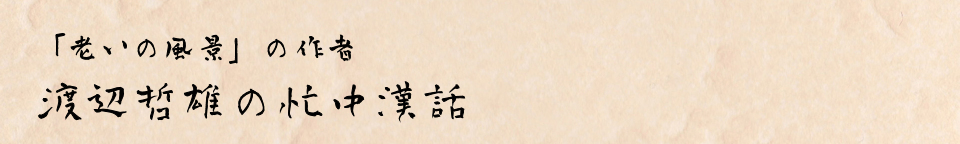「畳」
畳という文字は、タタミがうずたかく積み上げられているように見えます。一番上の一枚は立て掛けてあるのでしょう。
中学生の時に短期間だけ所属した柔道部では、先輩部員が来る前に、体育館の隅に積み上げられた畳を床に敷き詰めて道場を作るのは新入部員の役割でした。ウッと力を入れて持ち上げた畳を、反動をつけてくるりと背中に背負い、ばたんと床に下ろしては敷いて行きます。その度に、もわっとホコリが舞って、畳特有の匂いが立ちのぼります。表面のすべすべした感触が嘘のように、畳の裏はザラザラした藁(わら)が剥き出しで、柔道着の上からも背中がチクチク痒くなりました。部活が終わると再び新入部員の手で畳を元のように積み上げたのでしょうが、積み上げる作業のことはすっかり忘れてしまい、敷き詰める作業ばかりが思い出されるところを見ると、人間の脳は、後始末よりも準備の方を記憶するようにできているのかも知れません。
私の実家は零細な印刷屋でしたが、道を挟んだお向かいも零細な畳屋さんでした。トラックで運び込まれた大量の藁が、切り揃えられ縫い合わされ、青い畳になってどこかへ運ばれて行きました。父と息子がたった二人で営む家内工業でしたが、二人とも日がな一日、畳一枚分の大きさの、背の低い作業台の前であぐらをかいて、藁でできたマットにすべすべのタタミオモテやヘリを縫い付けていた様に思います。畳針という太い針を肘でぐいっと畳に突き刺しては縫いつけてゆく作業は、腕の筋肉を絶え間なく誇示するような格好になって、我が家の印刷屋に比べると格段に男らしく見えたような気がします。子供の私が店先から物珍しそうに眺めていても、二人の男たちと親しく口を利いた記憶はありません。ランニングシャツを着た汗まみれの男が二人、黙々と畳を縫い上げて行く様子は、私の中で「労働」というものの原型になっています。ときおり片方だけ持ち上げた男のお尻で鈍い音がする度に、恥ずかしそうに目を逸らすのは私の方でした。人差し指で片方の小鼻を押さえて、ふんっと肩を上下させると同時に、水洟が勢いよく作業場の藁くずに飛ぶのを見ては、あれはいつか畳の中に織り込まれてしまうのではないかと、子供心に心配になりました。
我が家は畳屋さんが回収して来る古畳をもらい受け、畑で腐らせて肥料にしていましたが、
「哲雄、この頃の畳は、ほれ、糸がいつまでも腐らんで、備中にからまって畑が耕せん」
母親がそうこぼした頃には、既に畳には丈夫なビニール製の糸が使われ始めていたのですね。やがて田んぼは次々と宅地になって藁が手に入り難くなり、残った田んぼも、コンバインが刈り取りの時に藁を短く切断して使いものにならなくなりました。そしてとうとう糸だけでなく、ビニール製の畳が工場で大量に作られるようになって、畳屋は廃業しました。
対岸の火事ではありません。ワープロの登場と、家庭用印刷機の普及によって、我が印刷屋も畳屋を追いかけるように廃業しました。桶屋、鍛冶屋、指物屋、襖屋、餅屋、鋳掛屋、唐笠屋、提灯屋・・・あの頃、郡上八幡の町に軒を並べていた職人たちが相次いで姿を消しました。風呂の手桶がプラスチックになり、テレビだ、冷蔵庫だ、洗濯機だと、まるで文明開化のような昭和の経済成長を歓迎していた結果が、何ともやりきれない今日の均一社会です。自分の腕一つで家族を食わせているという自信に満ちた職人たちの笑顔の代わりに、プラスチックのような表情のサラリーマンがあふれました。すっかり平板になってしまった世の中で、畳という文字だけは、懐かしい藁の匂いと共に、大人たちが貧しくもはつらつと暮らしていた職人の時代を思い出させてくれるのです。
終