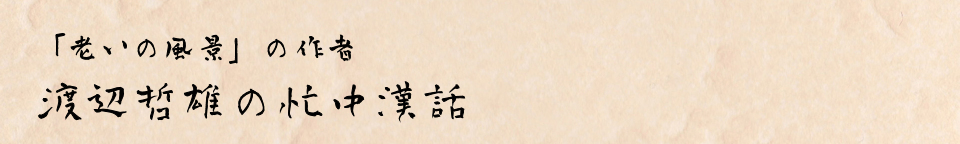「亀」
『亀』という字はカメにしか見えません。甲羅から頭としっぽを出して、しっぽはくるりと右に曲がっています。誰が考えたのでしょうか、視覚に訴える文字は見ているだけで今にも動き出しそうな気持ちになりますね。
亀といえば、通勤帰りに危うく轢きそうになった亀を思い出します。もう何十年も前のことで、娘も息子もまだ小学生だったと思います。え?こんな生活道路の真ん中に何だってあんな大きな石が…と見ると、石はのっそりと動くので、驚いて車を降りて見たら、甲羅の大きさが文庫本ほどもある堂々たる亀でした。
人通りはありません。
私はその亀を車のトランクに入れて持ち帰りました。
「おおい、カメだぞ、カメを拾って来たぞ」
「あ、本当だ!カメだ」
「カメだ!」
興奮する子供たちは、まるで昔の私でした。
「哲雄、大川に逃がしてやろう。喜ぶぞ」
母に言われると、とてもいいことをしようとしているような気持になりました。黄昏時…。大川にそそぐ乙姫川に沿った狭い道を、ひんやりと冷たいカメを両手に持って新橋に向かって歩きました。母は橋から大川が見下ろせるように、私の腰を欄干の高さまで持ち上げました。してみると、私は背丈が欄干に届かないくらいの年齢だったのですね。夏は勇気自慢の子供たちのダイビングで有名な新橋の上からのぞき見る吉田川は、はるか眼下で豊かな水量をたたえて流れています。カメは私の手の中で、まだ自分の運命を知らずにいます。これから十数メートルの高さを落下して、突然、眼下の大川の住人に加わるのです。
母と私は黙って川を見つめました。
ごうごうという瀬音の中に、不気味な死の闇が口を開けているような気がして、私は急にカメに対してとんでもなく悪いことをしようとしているような後ろめたさに駆られました。
「ほれ哲雄、逃がいてやれ!」
母の言葉に促されて手を放すと、カメは石のように落下して白いしぶきを上げました。
川はカメを一瞬で飲み込んで、何事もなかったように流れています。
「もう人間なんかに捕まるなよ!」
母はそう言って私を地上に下ろしました。
その言葉を聞くと、ついさっき心をよぎった後ろめたさはすっかり消えて、私は見知らぬ川の中で元気に泳ぐカメの姿を想像していたのでした。
子供たちに同じ経験をさせてやろうと思いました。
「名前をつけようか」
「カンタだ!カンタがいい!」
甲羅に赤いマジックでカンタと書いて、宝見橋から武儀川に放してやりました。そのときの心象風景を私は記述ができません。父親として子供たちに自分の幼い頃と同じ体験をさせてやりたかったという思い出に過ぎません。おとなより子供の心の方がはるかに多感なのでしょうね。水中に姿を消したカンタは、果たして子供たちの記憶に残っているでしょうか。東京で子育てをする側になった長女と長男に、機会があればカンタのことを聞いてみたいと思っています。
亀で思い出すのはもう一つ、小学校二年生だったときの学芸会です。私は主人公の浦島太郎に選ばれました。当時の学芸会は台本を渡されると、自分が演じる人物の衣装も小道具も各自で調達するルールだったのでしょうか。家族総出で浦島太郎らしい衣装と、釣り竿と、玉手箱と、そして亀を用意したことを覚えています。亀は金属の洗面器を白い布で包み、マジックで甲羅を描きました。綿を詰めた細長い布の袋を頭と足としっぽに見立てて洗面器の胴体に縫い付けると、どこから見ても立派な『亀』になりましたが、腕白小僧たちが吊り下げて棒で叩くと、亀らしからぬカン、カンという金属音がしました。
乙姫様を演じる女の子と私は、ほとんど出ずっぱりでセリフもたくさんありましたが、竜宮城で舞い踊るタイやヒラメの役の子たちは、頭に大きな魚の絵の付いた鉢巻を巻いて、ひたすら踊るだけでした。セリフを覚えて、大勢の観客の前で演技をしなければならない浦島太郎としては、黙って踊れば出番が済んでしまうタイやヒラメとの間の不公平を、悔しく思う気持ちと、誇らしく思う気持ちを交互に経験したことを覚えています。
圧巻はラストシーンでした。
浦島太郎は、開けてはならない約束で乙姫からもらった玉手箱をステージの中央で開けました。すると箱からは白い煙が立ち上り、浦島はたちまち白髪のおじいさんになってしまいます。
実は母と祖母のアイデアで、玉手箱の中には火の付いたタバコが固定してあって、蓋を開けると充満していた本物の煙が立ち上るようになっていました。蓋の内側には目を見開いた顔の白髪のじいさんのお面が裏を手前にして画鋲で貼り付けてありました。お面にかけ渡した割り箸を口にくわえて蓋を脇に置けば、画鋲が外れて、お面は私を白髪のじいさんに変身させてくれる仕掛けでした。
家で何度も練習した甲斐あって、観客は変身した私の顔を見ると、身を乗り出して驚きの声を上げました。拍手喝采を浴びた浦島太郎は、『予餞会』という卒業生を送る会で特別に再演することになりましたが、問題を二つ残しました。
一つは浦島太郎とタイやヒラメとの間の余りにも歴然とした扱いの差が保護者の間で問題になりました。学校に不公平を嫌う機運が生まれたのですね。
もう一つは、開けてはいけない玉手箱をどうして乙姫は浦島に渡したのかという謎でした。この謎は、今も私の心の玉手箱の中で解決をするつもりのない懐かしい謎として大切に保管されているのです。
終