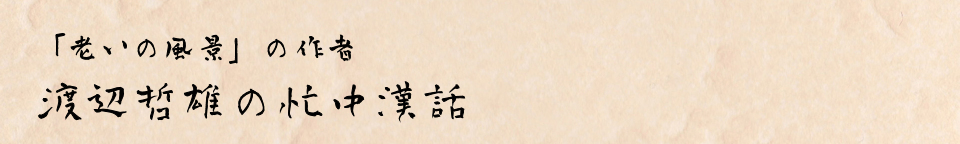「祟」
祟は『たたり』と読みますが、長い間、崇『たかし』という字と区別がつきませんでした。崇は崇高という熟語を作ることで分かるように、『けだかい』とか『あがめる』という意味ですが、崇という名前の人に出会う度に、
「これって、たたりとも読むんだよな?」
不気味な名前を付けたものだと密かに命名した人の感性を訝しむと同時に、そんな名前を付けられた目の前の人物を気の毒に思ったものでした。
今般『祟』という文字を忙中漢話に取り上げるに当たり、文字の構造を子細に眺めてみて積年の不明を恥じました。『たたり』は『出』に『示』と書くのに対して、『たかし』は『山』に『宗』と書いて、全く別の漢字なのです。
それにしても『出』に『示』と書いて『たたり』と読むのはなぜだろうとぼんやりと考えるうちに、三十年以上も昔の出来事が鮮やかに浮かんできました。
私がソーシャルワーカーとして勤務する総合病院に、生活保護を受給している高齢の痩せた男性が入院して来ました。病名は忘れてしまいましたが、呼吸器科の病棟に入院した彼は、間もなく症状が悪化して危篤状態になりました。私は市の担当者から聞いていた一人娘に連絡をとりました。勤め先の家電量販店を早退して娘がタクシーで病室に駆け付けたときには、本人はベッドの上で断末魔の苦しみを呈していました。鯵の生き作りのように、末梢を小刻みに震わせてあえぐ様子を主治医と看護師がなすすべもなく見下ろしています。
「お父さん!」
病室に入るなり本人に取りすがろうとする娘を遮って、
「いえ、ご本人は何も分かりませんから、娘さんは外で待っていてください」
主治医は病室から出そうとしましたが、
「先生こそ、ちょっと外に出ていてください」
私は主治医を廊下に追い出して、
「さあ、耳は最後まで残るんだよ。きっとお父さんは分かるから、声をかけてあげて!」
娘を促して本人の顔に私の顔を近づけました。
「お父さん!」
「お父さん!」
私の頭部が邪魔をして娘からは本人の顔が見えません。
「え?分かったんですね?今、お父さん、うなずいたよ!」
私は顔を上げて娘に言いました。
「分かったんだよ!お父さん、娘さんの声が聞こえたんだよ!」
「お父さん!」
娘は父親に取りすがって泣き出しました。
主治医が慌ただしく入って来て、ペンライトで目を照らし、聴診器を当て、脈を取って、臨終を告げました。
目を真っ赤にした娘は、後のことは私と市の担当者に任せて帰って行きましたが、それからが大変でした。病室と市営住宅に残された本人の私物を片付けなくてはなりません。司法書士資格を持っているという本人の床頭台には、苗字の異なる十数本の認印が輪ゴムで束ねてありました。
「あの患者さんね、お菓子を買う度に、不良品が混じっていたという内容の手紙をメーカーに送って、新品をもう一つせしめていたのですよ」
メーカーも心得ていて、こういう客から手紙が来ると、さっさと新品を送って済ますみたいですね…と、売店のおばちゃんが憤慨していました。
市営住宅の原状復帰はもっと大変でした。高校を卒業した娘を隣の町の家電量販店の寮に住まわせて単身生活になった本人の部屋は、前日まで生活していた状態で突然留守になったのですから、洗濯機の中には衣類が浸かったままになっており、台所だけでなく、冷蔵庫の中でも生ものが腐臭を放っていました。そして机の引き出しには、病室の床頭台の比ではない数の認印の束がぎっしりと並んでいました。
「いかがわしい人ですね」
「離婚した元妻が横浜にいるみたいですよ」
「え?ああ、そうなんですか?」
「司法書士として随分羽振りのいい時代があったみたいで、家庭を顧みず、愛人を連れてハワイで豪遊したりして、妻からは愛想をつかされていたようです。本妻の間に子供がなかったので、年を取ってから愛人にできた子が可愛くてね、引き取って育てたのが病室にかけつけた女の子ですよ」
「ああ、それで父と子というよりも祖父と孫みたいだったんだ」
「暴力団がらみの筋の良くない仕事を引き受けていたのが災いして、司法書士資格は剥奪され、愛人には捨てられ、娘を連れて方々を転々とした最後の地がここだったという訳ですよ」
「…」
「…ということですから、価値のないものはゴミということでいいですよね?」
「いいんじゃないですか?」
私たちは手あたり次第、ゴミとして処分しました。
「これ、どうしましょう?」
部屋の隅に一抱えほどの大きさの黒い仏壇がありました。
「仕方ないんじゃないですか?」
「…ですよね!」
二人は一瞬躊躇しましたが、仏壇を上向きにして、その中に手あたり次第ゴミを詰めて、手配したゴミ収集車の荷台に放り投げました。僧侶に依頼して魂抜きをし、作法通り仏壇を処分する時間的ゆとりも金銭的余裕もありませんでした。生活保護の基準の範囲内で簡単な葬祭を行った骨壺は、横浜の元妻なる女性を説得して引き取りに来てもらうまでの数か月間、病院の相談室のロッカーの上にありました。出勤すると、まずは骨壺に手を合わせるのが私の日課になりました。
あれから三十年の間に、私の身の上にも、色々なことがありました。直腸の腫瘍を摘出し、翌年には胆嚢を取りました。県の職員を退職し、白内障の手術を受け、喘息発作で二度救急搬送されました。一連の出来事に、まがまがしいという意味を与えて『祟り』の原因を探せば、仏壇にゴミを詰めて廃棄した罰当たりな行為が真っ先に浮かびます。つまり『祟り』は、私の身の上にわざわいとして『出現』することによって、死んだ元司法書士の怨念の存在を『示す』現象を言うのでしょう。しかし、発見した病気は全て順調に克服し、新しい伴侶と職場を得て、命の尊さを自覚しながら、こうして文章を書いていることを良しとすれば、『祟り』など、心の不安の反映に過ぎないと断定していいのではないでしょうか。
心の鍵穴に『祟』という漢字を差し込むことで開いた三十年以上昔の記憶は、破天荒で波乱万丈な司法書士の人生の断面を見せてくれました。あのときの娘はもう五十歳に近い年齢のはずです。引き取られて行った骨壺は、どこに葬られ、誰が手を合わせているのでしょうか。死ねば仏という言葉がありますが、どんな生き方であれ、この世の役割を終えた人間の物語は、祟りなどという生々しさを離れ、崇高な印象がするものですね。
終