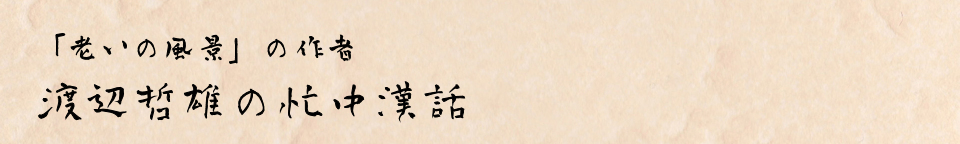「襖」
襖(ふすま)には、障子襖や板襖や唐紙襖などがあって、開ける度に人は奥へ奥へと進んで行きます。
奥へ奥へ…と言えば元禄の昔、火消し装束の浪士軍団が吉良邸を襲撃して、広大な屋敷の襖を次から次へと開け進むシーンが思い浮かびます。さてこそは…と襖を開けてもそこに目指す上野介の姿はなく、さらに奥の襖を開けても憎き仇は見つからず、最後にたどり着いた寝所の布団に浪士の一人が手を差し入れて、
「む…まだ温かい。吉良殿は近くにおわすぞ!」
と叫ぶ忠臣蔵のクライマックスは、まるでたくさんの襖そのものが主人公のようなシーンでした。
襖にはドアとは違った便利さと脆さがありますね。
開け放てば魔法のように広々とした空間ができあがる一方で、あっけないほど無防備です。他人の視界からはとりあえず中を遮りますが、鍵もかからず、音も筒抜けで、そもそも中の人物の安全やプライバシーを守ろうという発想はありません。だから時代劇では、悪代官の屋敷に乗り込んだ主人公が、襖ごと敵を斬ったり、襖の陰から繰り出された槍の柄を危うく小脇に抱えて応戦するする立ち回りが、乱闘場面の定番になっているのです。
子供の頃、と言っても小学校の低学年までの話しですが、その日ばかりは夜更かしを許された大晦日であるにもかかわらず、紅白歌合戦の途中で睡魔に負けて、私は襖一枚隔てた隣の部屋に寝かせられたものでした。ふと目を覚ますと襖の隙間から明かりが漏れて、歌合戦をしめくくる「蛍の光」の大合唱が賑やかに聞こえています。
「しまった、不覚を取ったか!」
とばかり跳ね起きて襖を開けると、祖父母と母が夕飯のご馳走の残りを囲んで燗酒を楽しんでいました。
「おお、哲雄、起きたか、起きたか」
さあ、お前もここへ来て食えと、ほんのり赤い顔をした祖父に手招きをされても、財布を落とした事実に気がついた時のように、取り返しのつかない損をしたような悔しさがつきまとって、しばらくは不機嫌だったような気がします。
その祖父が年を取って、ある日、自分が寝ている部屋の襖を指差してこう尋ねました。
「哲雄、そこの唐紙には何て書いてある?」
精神機能が衰えていたのですね。そうとは知らない私が、
「字なんか書いてないやろう」
批難めいた口調で答えると、
「ほんなら、そっちの障子には何て書いてあるんや?」
祖父は戸惑ったような視線を私に向けました。
「唐紙にも障子にも何も書いてないて」
何をわけの判らないことを言ってるんだ、と言わんばかりの私の態度に、祖父はくるりと背を向けて黙ってしまいました。
自分には確かに見える襖の文字を、孫は見えないと言うのです。祖父はその時、どんなに不安だったことでしょう。今だったら私は迷わずにこう言います。
「う~む、難しくて読めないなあ…。爺ちゃんは読める?」
「上手な字でも、ああ崩しては読めんなあ」
祖父はきっとそう答えて満足したに違いありません。
あれからしばらく生きて、祖父は九十二歳で死にましたが、襖はそのままになっています。時が過ぎて古びのついた襖を眺めていると、淋しそうな祖父の背中が浮かんで来るのです。
終