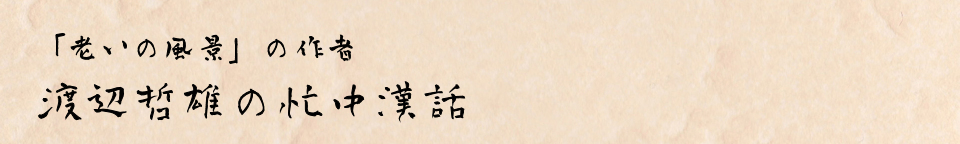「車」
この文字に黒く塗った鉄製の取っ手をとり付けて上から眺めればリヤカーです。それに赤い毛氈 (もうせん)の座席をしつらえれば人力車です。全体を木製にして、取っ手を長くすると大八車です。いずれにしてもこの文字は、原始的な人力の二輪車を上から描いたものに違いありません。
自宅から2キロほど離れた場所に畑を所有していた我が家では、その昔はリヤカーで畑に肥料を運び、リヤカーで畑から収穫物を運びました。肥料と言っても木製の桶に入った有機肥料ですから、考えてみれば、肥料の製造者が、自ら製造した肥料を畑にまき、自ら製造した肥料で育った野菜を食べて次の肥料を製造していたのですね。人間の体内から排泄された肥料は「肥え(こえ)」とか「肥し(こやし)」と呼ばれて、人前では口にできない響き…と言うよりは臭気を放っていました。モンペ姿の母親が長い柄の柄杓(ひしゃく)を用いて肥えをまく様子を人に見られるのが恥ずかしくて、私は畑の近くを同級生が通らないように祈りました。化学肥料の時代になって、肥えも木製の桶もリヤカーもすっかり過去のものとなりましたが、私の心の奥には、働く母親を恥ずかしいと思った罪悪感がかすかな痛みを発しています。日本神話ではイザナミの屍や糞尿から新しい神々が産み出されたように、汚穢(おわい)と呼ばれる究極の汚物から次の植物が萌え出ずる逆説は、生きることが刻々と死に行く過程でもあるという生命の実相に繋がっています。車という文字を眺めていると、私の意識はリヤカーに乗せられた小学生に戻って畑に向かいますが、背中には収穫物よりも木製の桶が並んで、車輪がくぼみにはまる度にチャプンいう不気味な音を立てるのです。
人力車には鎌倉と奈良で二度乗った経験があります。どちらも古い記憶なので、細部には霧がかかっていますが、思いのほか高い位置から通行人を眺め下ろす分不相応な優越感と、日焼けした車夫の腕で上下する筋肉のたくましさと、私のためだけに他人に肉体労働を強いているという申し訳なさだけは鮮明に蘇ります。もちろん車夫は私のために肉体労働をしているのではなく、生活のため、つまりは収入のために汗をかいているのですが、貧乏性ですね、自分で歩ける距離にもかかわらず、ひと様に車を引かせているという意識が、自責の念になって、どうにもくつろぐことができなかったのです。
同じ貧乏性の友人Sと中国旅行をした時のことです。残った中国通貨を北京で使ってしまおうと、看板につられて足湯マッサージの店に入りました。ビルの二階の小部屋に案内された私たちは、ズボンの裾を膝までまくり上げた格好で並んで座り、湯を張ったポリバケツに裸足の足を沈めました。中国服のスリットからなまめかしい太股が見え隠れする美しい少女が二人、それぞれの前にひざまずき、足指、足裏からふくらはぎまで、柔らかい素手で丹念に揉みほぐします。同じ衣装を着たもう一人の少女が、バケツに熱湯を注いでは湯温を一定に保ちます。気持ちがいいかと問われれば、むろん悪いはずはないのですが、何だか居心地が良くありません。病気でもない自分が隣国の若い女性をカネで買って足を揉ませているという行為に、人力車に乗った時と同じ種類の申し訳なさを感じてしまうのです。さらにその時の心中を拡大鏡で点検すれば、かつてこの国に大変な迷惑をかけた歴史的事実についての民族としての後ろめたさも関与していたように思います。その後ろめたさを払拭するように、私たちは四人の少女に盛んに話しかけました。日本語をわずかしか解さない相手に話しをしようとすると、こちらの日本語もカタコトになりますね。
「ニホンノ ウタ ナニ シッテマスカ?」
「ニホンノ ウタ?」
「ウタ、ウタ、ソング」
「キタグニノ ハル シッテマス」
「オオ、キタグニノ ハル!」
私たちは大声で『北国の春』を歌いました。
二人の中年日本人客がバケツに両足を突っ込んで歌謡曲を歌う珍しい光景に、部屋の間仕切りのカーテンが揺れて、外からあどけない少女の顔が二つ覗き込みました。
終