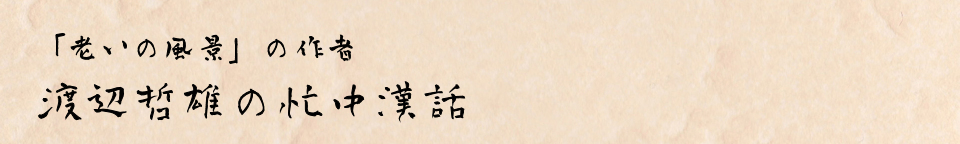「薬」
今でこそたいていの薬は化学製品ですが、その昔は薬草でした。煎じて飲めば体がらくになる植物だから、草かんむりに楽と書くのでしょう。
記憶に残っている薬草といえば何といってもドクダミです。学校の検査で体内に回虫がいることが判明したり、ゴム草履を踏み抜いた釘のあとが化膿したりすると、祖母が煎じるドクダミの臭いが家中に立ちこめました。
あの臭いを文章で表現してみたくて、ドクダミを知っている年齢とおぼしき何人かに尋ねてみましたが、みんな一様に、
「う~ん、長いこと嗅がないけど、あれって独特なんだよね、嫌な臭いなんだけどちょっと懐かしいっていうか、鼻で臭うんじゃなくて、吸った空気が体の中で臭うみたいな…あ~うまく言えない」
要するにかなり個性的な臭いなのです。
学校から帰って、ドクダミの臭いの充満する家の中に足を踏み入れると、たかが私の腸に棲みついた回虫を退治するために家族総出で取り組んでくれているような、不思議な幸福を感じたものでした。
非行少年の施設に勤務していた頃のことです。
挨拶をしてもそっぽを向く突っぱり中学生のY子が、夜、宿直室に訪ねて来て言いました。
「先生、お腹が痛い…」
「だいじょうぶか?」
常備薬をのませて顔をのぞき込むと、
「私、小さい頃からお腹が弱いの」
Y子は初めて見せる素直な表情で小学生時代の家族の思い出を聞かせてくれました。
「ある時、小学校へ行く途中でお腹が痛くなってね、お兄ちゃんがおぶって帰ってくれたの。心配するお母さんを私の方が慰めたりしてさ。あん時のお兄ちゃんの背中、大人の背中みたいに大きかったなあ…」
一粒の薬が、頑なな非行少女の心を開いた瞬間でした。
その晩遅く、Y子の様子が気がかりになって、薬と水を持ってそっと部屋を訪ねると、眠れないでいたのでしょう、Y子は小さな声で、
「ありがと、先生」
と言いました。
隣でK子がすっぽりと頭まで布団を被って寝ています。
「おやすみ」
小声で挨拶をして部屋を出ようとした私は、突然言いようのない胸騒ぎに襲われました。K子はあんなに小柄だったでしょうか。
勢いよく布団をはがすと、中には毛布が丸めてあって、かすかに窓のカーテンが揺れていました。
「お前、仮病を使ってK子を逃がしたのか!」
問いただす私に、うるせえ!と顔を背けたY子は、元の非行少女の目をしていました。
改めてY子の記録を読むと、職の定まらない夫に愛想をつかしたY子の母親は、子供たちを残して男と東北に逃げ、当時の兄妹は国民健康保険からも外された状態で、荒れる父親の暴力に怯えていました。Y子が話してくれた暖かい家族の思い出は、恐らく彼女が描いた叶わぬ夢だったのかも知れません。
時が流れました。
多感な思春期を多情に生きて、今頃はY子もK子も子育てに手を焼く普通のおばさんになっていることでしょう。
あのあと枕元の薬をどうしたのかは記憶にありませんが、薬といえばあの時のY子のありがとうという声が蘇って来るのです。
終