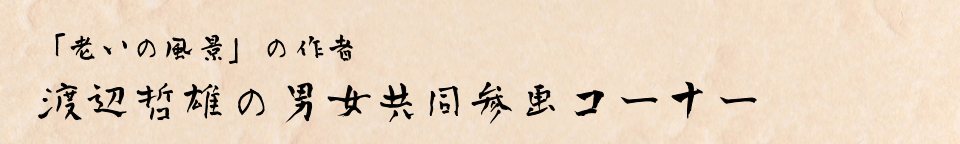- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 琴
琴
「あなた、智子じゃない?」
と声を掛けられて振り向くと、同級生の康代が黒い箱を下げて立っていた。
「こんなところで会えるなんて偶然よねえ」
という声は、次の新幹線の発車を知らせるアナウンスの音にかき消されて聞こえない。
二人は人波に押されるように改札口を出て、とりあえず構内の喫茶店に落ち着いた。
「何年ぶりかしら?」
「そうね、京都の同窓会以来だから…」
「じゃあ七年ぶりだわ。でもどうして東京へ?」
智子が聞くと、
「これよ」
康代は床の上の黒い長方形の箱を指差した。
「三味線ね」
「明日、国立劇場で地唄の演奏会があるの。智子は?」
「私?私は康代とは大違い。荷物だって見てよホラ、自家製の味噌でしょ?お漬物でしょ?畑でとれた里芋でしょ?」
「息子さんに会いに行くのね?」
「就職して四年になるというのに、電話をすれば、やれ出張だの接待だのって、一度も息子のアパートを訪ねる機会がないのよ。夫はよせって言うけど、私、きょうは思い切って連絡しないで押しかけて来たの」
「そう…うらやましいわ」
「あら、ごめんなさい。気を悪くした?」
智子は慌てて謝ったが、康代は落ち着いていた。
「私はもう大丈夫よ、ありがとう。そりゃあ確かに一人息子を事故で失った後、しばらくは途方に暮れてたわ。何もかもが色褪せて、生きてる張りがなくて…。女って結局どこかで子どものことを頼りにしてるし、生き甲斐にしているようなところがあるのよね。その虚しさから逃れるように夫は仕事に没頭し、私はもう一度地唄のお稽古を始めたの。あれから三年…。今ではお弟子さんも何人かできて、三味線のない生活なんて考えられないほどよ」
「強いわね…」
智子は康代の顔をまじまじと見た。悲しみを乗り越えた康代の顔は、はっとするほどたくましく、そして美しかった。
(強いのね…)
康代と別れて、混雑する山手線の吊り革につかまりながら、智子は心の中もう一度つぶやいていた。
最寄の駅でタクシーを拾って住所を告げると、和男のアパートはあっけないくらい簡単に見つかった。表札を確かめてドアをノックすると、
「はぁい!」
という女の声が返って来た。
思わず後ずさりして、もう一度表札を見上げる智子の目の前でドアが開き、若い娘が顔を出した。
部屋の奥から、
「誰だい?」
という和男の声が聞こえて来た。
智子は頭の中心に無理やり氷を詰め込まれたような衝撃とともに、ようやく事態を理解した。
「か、母さん!」
和男は智子以上にうろたえていた。
「そのうち、き、きちんと、話を、するつもりだったんだ。でも、とにかく、上がってよ、狭いけど…あ、美知子、お茶を頼むよ。そう、彼女、美知子って言うんだ」
「あ、始めまして」
美知子と紹介された娘は、ぎこちなく頭を下げると、そそくさとお茶を入れ、
「私、その辺りを散歩して来ますから」
気を利かせて部屋を出て行った。
二人の同棲は既に二年になるらしい。見回すと、きれいに片付けられた部屋のあちこちに、昨日きょうではない男女の暮らしの歴史が感じられた。
和男の話しによると、会社で合理化目的の人員整理があって、同じ課の閑職にあった徳さんという先輩が事実上解雇された。和男は嘆願書の発起人になったが、賛同者は思うように集まらず、終始美知子だけが和男の仲間であり続けた。二人は急速に親しくなると同時に会社という組織に激しく失望した。
いつか二人でアクセサリーの店を持ちたい…それが共通の夢になった。
「でも、いきなり会社を辞めるほどボクたち子どもじゃないよ。資金は給料を貯えるしかないからね。そのために一緒に住んで、美知子の給料はそっくり貯金してるんだ。いつ実現するかわからないけど、これは二人の生き甲斐なんだよ」
和男が見せてくれた貯金通帳には毎月決まった金額が振り込まれ、半年毎に定期にされて、残高は二百五十万円を越えていた。
(真面目なんだわ…)
智子は安心すると同時に、和男が自分の手の届かないところで暮らし始めたような気がして淋しかった。
それにしても康代といい和男といい、生き甲斐を持って生きている人間の顔というのは、どうしてこんなにも輝いているのだろう。
「これ、故郷の土産よ。二人だということがわかっていれば、もっとたくさん持って来たのにね」
「母さん…」
泊まって行けという和男を振り切って、
「まだ最終の新幹線に間に合うから…」
智子が部屋を出ると、暗がりに美知子が立っていた。
「ご心配をおかけして申し訳ありません、お母さん」
「和男のこと頼みますね」
智子は流れて来るタクシーに勢いよく手を上げた。
しかしなぜかそのまま戻る気はしなかった。
「どこか国立劇場の近くのビジネスホテルに行ってください」
無愛想な運転手にそう告げながら、智子は長い間家の床の間に立てかけっ放しになっている琴を、帰ったらもう一度習い始めてみようかしらと考えていた。
終