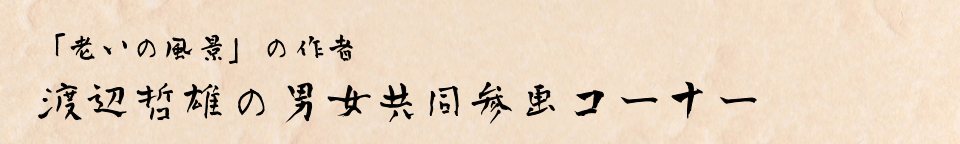- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 春枝の独り旅
春枝の独り旅
『しばらく留守にします。捜さないでください』と書いた置手紙を残して、北国に向かう列車に飛び乗った春枝は、生まれて初めての独り旅を、結婚後三十年も経った今、まさかこういう形で経験しようとは夢にも思っていなかった。
トンネルを抜ける度に、窓の外は急速に冬枯れの景色に変わってゆく。
(お正月の三が日が過ぎるまでは、絶対に戻らないから…)
春枝は心の中でそうつぶやきながら、一週間ほど前の総一郎とのやりとりを思い出していた。
「ねえ、あなた。裕介夫婦もお正月をスキー場で過ごすって言ってることだし、今度の年末年始は私たちものんびりと温泉で過ごすことにしたらどうかしら?」
「温泉?」
総一郎は小さな目をまん丸に見開いた。
「何を馬鹿なことを言ってるんだ。暮れに里帰りをするのは息子夫婦だけではないんだぞ。慎一郎だって誠一郎だって円一郎だって…」
「そうよ、あなたは六人兄弟の長男ですものね。綾子さんだってきっと子ども連れでやって来るし、智子さんはだんなさんの実家にはほんのご挨拶程度に立ち寄るだけで、あとはずっと我が家で過ごすに決まってるわ。毎年のことだもの」
「わかっていれば、くだらないこと言うな」
「くだらないことじゃないわ。今年は夫婦で留守にするからって、あなたからひとこと皆さんに電話を入れてくれればそれで済むじゃない?」
「お前、本気でそんなこと考えてるのか?」
総一郎は年賀状の宛名書きの手を休めて座り直した。
「いいか?正月ってのはな、散り散りになって生活している身内が年に一度集まって、健康を喜び、近況を語り合い、雑煮を食べて、酒を酌み交わす。そこに意義があるんだ。みんな懐かしい故郷に帰る日を首を長くして待ってる。慎一郎からの手紙、お前だって読んだだろ?」
「一緒に餅つきをするのを楽しみにしています…て、あれでしょ?もちろん読んだわ。でもね、そのお餅にしたって準備するのは私よ。もちろん後片付けも私、その後のお酒の世話も私…。ね?あなた、考えてみてよ、懐かしい身内が集まって健康を喜び合うのは結構だけど、その間だって私は台所で料理を作り、お皿を洗い、お酒を温め、皆さんが帰ってからは、山のような布団を干したり、シーツの洗濯をしたり…。お義母さんが亡くなってからというもの、お正月が来る度に、たった一人で普段の何倍も忙しい思いをして来たのよ。たまには私にだってのんびり骨休めをするお正月があってもいいと思うわ」
「それはお前、長男の嫁だから…」
と言いかけた総一郎は、思い詰めたような春枝の視線に出会うと、あわてて目を逸らし、
「まあ、どこの家でもやってることだ。運命だと思って諦めるんだな」
逃げるように立ち上がった。
春絵が独りで温泉に行く決心をしたのはこの時である。
密かに旅行会社に電話して、密かに旅館を予約した。
春枝が居なくなれば総一郎は困るだろうが、一度本当に困ってみればいいのだと思っていた。
列車は目的地に着いた。
一方、会社から帰って書き置きを読んだ総一郎は、まるで知らない土地に置き去りにされた子どものようにうろたえていた。
「春枝のやつ、春枝のやつ…」
とつぶやきながら心当たりに電話をしたが、春枝の行方はわからない。
明日から年末の休みに入る。暮れの大掃除も、お節の準備も、ここ二、三日のうちに済まさなくてはならない。しかし、総一郎一人でいったい何ができると言うのだ。
途方に暮れて一晩が過ぎた。
次の朝早く、気を取り直した総一郎は、とりあえず掃除機を取り出してはみたものの、いつものように耳元でうるさく指図されないと、何をどこへどう片付けてよいのかさえわからない。ましてや台所のこととなると総一郎は三歳児も同然だった。
「もうやめた、やめた!」
総一郎は諦めて座り込んだ。
大きなため息をつきながら、春枝が居なければ何一つできない自分の姿を改めて発見した。明日か明後日になれば、まず慎一郎の家族がやって来る。姉さんは?と聞かれたらどう答えたらいいだろう。不幸ができたと言えば差し障りがある。病気で実家に帰ったと言えば心配をかける。
総一郎はふらふらと立ち上がった。
「俺の負けだ…」
春枝の言うとおり、夫婦で留守をするからと連絡するしかなさそうだ。
住所録を調べていると電話が鳴った。
「春枝か?春枝だな?どこにいるんだ、え?お前が居なきゃダメだよ、この家は…。頼むよ、何でも手伝うからさ…な?戻って来てくれ」
受話器を持つ総一郎の声は、いつになく取り乱していた。
北国を後に、春枝は再び列車に揺られている。
正月三が日は絶対に戻らないと、あんなに固く決心していたというのに、どうして電話をしてしまったのか春枝自身にもわからない。ただ、おかしいような、哀しいような複雑な笑いが何度も何度もこみ上げて来た。
「さあ、帰れば戦争よ!」
唇を結ぶ春枝を乗せた列車は、また一つ師走のトンネルに吸い込まれた。
終