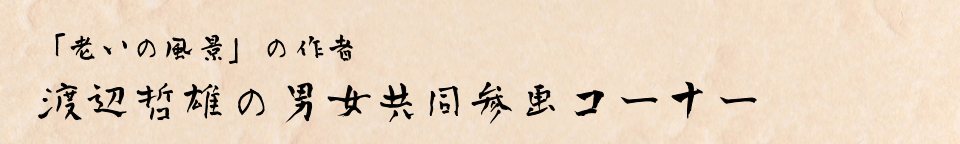- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 家族
家族
やがて十一時を刻もうとしている壁の柱時計を眺めながら、順三は由起子に声をかけた。
「おい、毎晩こんなに遅いのか?正明くんは…」
「今度のプロジェクトは特別らしいわ、彼、チームのリーダーだから責任があるのよ」
由起子は調理の手を休めずに答えた。
「それにしてもだ…」
と順三が言いかけた時、突然乾燥機のブザーが鳴って、慌てて洗面所に走って行った由起子は、かごに山盛りの洗濯物を抱えて戻って来た。
「ごめん父さん、何か言いかけてた?」
「いや、つまり、これでも家族かって思うんだよ」
「え?」
由起子は初めて順三の顔を見た。
「東京見物にやって来たつもりが、わしはお前たち家族のばらばらぶりを見物に来たような気がするよ。朝はまずお前が最初に出勤し、次が正明くんだ。由華と博明は両親のいなくなったマンションからあわただしく登校する。それぞれが勝手にトーストを焼き、一人一人が鍵を持っている。帰りももちろんばらばらで、お前が遅い時は、子どもたちは前の晩にお前がこしらえておいた料理をレンジで温めて、先に食事を済ませてしまう。これじゃ、お互いがただの同居人じゃないのかね」
「それは、そう見えなくもないだろうけど…」
「田舎にはちゃんと一家の団欒があるぞ。朝も夜も食事は全員が揃って取る。一日の出来事を争って報告しながら、そりゃあ賑やかなもんだ。たまには信之も残業して来ることもあるが、正明くんのように夜中の十一時を過ぎたりはしない。子供たちはいってらっしゃいと母親に送り出され、お帰りなさいと迎えられる。それに比べるとお前たちのはやはり家族とは言えないぞ」
「そりゃあ、お兄嫁(ねえ)さんは専業主婦だから私とは違うわよ。でもね、父さん。父さんの言う一家団欒ってのは、実はお兄嫁さんの犠牲の上に成り立っているんじゃない?」
「犠牲?」
「いつだったか田舎へ帰った時、お兄嫁さんしみじみ言ってたわよ。仕事に生き甲斐を持って生きてる私が羨ましいって。食事を作り、洗濯をし、子育てをするだけで終わってしまいそうな自分の人生が時々すごく空しくなるって。私はそんな生き方はごめんだわ。インテリアデザイナーとしていい仕事をたくさん残したいの。私たち夫婦は、妻が我慢して作り出す一家団欒よりも、夫婦が真剣に社会に参加している姿を子どもたちに見せながら生活する子育ての方を選択したのよ」
「し、しかしそれじゃあお前、妻の代わりに子どもたちが犠牲に…」
と順三が言おうとすると、玄関のドアが開いて正明が帰って来て、
「わしはもう寝るよ…」
順三はそそくさと立ち上がった。
八階の窓の外には、うっとりするような都会の夜景が広がっている。
順三が娘夫婦のマンションを訪れて三日目の朝は、いつものように追いたてられるような慌しさで始まった。ばたばたと由起子が出勤し、朝食もそこそこに正明が出かけて行き、しばらくすると由華と博明が起きて来たが、博明の元気がない。
「どうしたんだ、博明?」
と順三が聞くよりも早く、由華が博明の額に自分の額をくっつけた。
それから先の由華の行動に、順三は目を見張った。体温計をくわえさせ、弘明の学校には欠席を、自分の学校には遅れる旨の電話をかけてからタクシーを呼んだ。
「おいおい、保険証は?」
と慌てる順三に、
「だいじょうぶ、お爺ちゃんは家にいて。熱は大したことないわ。九時になったらママに連絡して。番号はここよ」
メモを残して出て行った。それは小学六年生の行動ではなかった。田舎の香織は中学一年生になるが、母親がいなければほとんど何もできないではないか。
午後の仕事をやりくりして由起子が戻って来た時には、博明は額に濡れタオルを乗せて横になっており、由華は台所でお粥をこしらえていた。
「ただの風邪よ、ママ。消化のいいもの食べさせて安静にって。お薬は食後。パパには心配いらないって病院から電話入れておいたわ。私は放課後、生徒会の集まりがあるから行くけど、ママの仕事はだいじょうぶ?」
「ありがとう。都合はついたわ。行ってらっしゃい」
「わ…わしでは役に立たないか?」
おろおろと落ち着かない順三ににっこりと微笑んで、
「行って来ます!」
由華は元気で出て行った。
「昔から、子どもたちの病気の時だけは、どんなに無理をしても正明さんと交替で仕事を休んでついていてあげることにしてるのよ」
由起子はそう言いながら素早くエプロンを身につけた。
これまでの印象とは違い、そこには確かに心を寄せ合い、いたわり合う家族の姿があった。しかも驚いたことに、小さな子どもたちまでが互いに自立して認め合っている。
「家族か…」
順三は慣れない手つきで弘明の額のタオルを替えてやりながら、母親がいなければ靴下の在り処もわからない田舎の孫たちのあどけない顔を思い浮かべていた。
終