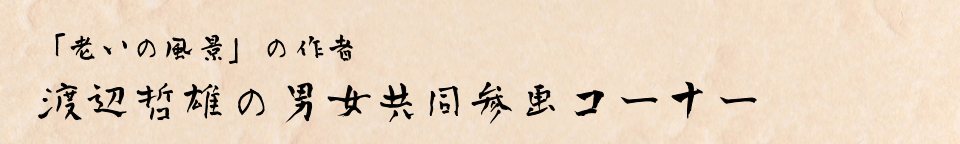- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 白衣
白衣
義母のふさが、夜トイレに立とうとしてふらふらと倒れた時、月江は自分でも驚くほど冷静だった。後で夫の隆雄が、
「お前は自分の親ではないから落ち着いていられたのだ」
と言ったが、そうではないと月江は思っている。二十年間の長きにわたって第一線の看護師として働き続けてきた月江の身体は、いつの間にか病に対しては医師のような理性に支配されるようになっていたのだ。
頭を高くして仰向けに寝かせ、衣服をくつろげて、脈と瞳孔を調べながら、
「あなた、救急車!病院には私の名前を言って電話をかけて!博司は薬箱の中から保険証を用意しなさい!それから、まゆ子はお婆ちゃんの下着と洗面用具を準備するのよ!」
てきぱきと指示をした。
もう三ヶ月以上も前のことである。
左側頭部内部に発見された出血は手術で取り除かれ、一命を取り止めはしたものの、ふさは右半身麻痺と高度の言語障害を残してリハビリの効果も限界に達した。
退院の話を切り出す時の看護師長の顔は、月江の家庭の事情が分かっているだけに暗かった。
「多少の融通はつきますが、できれば今月一杯で退院してください。ベッドに余裕があればもう少し居て頂けるのだけれど……」
「分かっています」
月江は唇をかんだ。
寝たきりのふさを家庭に引きとれば、世話をする人間が必要になる。隆雄がその役割りを引き受けてくれなければ、月江が病院を辞める以外に道はない。実はそのことで昨夜も隆雄とさんざん議論したのだ。
「まさか、男のおれがおふくろの世話をするわけには行かないだろう……」
隆雄は当然のようにそう言うが、月江にはどうしてもそれが当然とは思えない。
「あなたが転職さえしていなければ、お義母さんを私がみるのは当然かも知れないわ。だけど今のあなたの給料じゃ私が看護師を続ける方が余程得策じゃないかしら。博司も来年は大学でしょ?経済的なこともちゃんと考えた上で一番損失の少ない道を選ぶべきだと思うの」
「それは分かってるよ。分かっているけれどお前、世の中は何でも経済で割り切れるというものじゃないだろう。第一それじゃお前、世間体が悪くって町も歩けない」
「でもね、あなた。私たちがどんなに困ったところで世間は何も助けてくれないのよ。そんな世間に気を遣って、みすみす大変な道を選ぶのは馬鹿げたことだと思わない?それに私だって何も家の仕事を全部あなたに押しつける気持ちはないわ。お昼の食事は温めるだけでいいように準備をして出かけるし、洗濯だって今までどおり帰ってから私がするつもりよ。あなたはただ、お義母さんに食べさせてあげるのと、私がいない間のしもの世話だけして下さればいいのよ」
「男のおれがおふくろのしもの世話を?おいおい、いい加減にしてくれよ」
「だってあなた」
「もうたくさんだよ。とにかく、おれは外で働く。お前は仕事を辞めて家にいてくれ。それが世間の常識ってもんだ」
「あなた!」
「うるさい!何だかんだと言って、結局のところお前は、おふくろの世話をするのが嫌なんだろう!」
「???」
月江は目の前が真っ暗になった。
そして、絶望の中で、夫婦の信頼が音をたてて崩れていくのを聞いていた。
退院の日、月江は休暇をとった。
まだ、病院を辞める決心はついていなかった。しばらくは有給休暇を使いながら隆雄の説得を続けるつもりだった。
車椅子のふさを自家用車まで運び、助手席へ乗せようと抱きかかえた時、突然ふさが月江にしがみついた。
それは思いがけないくらい強い力だった。
ふさは泣いていた。
ポロポロと涙をこぼしながら声を出さずに泣いていた。
「お…お義母さん……」
怯えているのだろうか…。いや、そうではない。ふさは懸命に月江にすがっている。言葉を失い、身体の自由を失い、独りで生きていくことのできなくなったふさにとって、こうして子供のようにすがりつける相手は月江の外に唯の一人もいないのだ。
月江の決心が今ついた。
この義母が家にいて、博司とまゆ子を見ていてくれたからこそ、月江は今日まで大好きな看護師を続けて来られた。これからは自分が義母の役に立つ番なのだ。
月江が長年身に着けた純白の制服を病院に返した日、本当の看護の日々がゆっくりと始まった。
終