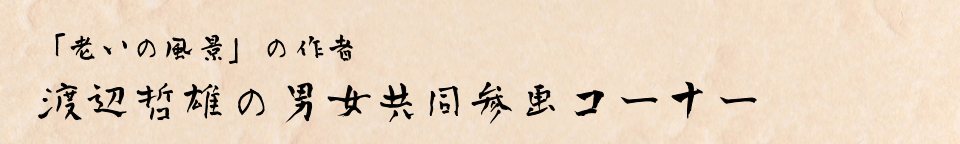- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 出不足入院
出不足入院
日曜日の朝、町内班長の鳴らすりんの音が家の外を通り過ぎていく。カーテンを開け放つと八月の空は青いスクリーンのように晴れ渡っていた。
「あなた、今日は八時から区の清掃作業よ!」
登美子が久雄に声をかけると、
「お前、頼むよ」
久雄はいつものように眠そうに答えた。
「何言ってるの。今回から女が出た場合は五百円の出不足料が取られるのよ。私、そんなの我慢ならないわ。あなたが出てくださいな」
「五百円?」 久雄はようやく布団から身体を起こして煙草をくわえた。世の中全体が男女平等の方向に進んでいるにもかかわらず、作業に出なかった場合の千五百円の出不足料に加えて、女が出た場合には、あらたに五百円を区に支払うことがこの前の総会で決まっている。
「そうか…。五百円か……」
久雄は、うまそうにふうっと煙を吐き出しながら言った。
「ちょうどいいじゃないか。女は男の三分の二しか働かなくていいって区が認めてくれたんだ。五百円払って適当にやりゃいいさ」
「ちょっと待ってよ」
登美子は昔から久雄のこういうところが理解できない。
「あなたのような考え方の人が増えたら、地域はいったいどうなるの?」
「どうもなりゃしないよ。大切な日曜日をつぶしてみんなが掃除なんかやってるからこの村は発展しない。そんなことは行政の仕事だよ。まあ、とにかく、今朝はおれが家に居ては何かと面倒なことになりそうだ。どこかで暇をつぶしてくるよ」
八時が近づくと、久雄は、さも会社の用事で出かけるようないでたちで、いそいそと車に乗り込んだ。登美子はスポーツウェアに着替えて、鎌と軍手を用意した。
適当にやりゃいいと久雄は言うが、いざ現場に出てみると、登美子はどうしてもそれができなかった。ましてや、出不足料を班長に支払って、
「女手で申し訳ありません」
と謝ってみると、それは逆に、
「女ですが精一杯頑張ります」
と、無理やり宣言させられたような不愉快な圧力となって感じられた。
登美子は、堤防の草むらにしゃがみ込んで懸命に釜を操った。ザクッ、ザクッという小気味よい音とともに、身の丈ほどもある夏草が倒れていく。時折立ち上がって腰を伸ばすと、さすがに女の姿は少ないが、代わりに年寄りの数が増えたようだ。
(馬鹿にしている…)
登美子は思った。
前田さんのところの周三爺さんも、小林さんちの喜作じいさんも、さっきからぷかりぷかりとたばこをふかしながらおしゃべりばかりしている。それでも女は、おんなであるということだけで、あの年寄りたちよりも劣っていると判断されるのだ。
五百円の差が無性に悔しかった。
「女でも男以上の働きをする人も居るでな。一律に五百円の出不足料を取るのは考えもんだと思うが……」
今年の総会でそういう意見を引き出すためには、文字どおり、男以上の仕事をするより外はない。
堤防の斜面には背の高い萱が密生している。
それを刈り取ろうと踏み出した時、足が滑り、登美子の体が宙を泳いだ。 覚えているのはそこまでである。
足から腰にかけて激痛が貫いて、登美子は気を失った。
喫茶店を三つもはしごして我が家へ戻った久雄は、近所の夫婦から富子の入院を知らされて、真っ青になってアクセルを踏んだ。
「登美子!登美子!」
久雄の声に笑顔で応えようとした登美子の顔は、ベッドの上で激しい痛みにゆがんでいた。
折れた右足は石膏で固められて天井からつり下げられている。
「いやあ、方々打ってはいるが、それでも頭を打たなくて何よりだった。気を失ったのはショックが原因だそうだ」
「ご迷惑をかけました」
久雄は登美子を運んでくれた班長に深々と頭を下げた。
「ご主人は仕事だと聞いていたもんだから、何度も会社に電話をしたんですがね?いったいどこへいってらしたんです?」
「あ、いえ、その……仕事にも色々ありまして……」
久雄はしどろもどろでごまかした。
「ま、これからは区の作業はなるべくご主人が参加してください。女の人はどうしても全ての面で男のようなわけにはいかないですからなあ……」
「あっ」
登美子は思わず叫び声を上げそうになった。
久雄がチクリといやみを言われるのは構わない。地域のことは何でも登美子に任せきりだった久雄の態度がそれで改まれば有難い。しかし登美子の怪我が、女が男に劣る証拠のように扱われるのはたまらない。
「あの……」
と言いかけた登美子の口を封じるようにまたしてもあの刺すような痛みが身体の芯をかけぬけた。
「いや、そのまま、そのまま」
班長は、登美子が礼を言おうとしたのだと勘違いしたらしい。
「私はこれで失礼しますが、どうかお大事に……」
そう言い残して診察室を出て行った。
遠ざかる班長の足音を、登美子はやりきれない思いで聞いていた。
終