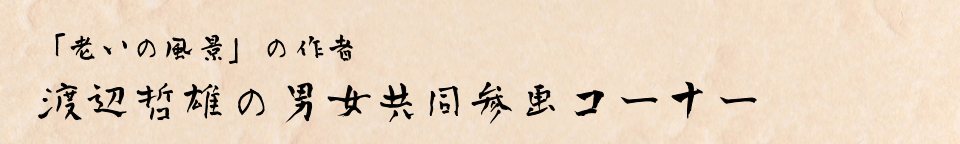- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 紙芝居
紙芝居
繁澤と名乗る老夫婦が広げて見せた紙芝居は、素晴らしい出来栄えだった。新聞紙大ほどの大きさに水彩で描かれた絵は、現在、保育園にある、どの紙芝居よりも美しかったし、ストーリーは読む者の心をとらえて離さない魅力に溢れていた。
「これをすべてあなたが?」
と尋ねると、
「はい。物語は私が作り、絵は主人が描きました」
七十歳前後かと思われる繁澤夫人は、穏やかに微笑んだ。
月一回、子どもたちに手作りの紙芝居を見せてやりたいというその老夫妻の申し出を、園として断る理由は何もなかった。
「それでは来月からお願いします」
美佐子が園長代理の主任保育士として深々と頭を下げたのは、もう三年も前のことである。
子どもを育てたことのない保育士は、園児の扱いも下手だなどと、時には陰口を叩かれながらも、美佐子が、あすなろ保育園の保育士として頑張り続けて来られたのは、病弱の母との二人暮しを支えてゆくためだけではなかったと思っている。婚期を逃し、母が死に、砂を噛むような虚しさに襲われても、
「先生おはよう!」
という園児たちの声を聞くと元気が出た。
ふり返ると、園児たちのために仕事を続けて来たというよりも、園児たちに励まされて今日までやってこられたという気がしてならない。その美佐子の生活を、定年という二文字が根こそぎ奪おうとしていた。来年の春になれば、美佐子にはもう仕事がない。夫もなく、子もなく、仕事もない初老の女を待っている生活はといえば…美佐子は想像するだけで背筋が寒くなった。紙芝居の繁澤夫妻がたまらなくうらやましかった。信頼し合える伴侶がいるというだけでなく、おそらくは二人の姿を暖かく見守っているであろう家族の存在がうらやましかった。
私には何もない…私には何もない…。
美佐子の胸を、またしてもあの虚しさが吹きぬけた。
「あ、美佐子先生がまた一人でオルガン弾いてる!」
いつも一番遅くまで園に残って親の迎えを待っているひろこちゃんが、ガラス越しに遊戯室を覗きこんで手を振った。
子どもたちの想像力には羽根が生えている。紙芝居を見つめる子どもたちの瞳が、テレビを見る時とは比べものにならないほど輝いているのは、一枚の絵の向こう側に無限に広がる想像の世界を見ることができるからに違いない。
ステージの上の絵がめくられる度に、子どもたちの表情は生き生きと変化して、物語はいよいよ最後の場面を迎えていた…が、それは同時に繁澤夫妻にとっても最後のステージになろうとしていることに、まだ誰も気づいてはいなかった。
朗読が終わると子どもたちの可愛い拍手が二人を包んだが、いつもなら、にこやかに頭を下げるはずの夫人が崩れるようにその場に倒れ込んだ。
その体を危うく抱きとめた繁澤老人を、大勢の園児たちが取り囲んだ。
「繁澤さん!繁澤さん!誰か救急車を!」
子どもたちの泣き声の中を、美佐子は夢中で行動した。
「ここへ連絡を頼みます!」
繁澤老人が差し出した手帳に書いてある番号に電話をする美佐子の指は震えていた。
何回かの発信音の後、
「はい。養護老人ホーム敬寿苑です」
という声を聞いた時、美佐子は自分の耳を疑った。
「はい…生涯売れない絵描きを貫き通した繁澤さんは、私どもの老人ホームに入所されてから幸恵さんと知り合って、初めて結婚されました。幸恵さんも全く身寄りのない一人暮らしで、なんでも昔は幼稚園の先生をしてらしたこともあるとかで、童話を作って子どもたちに聞かせたいという幸恵夫人の夢と、繁澤老人の特技とが、紙芝居という形で実を結んだのですね…」
しめやかに行われた通夜の席で、老人ホームの職員の説明を聞きながら、美佐子は溢れる涙を止めることができなかった。
哀しいだけの涙ではなかった。
(人生という紙芝居の幕が下りるまで、繁澤夫妻のように夢を追い続けてゆこう…)
膝の上でこぶしを握りしめたまま、うつむいている繁澤老人の後ろ姿を、美佐子は崇高な思いで見つめていた。
終