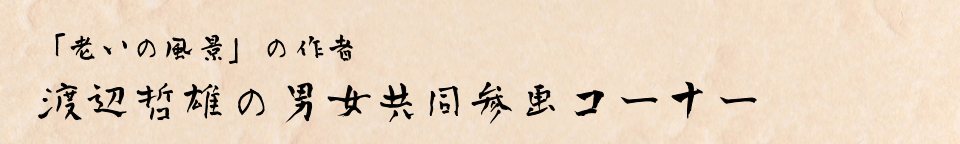- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 敏郎の遺言
敏郎の遺言
空腹時の腹痛が、かれこれ一ヶ月以上も続いているが、忙しさにかまけて放っておいた。しかしその朝、便器の底にポタリポタリと赤いものがしたたり落ちるのを発見すると、さすが医者嫌いの敏郎も、一度きちんと検査すべきだという良江の意見を無視するわけにはいかなくなった。
「恐いのね?」
と良江にからかわれて、
「馬鹿を言え。いくつになったと思っている」
笑って答えてみたものの、五十歳という年齢は十分にがん年齢である。
青白い顔をした大勢の患者たちと一緒に待合室の長椅子に腰を下ろした敏郎の心の中は、決して穏やかではいられなかった。
「鈴木敏郎さん、鈴木さん」
という病院独特のアナウンスが流れて、順番が来た。敏郎は覚悟を決めて診察室へ入った。ふり返ると、良江の顔がこわばっている。
軽口を叩いてはいるものの、内心は敏郎以上に不安を感じているのに違いない。
その日は問診だけで、検査は翌日ほとんど半日をかけて絶食下で行われた。胃の内部をカメラが巡り、腸にはバリウムが注入された。若い看護師の目の前で、屈辱的な姿勢を強いられながら、敏郎はまるで絶望の海に突き落とされたような気持ちになっていただけに、
「軽い胃潰瘍ですね。出血は内痔核からのもので心配ありません。切らないで薬で治しましょう」
という医師の言葉を聞くと、
「あ、有難うございます!」
白衣のよく似合うその青年医師に、思わず深々と頭を下げていた。
安心すると激しい便意を催した。注入したバリウムが流れ出るに違いない。敏郎は良江を診察室に残してトイレに駆け込み真っ白な便をした。戻って来ると、カーテン越しに医師と良江の話し声が聞こえて来た。はっきりとは聞き取れなかったものの、
「あまり長くはないでしょう」
という医師の言葉だけは心臓をえぐり取るような鋭さで敏郎の鼓膜に突き刺さった。
あとは何も覚えていない。
「お大事に」
という看護師の明るい声が、敏郎の背中の上に氷のような冷たさで貼り付いた。
日曜日、敏郎は散髪に出かけた。
良江は久しぶりに敏郎の仕事場の掃除をしながら、ここひと月ほどの敏郎の変化について考えていた。
胃の診察を受けてからというもの、敏郎は、はた目にも気の毒なくらいイラついていた。
「どうかしたの?」
と尋ねても、
「ん?いや、何でもない」
と言いながら、ため息ばかりついていた。
二週間ほどすると、今度は何やら真剣な顔つきで調べものをし始めた。
「何をしてるの?」
と尋ねてもやはり、何でもない…と答えながら、家中の預金通帳や年金証書を引っ張り出して来て、せっせとノートに書き写しては難しい表情でうなっていた。
そして、さらに驚くべきことには、女は家庭を守るものという信念を一度だって曲げたことのなかった敏郎が、ある日、こともあろうに、良江に適当な職場を探して来てこう言ったのである。
「お前、昔から商業簿記の腕前を生かして外で働いてみたいと言ってたなあ。これからは女も自立しなくてはだめだ。来週から行ったらどうだ」
おかげで良江は四十五歳になった今、小さな会社ではあるが、二十年ぶりに念願のオフィスウーマンになれた。
それにしても、この変わり様はいったい何なのだろう。例えば仕事場のテーブル一つとってみても、敏郎の掘り上げた印鑑は以前のように雑然と置かれてはいない。まるで店を誰かに明け渡す準備をしているかのように、客と商品の関係がきちんと整理されている。良江は何気なくひきだしを開けた。
謎はその時解けた。
鮮やかな墨跡で『遺書』と書かれた真っ白な封筒がすべてを物語っていた。
良江は血相を変えて外へ飛び出した。
さっぱりと散髪を終えて家に向かった敏郎は、息を切らして駆けて来る良江の姿に驚いた。
「ど、どうしたんだ?いったい」
「どうしたんだじゃないわよ」
良江は手に白い封筒を握りしめて涙ぐんでいる。
「水くさいじゃない!」
「ちょっと待て、興奮するな。とにかくどこかに腰を下ろそう」
二人は近くの公園のベンチに並んでかけた。
「さあ、わけを聞かせて」
良江が問い詰めると、
「知ってるはずだ」
「知ってるって何を?」
良江には解らない。
「そうやって隠すのがお前のやさしさだということはよく解る。しかし、おれはあの時、医者がお前に、あまり長くないでしょう…と話しているのを聞いてしまったんだ」
「長くない?」
「胃の検査をして長くないと言えば、それが、がんを意味しているぐらいのことは、今どき子どもでも知っている。手術をしないということは、逆に言えばもう手遅れということだ。がんはポックリとは死なない。おれが長いこと病んでみろ。家にある貯えなどすぐに底をつく。おまけにおれが死んだ後、お前に支給される遺族年金はわずかなものだ。おれは、いよいよという時は、周りに迷惑をかけないで、自分で自分の始末をつける覚悟がようやくできた。お前も自分の手で生きてゆく力を身につけてくれ。子どもたちを当てにしたくはないからなあ…」
敏郎が遠い目をしてそう言った時、良江が弾けるように笑い出した。
そのくせ顔は泣いている。
良江は泣きながら笑っているのだ。
「おいおい、笑うことはないだろう」
目を白黒させる敏郎に、
「ごめんごめん。でも私、たった今、ようやく思い出したのよ、あの時の会話」
「あの時の会話?」
「あなた、あの時、トイレに立ったでしょ?私それを見て、出血のことを思い出したのよ。それで先生に、出血はこれからも続くのですかって聞いてみたの。先生は、内痔核について色々と説明して下さった後で、こうおっしゃったわ。続いたとしても、そう長くはないでしょうって…。ちょうどその時あなたが戻って来たんだわ」
「す、するとお前、長くないってのは、つまり、その…」
「そうよ。あなたは絶対にがんなんかじゃないのよ」
「おれは…がんじゃない?」
くたくたと全身の力が抜けてゆく敏郎の目の前で、良江が勢い良く遺書を破り捨てると、足元まで近づいて来た鳩が一羽、驚いて大空へ飛び立った。
終