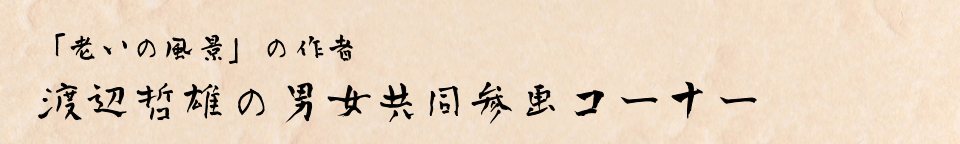- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 子離れ・夫離れ
子離れ・夫離れ
スーツケースに胃腸薬が入っていた。それが引き金になった。
「おれの体を心配してくれているんだ。そんなに目くじらを立てることじゃないだろう」
と誠治は言うが、尚美は我慢できない。
「だって夫の世話をするのは妻である私の役割でしょ?今度のことだけじゃないわ。お義母さん、いつだってあなたのことばかり考えてるのよ。似合いそうだからって、センスの悪いセーターは買って来るし、私の作った料理を食べながら、誠治には少し甘すぎるようねとかって、平気で言うし…いつだったか、あなたが長期の出張に出かける時、これをあなたにって、交通安全の御守りを手渡されたのには本当に驚いたわ。そして今度の胃腸薬でしょう?要するにお義母さんは子離れができてないのよ。やっぱり別居するしかないわ」
「またその話しかい…頼むからごたごたはおれが帰ってからにしてくれよ。第一、別居して子どもでもできてみろ。お前、仕事を辞めなきゃならなくなるんだぞ」
誠治は、はぐらかして大阪へ旅立った。
出張で大阪へ出た時は、いつも決まったビジネスホテルを利用している。三件ばかり商談をまとめてくつろいでいると、電話がかかってきた。
「もしもし?なんだ母さん…うん…大丈夫、下痢はもう治ったよ。胃腸薬?ちゃんと服んだから心配しないで」
答えながら、誠治は腹立たしくなった。
ひとり息子の誠治は、子どもの頃から母親の関心を一身に浴びて育って来た。それが結婚した今も続いている。大切に思われることに対しては十分に感謝しているが、そのために夫婦の間が気まずくなるのはたまらない。
考えてみれば、二十八歳になる息子の出張先に電話をかけて来て、体調を気遣ったりするのは、やはり、尚美の言うとおり子離れできていない母親の愚かしさというべきだろう。
これまでは黙っていた。
せっかくの親切を余計なお世話のように言うのは、思いやりに欠ける行為だと考えていた…が、それは間違っていたのかも知れない。家族の役割分担を無視した母親の行動は、放置すればやがて別居あるいは不和という形で、結局母親を苦しめることになる。
誠治は心を決めた。そして生水は飲まないようにと、とりとめのない注意を繰り返す母親の言葉を遮って、誠治は突き放すようにこう言った。
「母さん、もうたくさんだよ。ぼくの心配は尚美に任せて、母さんは放っといてよ!」
受話器を置く房枝の手は震えていた。
何だか突然、息子が遠い他人になってしまったように感じられて悲しかった。
それにしても…と、房枝は考える。母親が息子の心配をするのがそんなにいけないことなのだろうか。子どもに対する母親の愛が不変だとすれば、子どもが結婚したからといって、それを表現することを慎まなければならない理由は何もないではないか。
いや、理屈ではない。理屈ではなしに房枝は、頬を伝う熱いものをどうすることもできなかった。その時、玄関のチャイムが鳴った。
「あ、あなた、どうしてこんな時間に?」
戸惑う房枝に、
「やっぱり泣いていたな?」
周三は背広を脱ぎながら居間のソファーに腰を下ろした。
「誠治から会社に電話があったんだよ。きっと母さんが泣いているから慰めてやってくれってね」
「まあ、あの子が…」
「いやぁ、おれも今日はあいつにこっぴどくやりこめられて、返す言葉がなかったよ。お前がいつまでも子離れできないでいるのは、おれの責任でもあるとあいつは言うんだ」
「あなたの?」
「ああ。仕事、仕事で帰りは遅い。帰れば帰ったで、ゆっくりとお前と話しをする暇もなく、風呂、めし、寝る…の繰り返しだ。たまの休みはゴルフに出かけ、考えてみると夫婦で外出したことなど数えるほどしかありゃしない」
「…」
「ま、あれだ。心理学的に言えば…だ。対象を失ったお前の愛情欲求は、必然的に息子の方に向いてしまう…と、まあ、こういうわけだよ」
周三は煙草に火をつけて、遠い目をして煙の行方を追いかけた。
房枝は周三の隣りに腰掛けた。
確かにその通りかも知れない。当時としては珍しく、激しい恋愛で結ばれたはずの二人だったが、誠治が生まれ、周三の仕事が忙しくなるにつれて、房枝はいつの間にか母として、あるいは主婦として暮らす毎日の中で、ひとりの魅力ある女性としての顔を失った。気が付くと、仕事に情熱を傾ける周三と、すっかり成長した誠治との間で、房枝だけが取り残されていた。今、その生き方が、こういう形で問い直されている。
房枝の中で、ようやく何かが吹っ切れた。
誠治の言う通り、これからは息子のことは嫁に任せ、一人の女としての人生を取り戻そう。
「私、子離れも、夫離れもしてみせるから」
「おいおい、穏やかじゃないな」
二人は本当に久しぶりに顔を見合わせて笑った。
折りしも実家へ立ち寄って戻って来た尚美がびっくりするくらい、それは明るい笑顔だった。
終