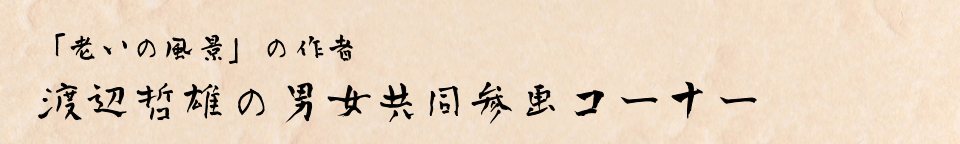- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > ホビープラザ
ホビープラザ
パンを作るのが趣味だと言っていた啓子が店を出したと聞き、訪ねてみて驚いた。
手編みのセーター、陶器、刺し子のハンカチ、ちぎり絵、自費出版の本などが、それぞれに値段をつけられて並んでいる。
「まあ、啓子ったら、こんなに色々な趣味が?」
「違うわよ、鈴江。お店の看板見たでしょ?」
「ホビープラザ?」
「そう。最初はパンのお店だったんだけど、近所の奥さんとか友だちとかが自分の作品も置かせてほしいって…。趣味も本格的になると、ただ作るだけじゃ満足できなくなるのよね。価値を認めてくれる人に、正当な価格で譲りたくなる。つまりここは、主婦たちの自己実現の広場ってわけよ」
「なるほど、自己実現ね。世界に一つしかないものばかりが並ぶお店なんて素敵だわ」
「これで結構、売れるのよ」
と笑う啓子の瞳が輝いている。
鈴江は羨ましかった。
自分にはいったい何があるのだろう。
子どもたちを育て、三年間寝たきりだった姑の介護をし終えたら、抜け殻のようになっていた。
生き甲斐になるような趣味は無い。
あるのはただ、仕事人間の夫の世話と、限りなく退屈な専業主婦の時間だけではないか。
「自己実現か…」
啓子の家からの帰り道、鈴江はつぶやいた。
つぶやいたとたん、生き甲斐を趣味の範囲でとらえていた鈴江の考えが飛躍した。
「そうだ、介護だわ!私は三年間の経験を持つ介護の技術者なのよ」
体の不自由なお年寄りのボランティアになろうと思った。
人の役に立っているという実感はきっと趣味以上に素晴らしいに違いない。
鈴江の瞳はその時、啓子に負けないくらい輝いていた。
終