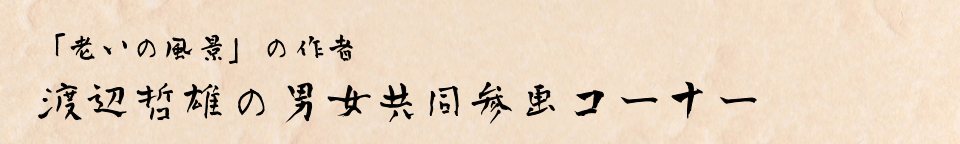- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 男のエプロン
男のエプロン
甥の博司の結婚式に出たついでに、息子のマンションに一泊した澄江は、翌日、夫の史朗が帰るのを待ち構えていたようにこう言った。
「和彦が夕食の後片付けをしていたんですよ」
「いいじゃないか、皿洗いぐらい。今は男も女もない時代だ」
「よかありませんよ。私はあなたにそんなことさせた覚えは一度もありませんからね!」
「そういうおれたちの暮らしぶりを見て育った和彦が、違う生き方をしようと思ってるんだろうから、放っておけばいいんだよ」
「でも…」
澄江は納得できなかった。
確かに自分には姑がいて、夫に家事を手伝わせようなんて口に出すことさえできなかったが、家のことは誰にも頼らず何もかも一人でやって来たことが、結局、主婦としての自信につながっている。そして、主婦に揺るぎない自信があることが家庭円満の基本なのだ。
「私、ちょっと美津子のアパートに出かけて来ます。引き出物の電子ポットが、ちょうどあの子が欲しがっていたタイプのだから、届けてやりたいんですよ」
澄江はそういい残して家を出た。
「で、どうだったの?博くんの披露宴」
澄江の顔を覗きこむ美津子に、
「博司よりも実は和彦がね…」
と言おうとすると、
「お義母さん、どうぞごゆっくり」
美津子の夫の雅弘がコーヒーを運んで来て、澄江は慌てて次の言葉を飲み込んだ。
ここでも夫が当たり前のように台所に立っている。
「ありがとう」
花柄のコーヒーカップを受け取った時、澄江の心がふいに軽くなった。
美津子は幸せそうだ。
その幸せを夫のやさしさが支えている。
大切なのは主婦の自信ではなくて、協力し合える夫婦の自信なのだ。
澄江の脳裏に、エプロン姿で流し台の前に立つ和彦の笑顔が浮かんでいた。
終