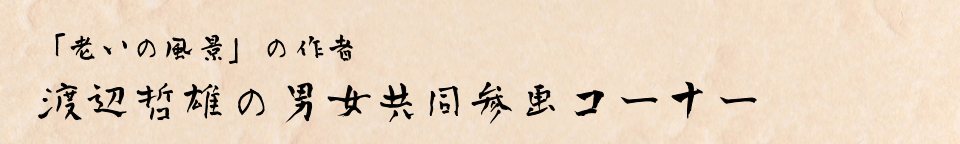- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 待合室
待合室
神経内科の待合室の片隅で居住まいを正す中山照子の横顔の厳しさに、深沢美幸は一瞬声をかけるのをためらった。昨年の暮れの同窓会では飲んで歌って花の熟年を謳歌し、
「要するに、子育てさえクリアーすれば大丈夫。女もきちんとした仕事に就いていれば、夫にも子どもにも頼らない、自由と生き甲斐が手に入るわ。これからは女が自立する時代よ」
と気炎を上げていた照子ではなかったか。
「どうしたの?照子、こんなところで」
耳元で、ささやくように美幸が尋ねると、驚いて振り向いた照子の傍らに、車椅子のお年寄りが虚ろな視線を漂わせている。
「あなたの?」
「母よ。兄嫁が体調を崩したの。私が面倒を看るしかないのよ」
「脳梗塞ね、うちの義父と同じだわ」
美幸が指差した長椅子の上の老人は、右の手足が絶えず小刻みに震えている。
「私、甘かったわ…」
照子がつぶやいた。
「同窓会の頃は何もかもが順調で、私、鬼の首を取ったみたいに自立自立って言っていたけど、女の自立って意識の問題だけじゃ済まないのよね」
「?」
「子どもと年寄りの世話を社会がきちんと保障するか、世話をする間の女の立場を守る仕組みを作らない限り、女が自立する時代はほど遠いのよ」
「照子、あなたまさか仕事を?」
「辞めたわ。母が大切だから…」
「そう…」
美幸は、すぐには慰める言葉を見出せなかった。
母が大切だからと言いながらしっかりと握りしめた照子のこぶしの白さが、病院を出てからも美幸の心に焼き付いたまま離れなかった。
終