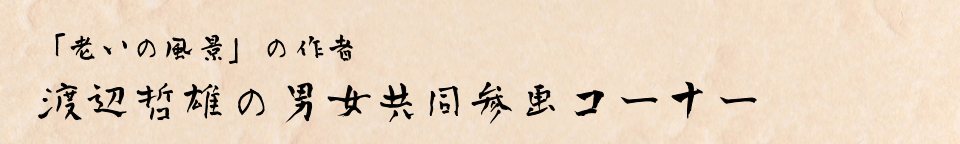- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 鍵っ子の夢
鍵っ子の夢
夕食の材料を買い込んだスーパーの袋を提げてマンションのエレベーターを五階で下りた佐藤英子は、隣りの部屋の鉄の扉の前にうずくまる小さな人影を発見して立ち止まった。ランドセルを背負った矢島慎吾が冷たいコンクリートの上でしょんぼりと膝を抱えている。
「どうしたの?慎くん。風邪を引くでしょ」
鍵をなくしたという慎吾をとりあえず自分の部屋の食堂に座らせて温かいココアを作りながら、英子は最近の若い親の身勝手さに憤りを感じていた。
慎吾の母親は看護師をしている。そのために家事がおろそかになるのを夫が理解してくれないといつも嘆いていた。二人は離婚をし、養育費の代わりに手に入れたマンションで、慎吾は鍵っ子になった。
(女の自立が流行ってるけど、家事も育児も片手間じゃできないわよ。ただいま!と帰ってくる子どもを笑顔で迎えてやるのが母親の努めじゃない)
英子は、おいしそうにココアをすする慎吾の姿に、この春大学に入学して寮生活を始めたひとり息子の圭司の子ども時代を思い出していた。
平凡な専業主婦だった英子は圭司に淋しい思いをさせたことだけは断じてない。
「ねえ慎くん、大きくなったら何になるの?」
何気なく英子が尋ねると、慎吾は目を輝かせて思いがけない返事をした。
「僕、お医者さんになるんだ」
「お医者さん?」
「お母さんのように、困っている人を助ける仕事をしたいんだ」
英子は胸が熱くなった。
慎吾は自分を置いて仕事に出る母親を尊敬している。
「あ、慎くん、おいしいケーキがあるのよ」
英子は慌てて冷蔵庫を開けた。
そして、圭司から母として大切にされることはあっても、一人の社会人として尊敬されることはないだろう自分を少し淋しく感じていた。
終