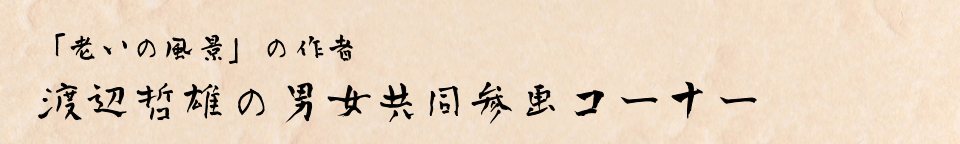- ホーム > 男女共同参画コーナー/目次 > 女の敵は女
女の敵は女
化粧を直しにやって来た光代と洋子は、総務課に書類を届けに出かけたはずの玲子が、まさかトイレに入っているとは気づかないで鏡の前で立ち話しを始めた。
「信じられる?育児休業よ、育児休業」
「そうよ、私たちの時代は嫌な思いをして姑に子供を頼むか実家に預けるかして、かろうじて働き続けたものだわよねえ」
「課長も課長だわ。玲子ちゃん一年間しっかり子育てに専念するんだよ、なんて猫撫で声出しちゃってさあ。若い子には甘いんだから」
「…で、玲子の仕事は結局私たちに回って来るんでしょ?バイトを入れるとか言ってるけど、すぐには使いものにはならないし、バイトに何もかも任せるって訳にはいかないものね」
「あ~あ、女のツケはやっぱり女が払うのかあ…。割りに合わないわよね、私たち」
二人の会話を聞きながら玲子は唇を噛んだ。法律で認められた権利を行使することのどこがいけないのよ!と叫びたい気持ちとは裏腹に、まるで悪いことをして隠れているように息をひそめている自分が情けなかった…と、その時、
「ちょっとあんたたち、女が女の足引っ張ってどうするの!廊下まで聞こえてるわよ」
昨年、女癖の悪い夫と別れて母子家庭になった田口先輩の声が加わった。
「私たちが苦労したからこそ、若い人には同じ苦しみを味わわせたくないんじゃない。育児休業を有給にするとか、代替職員の確保を要求するとか、女の権利を守るためには、まだまだやるべきことが山ほどあるわ。これからは女がお互いを支え合うために、みんなで主張する時代なのよ」
その通りだと玲子は思った。男も女もない。職場の労働条件を改善するためには、働く仲間たちとねばり強く連帯すべきなのだ。
眉を上げてドアを開ける玲子のお腹の中で、小さな生命がピクリと動いた。
終