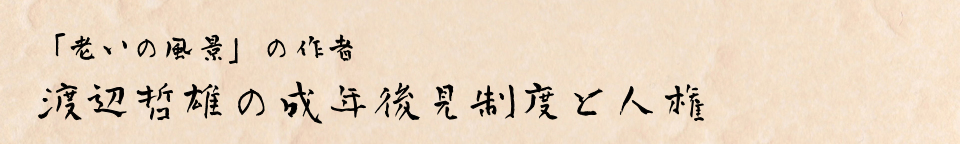- ホーム > 成年後見制度と人権/目次 > 親爺の再婚
親爺の再婚
二十歳も年下の女との再婚を宣言した啓太郎に、当然ながら子供たちは猛反発をした。
「お父さん、今年八十歳よ。再婚なんかしたら、財産の半分は訳のわかんない飲み屋の女に渡ってしまう。それでもいいの?」
「籍入れなくったって同棲でいいじゃないか」
「そうよ、女の目的は財産に決まってるわ」
「再婚するんなら、財産は全て私たち三人に残すって遺言を書いてからにして欲しいわ」
「遺言はだめよ、妻には遺留分がある」
「だったら生前贈与は?贈与税を取られたって財産が半分になるよりはましじゃない?」
「うるさい!わしは寝るぞ」
三人を睨み付けて敬太郎は寝室にこもった。
「やれやれ、億という財産を持つ会社の創業者も、おふくろが死んでからボケたのかな」
「そうよ!お父さん、ボケたのよ!」
「何だ、嬉しそうに」
「確かボケた人の財産を守る何とかという制度があるって聞いたことがある」
「成年後見制度だ!お前、よく気がついたな」
次の日、三人を代表して長男の啓助が会社の顧問弁護士に相談すると、
「社長、勘違いされてるようですが、制度はご本人の権利を守るためのものですからねえ…」
たとえ判断能力が衰えていたとしても、基本的な権利である婚姻は制限できなかった。
相手の女性と率直に話し合った方がいいという弁護士の助言に従って、その晩、居酒屋『ふるさと』の暖簾をくぐろうとした啓助は、中から聞こえて来る啓太郎の声に立ち止った。
「…だから、わしは、子供たちに、あんたと再婚すると言ってやったんだよ」
「まあ、会長ったら、悪い冗談を…」
「しかし、誰もわしの再婚を祝福する者はいなかった。役割も妻も失くしたわしの幸せより、みんな財産のことばかり気にしとる」
会社は大きくしたが、子育てには失敗したみたいだな…という啓太郎の言葉が啓助の胸に深々と突き刺さった。
終